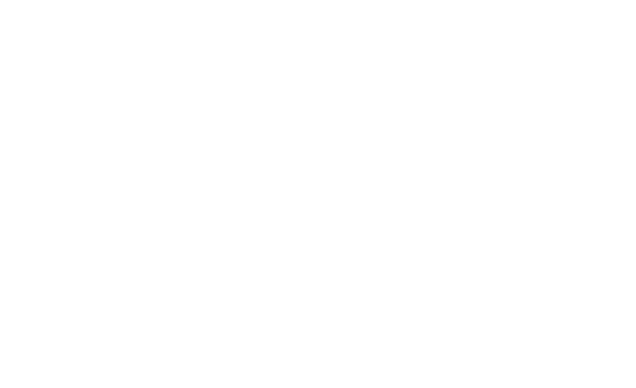|
���낵����� ��12���@���̂Q �Q�O�O�T�N�V���Q�X�� |
|
2004�N11������ՂŃs���V�L��^��������ؑ��A���A�O����������A�T�R�A���� |
�k���̓y�����l����
�\�\�k���l���𗬁E��p�ҁi�F�O���j�K�⎖�ƂɎQ�����ā\�\
���s��w��w�@�l�ԁE���w�����ȏC�m�ے�
����M���
�͂��߂�
�@2004�N7�����{�A���͖k���l���i�k���̓y�j�̂����̈�A�F�O����K�₷��@����B1992�N���n�܂����A���I�����ɂ�邢����u�r�U�Ȃ��𗬁v�̈�Ƃ��Ă̓n�q�ł���B
�@�u�r�U�Ȃ��𗬁v�Ƃ́A1991�N�̃S���o�`���t�E�\�A�M�哝�̖K�����A�C���r���Ƃ̊ԂŔ��\���ꂽ���\���������̒��Ō��y����A���̌�̐Ղ��o�Ęg�g�݂�����ꂽ���x�ł���B����ɂ��A�]������́u�k���̓y�ɋ��Z���Ă����ҁv�i�������Ƃ��̐e���j�ɂ���Q�ɉ����A�u�k���̓y�Ԋҗv���^���W�ҁv�u�W�ҁv�̎��R�K����F�߂���悤�ɂȂ����i��Ɂu���̖K��̖ړI�Ɏ����銈�����s�����Ɓv���K�⎑�i�̈�ɉ�����ꂽ�j[1]�B
�@����A�O���ȃ��V�A�ہE�ے��⍲�̐�㋱��Y���i���m������w�u���낵���v����2����e�ҁj����A���m������w�̉����j�N�搶��ʂ��āA�K��c�Q���ւ̂��U�����������B���̂Ƃ���A���́u���I���j�v�̐�U�����̂��Ă���ɂ�������炸�A�k���̓y���ւ̋����S�͔��������B���l����u�k���̓y���ɂ��Ăǂ��v���H�v�Ǝ��₳��Ă��A������������̂Ȃ��ԓ�������Ɏ~�܂��Ă����B�܂�A�{���I�Ȗ��ӎ�������Ă��Ȃ������̂ł���B����́A�u���V�A�ɂ��Ċw��ł���ҁv�ɂƂ��āA�{���ɒp������������ł������B
�@�܂��́A�u�S���͈ꌩ�ɔ@�����v�i�u�S���v�����͏d�v���Ǝv���Ă��邪�j�B�C�m�ے��Ō�̊w�N�ł���A�k���̓y�֓n�q�ł���̂��A����������Ƃ��ꂪ�ŏ��ōŌ�̃`�����X��������Ȃ��Ǝv���A�K��c�ւ̎Q�������ӂ����̂ł���B
���O����
�@����̐F�O���ւ̖K�⎖�Ƃ́A�Ɨ��s���@�l�E�k���̓y����i�ȉ��A�k���j�ƁA�k���l���𗬖k�C�����i�ψ���̋��Âɂ����̂ł���B�u�l���𗬌�p�ҖK��v�Ɩ��ł��Ă���悤�ɁA���ϔN������Ȃ��Ă��Ă���u�Ԋҗv���^���W�ҁv�̌�p�҂��琬���邱�ƂɁA���̖ړI���������B�����搶���F�O���֍s�������Ƃ���������Ă����̂����A�u�Ⴂ�w���A�Љ�l�N��A��čs���v�̂����ł��邽�߁A��㎁���疳���ƌ���ꂽ�炵���A�c�O�����Ȃ��l�q�ł������B
�@�ŏ��ɎQ����]�ɂ��Ă̏Ɖ�������̂�5���B���̌�A�K��1�����O��6�����ɂȂ��āA�悤�₭��̓I�ȓ����E�s���̂��m�点�����������A�K�v���ނ����낦�đ��₩�ɖk���̎����ǂɑ��t�����B����ƕ��s���āA�O���Ȃ̐�㎁�ɂ͂����Z�̒��A�K��c�Q���ւ̐��E��܂ō쐬���Ă����������B��㎁����́u�ό��C���ōs���Ă��Ă��������v�ƌ����Ă����̂ŁA�{���ɋC�y�ȋC���ŏo���̓���҂��]��ł����B���A�����͖≮�������Ȃ��B���O�ɁA�k���̎����ǂ����u���肢�v������Ă��܂����̂ł���B
�@��́A�u�[�H�𗬉�v�ł̊y��̉��t�˗��B���E��쐬�̂��߂̃v���t�B�[���Ɂu��E���Z�F�y�퉉�t�v�ƋL�q���Ă����̂��A�^�����i�H�j�����ǂ̖ڂɗ��܂��Ă��܂����̂ł���B�d�b�ł̖₢���킹�ɑ��A�M�^�[���g�����y�b�g�Ȃ�\�Ɠ����Ă������B���ǂ̓g�����y�b�g�i���m�ɂ̓t�����[�Q���z�����j���������݂ʼn��t���邱�ƂɂȂ�A���̂��ߏo���܂ł̊ԁA���V�A�Ɠ��{�̈����̂Ȃǐ��Ȃ��A���h�߂��̊���̉͌��ŗ��K������X���������B
�@������́A�F�O���K�⎞�ɗ\�肳��Ă��郍�V�A�l�Z���ƖK��c�Ƃ́u�Θb�W��v�ł́A������̈˗��ł���B�Q���҂̒��ɂ́A���ɂ��k���̓y���ɊS���[���w�����������낤���A�����炭���I�W���U���Ă���w���͎���l�ł��������߁A���̂悤�ȑ�������t���邱�ƂɂȂ����̂ł���B�o����2�T�ԑO�A�����ǒ����璼�X�ɁA�����������Ɣ����̗v�_�̃������X������Ă����B�u�Ԋҗv���^���W�ҁv���g����߂����g�ŎQ������Ƃ͂����A��w�@���ł��鎄���g����Ă���̂́u�Ԋҗv���^���v�ł͂Ȃ��A���I�W�ɂ��Ắu�����E�����v�ł���B���́A����I�ɗ̓y�Ԋ҂�i���邱�ƂɏI�n���邱�ƂȂ��A���{���E���V�A���̗���A�O�����̌o�܂��ÂɌ��������A�_���I�Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B����5�����x�̔������e���쐬�����̂ł��邪�A���O�i�\���u�����v���Ǝ��ӂ����������j�̂��Ƃ��Ǝv���A�������邱�Ƃ�����Ă����k���̓y���ɂ��ĕ��������A�ǂ��@��ɂȂ����B���̍��A���傤�Ǔǂ�ł��������V���L�҂̍����a�Y�E��ؖ��`�ɂ��w���E���I��]���x�i��g���X�A2003�N�j���A�u�̓y���v���̗v�_�����邤���ő�ϖ��ɗ������B������̓��e�ɂ��Ă͌�q����B
�@��ɁA�u�S���͈ꌩ�ɔ@�����v�Əq�ׂ��B�������A�u�ꕷ�v���������āu�ꌩ�v�����Ƃ��Ă��A����͖��Ӗ��Ȃ��Ƃ��Ǝv���B�u�ꌩ�v����O�ɁA������Ɓu�S���v���Ă������Ƃ��K�v�Ȃ��Ƃł��낤�B
�k���̓y�u�őO���v�̊X�E������
�@���O�����������A���悢��7��21�����߂��A���{�q��3131�ւŖ��É���`���ї������B2���Ԏ�̃t���C�g���I���A���H��`�ɒ��������̊��z�́u�����v�̈ꌾ�ł������B���Ƃ̖��É��≺�h���Ă��鋞�s�Ɣ�ׁA�����͒���Ƃ�10������15���قNjC�����Ⴍ�A����ɂ��̓��͏��J���~���Ă������炾�낤�B
�@��`�o�X�ŋ��H�w�ֈړ�������AJR�����{���ŏI���w�E������ڎw�����B���̃��[�J�����͖q��A�R�сA�C�݂ȂǑ厩�R�̒��𑖂�A�S�H�̂��ŃV�J����ђ��˂�p������ꂽ�B�r���̒�ԉw�ł������(��������)�́A���܂�m���Ă��Ȃ����A���O�˂ƃ��V�A�l���l�̍ŏ��̐ڐG���������ꏊ�ł�����[2]�B
�@�����ɓ����������ɂ́A7�����Ƃ͂����A�������Â��Ȃ��Ă����B�ߌ�8���܂łɍ����O�����h�z�e���Ŏ����葱�����ς܂����ƂɂȂ��Ă����̂ŁA�����ɓk���Ō������B�d�b�ňȑO����A�����Ƃ��Ă����k�������ǂ̕��X��A���̎Q���w���Ƃ��A�����ŏ��߂Ċ�����킹���B��ɂ͍��e������˂ĖK��c���ŗ[�H�ɏo�������B
�@��閾���āA7��22���B���̓��͖k���ɂ���p�ҖK�⎖�Ƃ̑����ڂŁA�����s���ŏo���O�̎��O���C���s��ꂽ�B���A�܂��͔[���z������k���̓y�����@���ׂ��A�K��c��s�̓o�X�ňړ������B��v���H�ȂǁA�s���̎���Ƃ���Ɂu�Ԃ��I�@�k���̓y�v�Ƃ����悤�ȊŔ�������B�����́A���V�A�ɂ��u�s�@�苒�v���ꂽ�k���l����ڑO�Ɍ��镶���ʂ�́u�őO���v�ł���Ɠ����ɁA�Ԋҗv���^���́u�őO���v�ł��������B
�@���̓��́A�K���ɂ����V�Ɍb�܂�A�[���z���������Ŏ����Q���⍑�㓇��F�߂邱�Ƃ��ł����B��������[3]�̍��z���D���Q���Ȃ��ĉ��݂𑖂�p�͑u���ł��������A���������ɖڂ�����A������ł��߂������Q���E�L�k(��������)���ɎK�тČX�������䂪�����A���̕t�߂ɂ̓��V�A�̍����x���������Ă���B�[���z���ɂ���u�k���فv�Ƃ��������قł́A30�����̖K��c�����e�X���ȏЉ����A�k�������ǒ��E�g�z���Ƒ�B��w�����̉������j�搶���猤�C�����B���s���ꂽ�����搶�́u�|���i�؍����E�Ɠ��j���v�̐��Ƃł���A�k���̓y���Ƃ̔�r�̊ϓ_���炲�u�������������B
�@�ߌォ��͎s�X�n�֖߂�A�����O�����h�z�e�����ׂ́u�瓇��فv�ŁA�F�O���E�ΌÒO(���Ⴑ����)�̌������ł��链�\(�Ƃ��̂�)�����A�\�A�N�U���̗l�q�Ȃǂɂ��Ă��b�����B���̌�A���s�ʖ�̊ȒP�ȃ��V�A��u���A�K�⎞�̖������S���߂Ȃǂ��ς܂��A�����ڂ̌��C���e�����ׂďI�����B
�@������A�����O�����h�z�e���ɂāA���㓇�܂œr�����D����k�C�����i�ψ���ƍ����ŁA���c���ƌ𗬉�Â��ꂽ�B�Ȃ��A�k�C���Ƃ̋��Âɂ�鍡��̌�p�ҖK��́A�O�N�ɍs����\�肾���������p�ҖK�₪���V��ɂ��o�q���O�Œ��~�ƂȂ��Ă������߁A������́u����v�ł��������B

���������E�[���z���ɗ��M�ҁ@2004.7.22
�u�R�[�����z���C�g�v���o�q
�@7��23���A���悢��o�q�̒����}�����B�����`�̊ݕǂł́A�k���Ɩk�C�����i�ψ���̖K��c�����W�����ďo�������s��ꂽ�B9�����A�W�҂̌�������Ȃ���A���U��̋q�D�u�R�[�����z���C�g�v���ŏo�q�B��������́A�k�C���̒c�����K�₷�鍑�㓇���o�R���ĐF�O���������A4���Ԃ̑D���ƂȂ�B
�@�O���Ɉ��������ēV�C�Ɍb�܂�A�g�����₩�ł��������߁A�D�͉Ă̒g�����k�̊C������悤�ɐi�B�o������1���Ԃ�����ƁA�������C��́u���ԓ_�v�i������́u�������v�j��ʉ߂��A������̂��߂��Ă����C��ۈ����̏������Ƃ͂����ŕʂ�̍��}�i�D�J�j�𑗂荇�����B���{���{�͖k���l���ɂ����郍�V�A���̎{�����𐳎��ɔF�߂Ă��Ȃ��B�Ƃ͂����A�����̒n��ɓ��{�̍����@���y��ł����ł��Ȃ��B���{�͑D�̒��ŁA�B��u���ԓ_�v���z���邱�Ƃ��ł���̂��A���́u�r�U�Ȃ��n�q�D�v�Ȃ̂ł���B�Ȃ��A�u���ԓ_�v�̌������̓��V�A�i�T�n�����j���ԂƂȂ邽�߁A�T�}�[�^�C���̒����������2���ԑ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��i���{�̐��߂́A�k���l���ł͌ߌ�2���ƂȂ�j�B
�@�D���̈���ڂƎl���ڂ́A���㓇��K�₷��k�C�����i�ψ���̃����o�[�����D���Ă����B���̂��ߑD���͑z�����Ă����������������A�H������ւłƂ邱�ƂɂȂ����B���Ȃ݂ɁA���̎Q�������k���̖K��c�́A�w����Љ�l�N�̎Q���҂��قƂ�ǂł��������A�k�C���̖K��c���͍��Z�����猳�����A����E����c���܂ŗl�X�ł������B�Ƃ���ŁA���́u�R�[�����z���C�g�v���B���{�̋q�D�ł���A���R�Ȃ���D���ȉ��A�D���݂͂ȓ��{�l�ŁA�H���Œ��E���E�ӂƏo�����̂����{�H�B�����͕ʂ̖ړI�Ō������ꂽ���A���͂����ς�r�U�Ȃ��n�q�̂��߂Ɏg�p����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B
�@�[���A���㓇�E�Ê��z(�ӂ邩�܂���)�p�ɓ������A�ꎞ�┑�B�`�̐��[�����߁A�x(�͂���)���g���Ă̏㗤�ƂȂ�B�x�D�Ƃ͂����A�ݕ��ςݍ~�낵�p�̌��\�ȑ傫���ł������B���̑D�́A���{���{���u�l���x�������v�Ƃ��Ďl�����ɑ��������̂ł���A�u���̊ہv�������ǂ����Ԃ��~�̃}�[�N�̎���ɂ́A�s�B �H�N�@�K �D�Q�T�G�A�\�^�O�S �`�P�O�N�R�K�O�C�O �N�@�Q�O�D�@�t�i�F�D�̈�Ɂ^���{�������瑡��ꂽ�j�ƋL����Ă����B���s�̊O���ȐE���ƍ��㓇�̒S�����̗���̉��A�k�C�����i�ψ�����o�[�́u����葱���v���s���A��l�����x�ɏ�芷���Ă������B�u����v�Ƃ������t�����Ƃ��~�\�ł���B
�@�k�C���g�ƕʂ�Ă���A�u�R�[�����z���C�g�v���͈�H�A�F�O����ڎw���B�I�����W�F�̗[�Ă���̒��A�ǂ�����Ƃ��Ȃ��J����������Ă��đD�ɋ߂Â��Ă���B�[�H���I�����D���ł́A�����̖K�⎞�ɗ\�肳��Ă���u�������͂މ�v�̑ł����킹��A�u���I�����𗬁v�i���[�A���Ȃǁj�̏��������X�Ɛi�߂�ꂽ�B
�@���V�A���Ԃ̌ߌ�10���i���{���ԁ��ߌ�8���j�߂��A�F�O���k�����̌���(���Ȃ�)�i���N���{�U�{�c�N�j�p�ɓ����B�ӂ�͔��Â����A�b����́A��������ƍ`�p�̒n�`�Ƌ͂��Ȍ����̖����肪������B��Ԃ̏㗤�͂ł��Ȃ����A���ɂ͖K��c���S�������܂��悤�ȃz�e�����Ȃ��̂ŁA���̓�����͘p�̒����ɒ┑���Ȃ���̑D�����i3���j�ƂȂ�B�q�D���ɂ̓V�����[����J�[�h�����O�d�b�i�q���d�b�j������A��������ɂ͊T�ˉ��K�ł��������A����ł������ȓ�i�x�b�h�ɂ͐����A�������B�K��c�����m�荇���܂ł́u�Ԃ̑��l�v�������Ƃ͂����A��������D�ɏ���Ă��܂��Ή^�������́B�k�b���i�i���j�ƐH���i�։��j�́A�c���̌e���̏�A�𗬂̏�ƂȂ����B
�F�O���K�����ځ\�\������
�@7��24���ߑO7���i���{���ԁ��ߑO5���j�A�u���H�̏������ł��܂����I�v�Ƃ����D�������Ŕۉ��Ȃ��N����������B���������c�����Ă���A���V�A���ԂƓ��{���Ԃ̂ǂ���Ő������Ă��ǂ��̂����i���Ȃ݂ɑD���ł͓��{���ԁj�A���{���Ԃōs�����Ă������ɂƂ��ẮA���i�̐�������͍l�����Ȃ��N�����Ԃ������B���H���ς܂��b�ɏo��ƁA���܂̒��Řp���̑S�i�����n����B�u�R�[�����z���C�g�v���͂������ƌ������̎V���ɋ߂Â��Ă����B�N���{�U�{�c�N�i�K���p�q���x�p�r���t���{�j�Ƃ������V�A�����\���Ă���悤�ɁA�����́u�J�j�i�{���p�q�j�̍H��i�x�p�r���t�j�v�̑��ł���B
�@�����ŁA�k���l������ѐF�O���̌�����������Ă������Ƃɂ��悤�B���{�ł́u�l���v�Ƃ����悤�ɁA�𑨓��A���㓇�A�F�O���A�����Q���i��̓��ł͂Ȃ��j���ꊇ��ɑ������邱�Ƃ��������A���V�A���̍s���敪�͂���Ƃ͈قȂ�B�u�l���v�́A���V�A��89����u�A�M�\����́v�̂����̈�ł���T�n�����B�ɑ����A���̒��́u�s����v�Ƃ��āu�N�����n��i�K�����y�|�����{�y�z ���p�z���~�j�v�i�V���V�����A�E���b�v���A�𑨓��j�Ɓu��N�����n��i�_�w�~���{�����y�|�����{�y�z ���p�z���~�j�v�i���㓇�A�F�O���A�����Q���j�̓�����݂��Ă���B���́u��N�����n��v��1��3��������A���㓇�ɂ͌Ê��z�i�����W�m�N�����X�N���j�Ɣ�(�Ƃ܂�)�i���S���u�j�m���j���A�F�O���ɂ͎ΌÒO�i���}���N�����X�N���j�ƌ����i���N���{�U�{�c�N���j�����݂��Ă����ł���B�F�O���̐l���͖�2100�l�B���㓇�̖�4300�l�ƍ��킹��ƁA�u��N�����n��v�̏Z���͖�6400�l�ł���B�u�N�����n��v�i�𑨓��j�̖�7800�l�ƍ��v����A�l���S�̂Ŗ�1��4200�l�̃��V�A�l�Z�������邱�Ƃ�������[4]�B���Ă͐F�O����1038�l�A�k���l���ɂ�1��7291�l�̓��{�l��������炵�Ă���[5]�B
�@���݁A�u�N�����n��v�̃V���V���i�V�m�j���ƃE���b�v�i�����j���A�u��N�����n��v�̎����Q���ɂ͏Z���͂��Ȃ��Ƃ����B���ɁA�[���z���́u�ڂƕ@�̐�v�ɂ��鎕���Q���i�ȑO�A���{�l���Z��ł����j�ɂ́A���V�A�����x�������풓���Ă���݂̂ł���B�������A2004�N9��7���̋����ʐM�̕ŁA�����Q���̗E��(���)���Ŗ��Ԍ������������������Ƃ����炩�ɂȂ���[6]�B
�@�D�͂������ƎV���t�߂ɒ��݂���B�D��Ŏ����Ǒ��ƃ��V�A���ǂ̒S�����Ǝ����ł����킹���I���ƁA�K��c���͈�l���_�Ă���A�u����葱���v���s��ꂽ�B�^���b�v������A�ߑO9�����i���{���ԁ��ߑO7�����j�ɐF�O���㗤�B�������p�ҖK��̑����ڂ��n�܂����B
�@�㗤����ƁA20�l�قǂ̃��V�A�l�����̏o�}��������A�����ߑ��𒅂��Ⴂ��������u�p���Ɖ��v�̂��ĂȂ������B�n���̎q���Ƀ��V�A��Řb�������Ă݂Ă��A�p�����������ł͂��邪�A�����Ɖ�b�ɓ����Ă����B�K��c���㗤���������i���N���{�U�{�c�N�A���Ȃ킿�u�J�j�H��v�j�ɂ́A�`�ɗאڂ��Đ��Y���H�H�ꂪ����B���̍H��͑𑨓��ɋ��_��u���M�h���X�g���C�Ђ̎q��Ђ̎{�݂������ŁA���́A��s���㗤�����V�����`���A���̍H��̕~�n���ɂ������B�M�h���X�g���C�Ђ́A1991�N�ɍ��c��Ƃ���薯�c�����ꂽ��ЂŁA���X�͍`�p�E�͐���̃[�l�R���������炵�����A���V�A�o�ύ����̒��ŗl�X�Ȏ��Ƃ�W�J���Ȃ��琬�����A���ł́u�N�����n��v����сu��N�����n��v�ōő�̐��Y���H��Ђ��P���Ɏ��悤�ɂȂ���[7]�B�㗤����ƁA�܂��͌����H��ӔC�҂̃p�i�Z���R���̈ē��̉��A���Y�H��������@�����B���i�̑唼�͗A�o�p�Ƃ̂��Ƃł���A�H����ɂ̓n���O���̈�����ꂽ�i�{�[�������ς܂�Ă����B
�@���̌�A���̕�����ق֓k���ňړ����A�ߑO10����菬���ȃz�[�����Łu�����\�h�K��v�Ɓu�������͂މ�v���s��ꂽ�B�u�͂މ�v�ł́A�������̃Z�f�B�t�������A���̌���Ɋւ��鎄�����̎���Ɉ������Ă������B
�@�ߑO11������A����ɂ��錊�����w�Z�֎Ԃňړ��B�A�X�t�@���g�̓��H�͐��Y�H��~�n���ɂ����������ŁA���̓��H�͂��ׂč������B�ܑ����͂ق�0���ł���B�Ԃ���������ɍ����������オ�邽�߁A�t�@�X�i�[��߂��o�b�O�̒��ɂ܂ō������荞��ł����B���w�Z�̓v���n�u����̈�K���ĂŐ^�V�����A�b�ł�1994�N�̖k�C���������n�k�œ|�����̂��A���{����̐l�������ʼn��݂����炵���B���w�Z�ł́A�܂����{��w�K�T�[�N���u���E�V�E�j�v�N���u�̎q������������{��̈��A�A�����ă_�l���A�搶�i�����j����u���V�A��u���v���������B�����āu���I�����𗬁v�Ƃ��āA�F�O���̎q�������ɁA���{�̗V�тƎ��[������ɒ��킵�Ă�������B���{��ł͒Z���͏ォ�牺�ւ̏c���������\�\�q�������͉������i���V�A��j�̊��ꂽ����ŁA���ꂼ��肢������������ł����B�����Љ�悤�B
�E���{�ꂪ�ł���悤�ɂȂ肽���B�^���{��̒ʖ�ɂȂ肽���B
�E���������ɂȂ�܂��悤�ɁB
�E�e�����l�X�����N�ł���܂��悤�ɁB
�E���ׂĂ̐l�X���K���ł���܂��悤�ɁB
�E�v�����Z�X�̂悤���Y��ȗm�����~�����B
�E���̓��ł����ƕp�ɂɎ���������܂��悤�ɁB
�E���{�ɍs���Ă݂����B�^���{�̖{�B�ȓ�ɍs���Ă݂����B
�@�ǂ��֍s���Ă��A�q���͓����悤�Ȃ��Ƃ��l������̂ł���B�����F�O���ɂ͖��N�A�l���𗬂⎩�R�K��œ��{�l������Ă��邵�A���{�ꂪ������x�w�K����Ă��邽�߂��A���{�ւ̍D��S���F�Z���o���Z�����������ꂽ�B
�Θb�W��ɂ�����X�s�[�`
�@�������w�Z�̋����ł́A�u���V�A��u���v�u���I�����𗬁v�Ɉ��������A���߂�����F�O���Z���Ƃ́u�Θb�W��v���J���ꂽ�B�����k�������ǂ���˗�����Ă����̂́A���̏W��ł̓��{������̊�����ł���B
�@���e�����O�ɗp�ӂ���ہA�����ǂ���̎w�E������A���̎O�_�͐��荞�ނ悤���ӂ��Ă����B��ڂ́u�v�[�`���哝�̗̂̓y�����������Ă̈ӎu�v�A��ڂ́u�����錾�ɂ�������I���{�Ԃ̍��ӓ��e�v�A�O�ڂ́u���a��������i�̓y��������j�̓��I�������́w�����x�̂�����v[8]�ł���B�K��c���u�Θb�W��v�ŐF�O���Z���ƈӌ�����������O��Ƃ��āA�����̔F���͐���Ƃ����L���Ă����������̂ł������B
�@�������A�����ɁA���{���{���ߔN�̗̓y���ŋ���ǂ���ɂ��Ă��铌���錾�́u���E�v�ɂ��Ă��A���{�����\���ɒm���Ă����K�v������ƍl���Ă����B���錾�̃|�C���g�́A���Ɂu�k���l���̓�������āA���̋A���ɂ��Ă̖����������ĕ��a����������A�����W�����S�ɐ��퉻����Ƃ����菇�m�ɂ������Ɓv�A���Ɂu�w���j�I�E�@�I�����x�w�����̊Ԃō��ӂ̏�쐬���ꂽ�������x�w�@�Ɛ��`�̌����x�Ƃ����O�̗v�f�ɂ���āA�̓y��������������j�����ӂ��ꂽ���Ɓv�ɂ���Ƃ����[9]�B�Ƃ��낪�A���錾�̃��V�A�����Q�Ƃ��Ă݂�Ƃǂ����B�����ł́A�̓y�����������ĕ��a�����������Ƃ����u�菇�v�i�O��W�j���K���������m�ɂ���Ă���Ƃ͌�����[10]�A�܂��u�@�Ɛ��`�̌����v�ɂ��Ă����{�Ƃ̊ԂɁu���x���v������������̂ł���B���V�A���̒��Łu�@�Ɛ��`�̌����v�ɊY������̂́A�s�����y�~���y�����r �x�p�{���~�~�������y
�y �������p�r�u�t�|�y�r�������y�t�ł���B�����ł́u�@�i�x�p�{���~�~���������j�v�́u�K�@���^���@���v���Ӗ����邪�A�u���`�i�������p�r�u�t�|�y�r���������j�v�́u�������^�������^���R���v�܂Ŋܒ~���Ă���B�܂��A�u�@�v�͂�����x�q�ϐ�������ɂ��Ă��A�u���`�v�͗������̊ԂŊu����̂����ϓI�Ȃ��̂ł��邩������Ȃ��\�\�B���s��w��w�@�̎w�������E�ؑ����搶�����������w�E����Ă��邱�Ƃ����A���͈�Έ�őΉ����Ă����ł͂Ȃ��A�j���A���X�ɂ̓Y��������B�u�@�Ɛ��`�v���X���[�K���̂悤�ɘA�Ă��Ă��A�K�������k���̓y�Ԋ҂ɋ߂Â��Ƃ͌���Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ�����A�K��c���ƃ��V�A�l�Z��������i��҂�1�����o����A���̐i�s�Łu�Θb�W��v�͎n�܂����B�`���͎�����̊�ł������B�����ɂȂ邪�A�����̃X�s�[�`���e���ȉ��A�S���f�ڂ���B
�@���W�܂�̊F���܁A����ɂ��́B�{���A���{����̎�҂����ƁA�F�O���ݏZ���V�A�l�̊F���܂Ƃ̊ԂŁA�L�v�Șb���������ł��邱�Ƃ��A��ϊ�����v���Ă���܂��B���{�����\�������܂��āA�܂����̕�����������N�������Ă��������A�����ɉ����āA�o���̊����Ȉӌ������ɂȂ��邱�Ƃ��ł���K���ł��B
�@�����m�̕��������Ǝv���܂����A���N6���A�č��ŊJ�Â��ꂽG8��]��i�V�[�A�C�����h�E�T�~�b�g�j�ɍۂ��āA�v�[�`���哝�̂Ə���Ƃ̊Ԃœ��I��]��k���s�Ȃ��܂����B�����ŗ�����]�́A���N2005�N���u���D�ʍD���v����150���N�ɓ�����A���j�I�ɏd�v�Ȑߖڂ̔N�ł���Ƃ��āA���I�����ŋL�O�s�����J�Â��邱�Ƃō��ӂ��Ă��܂��B���̏�ő哝�̂́A2005�N���߂ɖK���������A�Ƃ����ӌ���\�����܂����B
�@�܂����a�����ŁA�v�[�`���哝�̂́u�̓y�����������ĕ��a����������邱�Ƃ��K�v�v�ł���A�u�����͂��̖��[11]�̓��c����������͂Ȃ��v�ƌ������Ă��܂��B�̓y�������ɑ���哝�̂̂��̂悤�ȍl���́A1993�N�ɃG���c�B���哝�̂ƍא�ɂ���Ĕ��\���ꂽ�u�����錾�v�Ɋ�Â����̂ł��B
�@�����錾�ɂ́A���I�������u�𑨓��A���㓇�A�F�O���y�ю����Q���̋A���Ɋւ�����v���u���j�I�E�@�I�����ɗ��r���A�����̊Ԃō��ӂ̏�쐬���ꂽ�������y�і@�Ɛ��`�̌�������b�Ƃ��ĉ������邱�Ƃɂ�蕽�a���𑁊��ɒ�������悤�����p�����A�����ė����Ԃ̊W�����S�ɐ��퉻���ׂ��v���Ɩ��L����Ă��܂��B6���̎�]��k��ɍs�Ȃ�ꂽ�������t������O����k�ł��A�u�l���̋A���̖����������ĕ��a�����������v�Ƃ������������m�F����Ă���悤�ɁA�u�����錾�v�͗������{�̈ˋ����ׂ����ӁA���ʕ��j�ł���ƌ����܂��B
�@���āA��قǏq�ׂ܂����悤�ɁA���N�œ��I�C�D150���N���}���܂��B�u�E���b�v���Ƒ𑨓��̊Ԃō�������肷��v�Ƃ����j�R���C�ꐢ�P�߂̂��ƁA�v�`���[�`��������q�A�����s�E��H(���킶)���(�Ƃ�������)�Ƃ̊ԂŌ���������A1855�N2���A�u���D�ʍD���v������܂����B����ɂ���āA���V�A�Ɠ��{�͍��������сA�����͕��a�I�ɗ̓y���̈�����������̂ł��B���̌�A�������͊��x������������܂����A���I�����̍������������ȏ�Ԃɒu����Ă��錻�݁A���́u���D�ʍD���v�́A��X���Ăї����Ԃ�ׂ����ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���̉��c�ł̏����ɍۂ��āA������[���G�s�\�[�h������܂��B���̍Œ��A�ɓ��ɒ┑���������v�`���[�`����s�̃t���Q�[�g�́u�f�B�A�i���v���A�����̑�n�k�i1854�N�j�ɂ��Ôg�ő�j���A���v���Ă��܂����̂ł��B�K���A���V�A�l���v�͓��{�̋����ɂ��~������܂����B���̌�A�ɓ������̌˓c(�ւ�)���Ń��V�A�l�̊ē̉��A���{�l�D��H�����͂��āA���{���̗m�����D�ƂȂ�X�N�[�i�[�́u�w�_���v����������܂��B�v�`���[�`����͏���A�����A���̓r�ɂ����Ƃ��ł��܂����B���̏o�����́A���{�̋ߑ㑢�D�Ɣ��W�̑b�ƂȂ����_�ŁA�܂�150�N�O�Ƀ��V�A�l�Ɠ��{�l�̋��͎��Ƃ��s�Ȃ�ꂽ�_�ŁA���ڂ��ׂ����̂��Ǝv���܂��B
�@���c�ł́u���D�ʍD���v�������ƁA����Ɠ����ɋN�������u�w�_���v�����̃G�s�\�[�h�́A���B�ɂ��ꂩ��̓��I�W�̂�������������Ă���Ă��܂��B���ƊԂ̊W���P�ƁA���Ԃ̗F�D�E���͂́A�����ĕʁX�̂��̂ł͂Ȃ��̂ł��B�u���D�ʍD���v����150�N���}���悤�Ƃ��Ă��鍡�A���V�A�Ɠ��{�́A�v�`���[�`���Ɛ�H�̐������f�A�u�w�_���v�����ɂƂ��Ȃ����I�̖��ԋ��͂Ƃ�����̗��j�I�ȏo�������A����Ƃ����K�����ł͂���܂��B
�@�̓y���̉����ƂƂ��ɕ��a����������A���̖k���l���́A���I�������ɂƂ��Ắu�ӌ��s��v�v�̏ے�����A�u�F�D�E���́v�̏ے��ւƕω����邱�Ƃł��傤�B�V���{���Ƃ��������łȂ��A�F�D�E���͂̎����I�ȋ��_�Ƃ��āA���������W�𐋂���\��������̂ł��B���̂��߂ɂ��A�߂������̗������́u�����v�̂�����ɂ��āA�������͏\���ɑΘb���d�˂Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�����ɁA�̓y���̉����́A���V�A�l�Z���̗��v�����Ȃ���`�ōs�Ȃ�����̂ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��m�F���Ă����K�v������ł��傤�B
�@���̑Θb�W���ǂ��@��Ƃ��āA��قǐG��܂����u�����錾�v�̓��I���{�Ԃ̍��ӓ��e��A���a��������̓��I�������́u�����v�̂�����ɂ��āA�F���܂Ƙb�������A���ݓI�Ȉӌ��������ł���Ǝv���Ă��܂��B�܂����I�C�D150���N�����ẮA�F���܂���̐ϋɓI�ȒȂǂ����}�������܂��B
�@���������肪�Ƃ��������܂����B
�@�K��c���s�̑哇���ɒ����ʖ�����肢���A10���قǂŃX�s�[�`�͏I������B���̌�A�F�O����������A�h�D�_�[�G�t���̊���������B���́A�����܂߁A���j�I�o�܂����邱�Ƃ��A���I�������̎��_�Ƃ��ďd�v�v�Əq�ׂ��B�܂��u�F�O���̈�ʏZ���́w�����Ɓx�ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ȃ�����A�u�����������t�̏�ǂ�����������A�����ł��Ȃ����͂Ȃ��v�Ƌ��������B
�@�u�Θb�W��v�̘_�_�́A�u�����v�Ƃ����L�[���[�h�Ɉڂ��Ă������B�K��c������́u�̓y�������Ƃ���ɔ��������ɂ��āA�ǂ���������肪���邩�v�Ƃ̖₢�ɑ��āA�����N�̏Z���́u�������s���v�u�̓y�������͎�҂̈ӎv�ɔC���v�u�Â��ȘV�オ��炵�����v�ƌ��𑵂����B�����ĕω������߂����Ȃ��\�\���ɓI�ȍl�����ł͂��邪�A���ꂪ�ނ�̖{���ł��������B
�@�u���œ��{�l�ƈꏏ�ɏZ�߂邩�H�v�Ƃ̎���ɂ́A�o�Ȃ������V�A�l�Z����20�l�̂����O���̈�قǂ����肵�����A���ɓ��{�����u���Ń��V�A�l�ƈꏏ�ɏZ�߂邩�H�v�Ɩ����ƁA�K��c���̈�l������������Ȃ������B�����Ƃ��A���́u���x���v�͎d���Ȃ����̂��낤�B���ɁA�K��c�̎Q���҂ɂ͖k���l���Ő��������ՂȂǂȂ��i�F�O���̌������Ȃ�A���I�������łȂ�����A���̑������肷����̂Ǝv����j�B���ɁA�ނ炪�P�Ɂu���ŋ�������v�ƌ������ꍇ�A����̂܂܂Łi���V�A�̎{�����Łj���{�l�ƈꏏ�ɏZ�ނ��Ƃ�z�����Ă��邩������Ȃ�����A�ނ�ɂ͊������u�z�X�g�ӎ��v������B�ׂɓ��{�l���Z�ނ��Ƃ��炢���ł��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��낤���B�������A���{�����l���Ă���̂́A�̓y�ԊҌ�Ɂi�{���ւ̈ڏZ���u�����v���Ȃ����ƂŁj��������ł��낤���V�A�n�Z���ƁA���{�l�Ƃ̋����ł���B���̓_�A�b�������̑O��ɐH���Ⴂ���������\���͔ۂ߂Ȃ��B
�@�܂��A�l�I�ɂ́A�u�����v�Ƃ������t�̃j���A���X�ɂ�������肪�������Ǝv���B���{��ł̋����́A�u�����E���h�v�ɋ߂����ۓI�ȈӖ��Ŏg���邱�Ƃ������B�������A���̑Θb�W��ł́A�u���������v�u�G���v�Ƃ������j���A���X���������r�}�u�����~���u �������w�y�r�p�~�y�u�Ɩ�Ă����B�����ʂ�Ɂu���ۂɓ��ňꏏ�ɏZ�߂邩�ǂ����v�Ƃ������Ƃ���̏œ_�Ƃ��ꂽ�̂�������Ȃ��̂ł���B�u���a�����v�ƌ����ꍇ�Ɏg�������������u�����r���r�p�~�y�u�i�����j�Ȃǂ��܂߁A���̑I��������ׂ��ł͂Ȃ��������v���B
�@�Ƃ�����A���́u�Θb�W��v�ł͐F�O���Z���̈ӎ��i�u�r�U�Ȃ��𗬁v�Ɋւ���Ă���ꕔ�����̈ӎ��ł���A�u���ψӎ��v�Ƃ܂ł͌���Ȃ�[12]�j��m�邱�Ƃ��ł��A�L�v�Șb�������̋@������Ă����Ƃ͊m���ł���B��X�́u�O�����v�ł͂Ȃ��B������̓y��������K�v�͂Ȃ����A�ނ��낵�Ă͂����Ȃ��Ƃ��v���B��p�ҖK��c�ɂł��邱�Ƃ́A�u������̎咣��b���A����̎咣���v�\�\����ȍŏ����̂��Ƃ����ŏ\���ł͂Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�A�u�r�U�Ȃ��n�q�v�̘g�g�݂��ł�������ȑO�ɂ́A���ꂷ��s�\�ł������̂�����B�Ō�ɁA�������̃Z�f�B�t�����́u�������_�����ɂ��āA�v�[�`���哝�̂͂����Ȃ錈�f�ł��Ȃ����낤�v�Əq�ׂĂ����B�k���̓y���̉������l���Ă�����ŁA�����Ė����ł��Ȃ������ł��낤�B
�z�[���r�W�b�g�A�[�H��ł̌�
�@�ߌ�1�����Ɂu�Θb�W��v���I������̂��A�K��c��4�A5�����̔ǂɕ�����āu�z�[���r�W�b�g�v�ɏo�������B�h�����Ƃ��Ȃ��u�z�[���X�e�C�v�ł͂Ȃ��A���H���̉ƒ�ł��������ɂȂ�Ƃ������̂ŁA�e�ǂƂ��A�z�X�g�t�@�~���[�̎Ԃňړ������B
�@���̔ǂ́A�������܂ߊw��4�l�ƊO���ȃ��V�A�ۂ̕������̌v5�l����Ȃ�A�Z����_�[�`���ł͂Ȃ��A���O�ł̒��H��ɏ��҂��ꂽ�B���������ъԂɂ����n�ɓ����������ɂ́A��̉��ŁA���łɐH���̏����������Ă����B�z�X�g�t�@�~���[�̓Z���Q�C�A�I���K�E�|�^�y���R�v�ȂƁA�����J�[�`���i12�j�A���j�C�����[�i5�j�B���̓��́A�q���̗F�l�̒a�����Ƃ������ƂŁA���̉Ƒ���e���E�F�l�Ȃ�10�l�ȏオ�W�܂��Ă���A�ɂ��₩�ȐH����ƂȂ����B�����A�K��c�ɂ�4�������v���̒ʖ��炸�A���̔ǂɂ͓��s���Ȃ��������߁A�����O�����w�̍�������Ǝ��Ƃʼn��Ƃ����̑���߂��B
�@�e�[�u���ɂ́A�E�n�[�i���X�[�v�j��z�^�e�̎h�g�̂ق��A����ނ𒆐S�Ƃ����������������ƕ���ł���B�u���t�v�̌�A�����ɐ�ۂ�ł��Ȃ���A�v���[���g������k�b���y���B�z�X�g�̕v�Z���Q�C����͋��t�ŁA�����A�ԍ�A���H�ɓ��`���邱�Ƃ������Ƃ��B�Ȃ̃I���K����͓��̍s���{�E���Ƃ��ē����Ă���A��ŕ������b�ł́A���H��ɂ����Ă����ޏ��̕�e�͈ȑO���炱�̓��ɏZ��ł���Ƃ̂��Ƃł������B
�@�����Ă��Ă���ׂ̗ŁA����j�����ʔ��������̍����������Ă��ꂽ�B�C�N���̃s���[�`�E�~�k�[�g�N�i�������� �}�y�~�������{���u5���v�̈Ӂj�Ƃ��������ŁA�����ɂ�5 ����������Ȃ��B�܂��A�����ɑ��ʂ̐H����n�����B���ɁA���̂����̒��ɋ؎q�����A��̕��ł悭���݂Ȃ���ق����Ă����B����Ńs���[�`�E�~�k�[�g�N�̏o���オ��B����Ή����̑��Ȃ̃C�N���ŁA�������Ă����ɐH�ׂ��邱�Ƃ���D�܂��炵���B�����t�����X�p���ɏ悹�A�E�H�b�J�ƂƂ��Ɉ���j�������B�O���u�~�� �r�{�����~��!�i�����I�j
�@�H�����ςނƁA�ǂ̃����o�[�̓��V�A�l�Ƒ���ƂƂ��ɁA�o���[�{�[���⏬��ł̋��ނ�i�����ŁA�������u����H���v��ԁj�ɋ������B��������O�ł̒��H��̑�햡���낤�B�y�������Ԃ͂����ɉ߂������Ă��܂����̂ŁA3���Ԃقǂ́u�z�[���r�W�b�g�v�͖{���ɂ����Ƃ����ԂɏI�����Ă��܂����B�K�����Ԃ̒��ŁA���V�A�l�����ƍł��g�߂ɁA�܂��ł��a�₩�Ɍ𗬂��ł����̂����̎��������Ǝv���B
�@�u�܂�������邩��v�Ɣނ�ƕʂ����������A���x�́u�[�H�𗬉�v�̂��߁A�F�O���k�����̑��E�ΌÒO�i���}���N�����X�N�j�֏o�������B�r���A�������̏��X�Ɋ��A���E�^�o�R�Ȃǂ̓y�Y�������߁A�v�X�Ɂu�{��v�̃}���[�W�i�G�i�A�C�X�N���[���j��H�ׂ��B�����ōs�g�������[�u���́A�㗤�O�Ɂu�R�[�����z���C�g�v���D���ŁA2000�~������ɗ��ւ��Ă���������̂ł���B�������[�g��1���[�u����4.34�~���낤���A460���[�u�������̏������������B�^�]���Ă��ꂽ�Z���Q�C����̍D�ӂŁA�����ƎΌÒO�̒��ԂɈʒu����C�����̌i���n�E�}�^�R�^���ɂ�������邱�Ƃ��ł����B�������y�ɖ��܂��Ă��鋌�\�A�R�̎K�т��p��ԂȂǒ��������̂��������A�������Ȃ����������A�ۂ݂�тт��}�^�R�^���̊C�ݐ��́A�m�������ƂƂ��ɐ��E���R��Y�ɓo�^���Ăق����Ǝv���قǔ��������̂ł������B
�@�F�O���̐l������2100�l�ł��邱�Ƃ͏�q�������A���̓���͌�������1000�l��A�ΌÒO����1100�l���ƂȂ��Ă��āA�����̑��ɂ���ē��������ɓ���邩�����ɂȂ��Ă���B�ߌ�6���߂��A�ΌÒO�����S���֓����B�����x���������݂���ΌÒO�́A�u��ꂽ���v�Ƃ�����ۂ��@���Ȃ������ɔ�ׁA�܂��X�Ɋ��C���������B�u�[�H�𗬉�v�́A�C�����̃��C���X�g���[�g�ɖʂ����F�O������̃��X�g�����ŊJ���ꂽ�B
�@�[�H��͎ΌÒO������s�E�J���}�C�R���j�̈��A�Ŏn�܂�A��p�ҖK��c���̊ۓc�����瓚��̃X�s�[�`����������A���t�B�����Ŏ��̏o�Ԃł���B�P�[�X����y������o���i�킴�킴�����Ă��Ȃ����A�����ł͊y��P�[�X��������������Ԃňړ����Ă���j�A�����������ƁA���V�A��Łu������g�����y�b�g�Ń��V�A�Ɠ��{�̉̋Ȃ����t���܂��B�ǂ������������������v�Əq�ׁA�y��𐁂��n�߂��B���́A���Ɉ��݂������E�H�b�J���c���Ă������߁A�K���ɂ��S���ْ������S�n�悭���t�ł����i���A�����ɂǂꂾ�����s�����������܂�o���Ă��Ȃ��j�B�Ƃ�����A���{�́u�ӂ邳�Ɓv�u�l�ӂ̉́v��A�u�J�`���[�V���v�u���v���g�[�N�i�R�y�~�y�z ���|�p�������u�{�j�v�Ƃ������R��I�ȃ��V�A�����̂�I�Ȃ����̂͑吳���ł������B�A���R�[���̎��Ԃ����Ղ��A�\�z�ȏ�̍D�]�ł������Ǝv���B�]�k�ƂȂ邪�A�k�������ǂ̕�����́A�����㗤�O�ɍb�ŗ��K���Ă������߂��A�u�����炢�̃g�����y�b�^�[�v�Ƃ̂������������Ă��܂����B
�@�X�P�W���[���̐����A1���ԂƂ����Z���[�H��ł������B�ԂōĂь����̎V���ɖ߂�A�ߌ�8���i���{���ԁ��ߌ�6���j�A�J�����̑�Q�Ɍ�������悤�ɂ��āu�R�[�����z���C�g�v���ɏ�D�B�����p���ɒ┑���邽�߁A�o�q�����B
�@����ځi23���j�͂��̂悤�Ɂu�ړ��v�Ɓu�s���v���ڂ܂��邵���A�������̂����A����ɂ͖������B����ڂ�7��24���́u���V�A�C�R�L�O���v�ɂ����邻���ŁA���̐l�X�͂��̊֘A�s���ɏo�Ȃ��˂Ȃ炸�A���{�̖K��c�ɂ͍\���Ă����Ȃ��B���̂��߁A���Z�v�V�����s���Ȃǂ̂قƂ�ǂ�����ڂɏW�����Ă��܂����̂ł���B�t�Ɍ����ƁA����ڂ��������ɏI������A����ڂ́u�ό��C���v�ł��ǂ������B
 �@�@
�@�@
�@�@�z�[���r�W�b�g�ł̈�R�}�@2004.7.24�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�H��ɂāA���V�A�����̂����t����M�ҁ@2004.7.24
�F�O���K�����ځ\�\�ΌÒO��
�@�K�����ڂ�7��25���A�O���Ɠ������ߑO7���i���{���ԁ��ߑO5���j�Ɂu���H�̑D�������v�ŋN���B�����ł͒P���ȃ��V�A���̐H������ł������̂ŁA�D��ł̓��{���̒��H�i���X�`�A�Ă��C�ہA�[���Ȃǂ��o�Ă���j�͗L�������B�u�R�[�����z���C�g�v���͍Ăь��ԑ��E���Y�H��̎V���ɋ߂Â��Ă����B�����āA���V�A���ԌߑO9���߂��A����ڂƓ����悤�Ɂu����葱���v���o�čď㗤�����B
�@������s�́A����̎Ԃɕ��悵�A�ΌÒO���Ɉړ�����B�����܂߁u��p�ҁv�ɊY������Ⴂ�j���K��c���́A�O���Ɉ��������A���\�A���̗��q�g���b�N�ɋl�ߍ��܂ꂽ�B���̃g���b�N�͌R���p�ԗ���f�i������{���l�b�g�������A�Z�ΐF�̎ԑ̂ɁA�ƃI�����W�F�œh��ꂽ���S�����ڂ��Ă���p�����Ƃ��~�X�}�b�`�������̂ŁA�K��c������́u�l�R�o�X�v�Ƃ̈��̂ŌĂ�Ă����B
�@�ߑO10���A�܂��͎ΌÒO�p�E�����̍���ɋߔN�V�z���ꂽ���V�A������̎��@�ƂȂ����B���䂩��́A�ΌÒO�p�̑S�i�����n���A���V�A�����x�����̊�n��������B���́A���������F�O�����̑��E�ΌÒO�̍`�𗘗p�ł����A�킴�킴�����̐��Y���H��Џ��L�̎V������㗤������Ȃ��������R�͂��̓_�ɂ���B�C�R�����풓���Ă��Ȃ����A�����́u�R�`�v�Ɠ����B�����x������n���o�b�N�ɂ��Ă̎ʐ^�B�e�����߂�ꂽ�B
�@���̓��͓��j���ŐV���ɐ���҂����������߁A�������̌��w�܂�30���ȏ�҂����ꂽ���낤���B�����ɓ���Ɛ^�V�����C�R�m�X�^�X�i����j�̑O�ŁA�h�~�g���[�_�������������B���̐����̓A���N�T���h���E�l�t�X�L�[�̑��q�_�j�[���E���X�R�t�X�L�[�i���X�N���̃_�j�[���j�̖��������Ă���A��N8���ɗ�����������Ƃ̂��Ƃł���B�A��ہA�_�����珑�ЂƃJ�[�h�^�C�R���i����I�I�j��q���B�Ԃł̈ړ����A�K��c�ɓ��s���������́u�r�U�Ȃ��𗬁v�S���҂̈�l�E�h�D�_�[�G�t���Ɂu���Ȃ���������M���Ă���̂��H�v�Ɛq�˂Ă݂�ƁA�u���̓��X�������v�Ɠ������B�k���l���ɂ́A���ɃE�N���C�i��x�����[�V�A�R�[�J�T�X�Ȃǂ���ڏZ���Ă����l�������B�F�O���̏Z�����u���V�A�l�v�ƈꊇ��ɂł��Ȃ��ʂ����邾�낤�B
�@���āA���̎ΌÒO���̓��V�A���Ń}���N�����X�N�i�M�p�|���{�����y�|�����{�j�ƌĂ�Ă���B���{��ł́u���N�����v���Ӗ�����B���V�A�ł́i�k���l�����܂߂��j�瓇�i�N���������j�̕��ޕ��@�͈�ł͂Ȃ��A�s���敪�Ƃ��Ắu�N�����n��v�u��N�����n��v�A���R�Ɩk���̓y���w���ꍇ�́u��N�����v�̑��ɁA�u��N�����v�u���N�����v�Ƃ����敪�����݂��Ă���B�u��N�����v�́A�k�̓J���`���g�J�����암�̃V�����V���i���j�����獑�㓇�܂ł̗ŁA�I�z�[�c�N�C�Ƒ����m�̋��Ɉʒu����m���E�����������̊Ԃɓ˂��h����悤�Ȍ`���Ȃ��Ă���B����u���N�����v�́A���������̐�[�E�[���z���̉�������ɂ��鎕���Q���A�F�O�����w���Ă���B���́u���N�����v�̑��̑��i������Ȃ����j�ł��邽�߁A�}���N�����X�N�Ɩ������ꂽ�̂ł��낤�B1956�N�A�����̃\�A�����\�����錾�̒��ō��ӂ����A���a��������̎����Q���ƐF�O���̈����n�����A����������ɂ���������u��s�ԊҘ_�v���A���́u��E���v�̒n���I�敪�Ɋ�Â������̂ƍl�����Ȃ��͂Ȃ��B
�@�b��߂����B�ΌÒO�̍��䂩��ӂ��Ƃ̑��։��肽�K��c��s�́A���x�́u���I�e�P�T�b�J�[���v���s����O���E���h�Ɍ��������B�u�O���E���h�v�Ƃ͂����Ă����F���u�`�̋����������ƕ����Ă���\�\�u�����͖q��H�v�Ǝv�����ݓ����ƁA�\�z�I���B���́u���e�v�����������ɗ����Ă����B�e�P�����̂��ߊw���ƎЉ�l�ɂ��ɂ킩�u���{��\�v������������A�F�O���̋����T�b�J�[�`�[���ɂ͓G���͂����Ȃ��A�n�����N�Ƃ̑ΐ�ƂȂ����B�K��c���P�킵�����A���ʂ�2��5�ŐF�O�`�[���̏����ɏI������B�O���E���h�ł́A���̑��u���ɂ�����v�u�o���[���E�A�[�g�v�ȂǂŁA��ʓ����Ƃ̊y�����𗬂̈ꎞ���߂������B
�@���߉߂��A�ΌÒO�p�݂ɓk���ňړ����A�u���V�A�C�R�̓��v�L�O���T�����w����B���i�͍����x�������u����Ă��邾���̐F�O���ɂ��A���̓��͊C�R�͒������`���A�L�O���T�i���e�͗ǂ�������Ȃ������j�ƌP���̃f�����X�g���[�V�������s��ꂽ�B���T���n�܂�܂ł̊ԁA��ʐ����ɓ������Ă����Z�[���[���̎Ⴂ�����Ƙb���@����B�X�q�Ɂs�}�������{�p�� �������p�~�p�t�i�C��x�����j�ƋL����Ă����̂ŁA���m�ɂ͍����x�������炵���B�ނ͖����A���x���g�Ƃ����A�I�Z�`�A�o�g��18�B�ނ����̖K��c���ɓn�����M�k�̃����ɂ́u�T���[���m���X�����̈��A�n�A�F�l�����I�v�Ə�����Ă����B�ގ��g�C�X�������k�Ȃ̂��낤�B�ݓ�1�N�ɂȂ�Ƃ����A�u�I�Z�`�A�̉Ă�50���߂��ɂȂ邩��A�����m�F�O���n�̉Ắw�~�x�݂����Ȃ��̂��v�Ƙb���Ă��ꂽ�B���̖�1������ɋN�������k�I�Z�`�A���a���E�x�X�����ł́u�w�Z���Ă����莖���v�i2004�N9���j���A�ނ͂ǂ̂悤�Ɍ��邱�ƂɂȂ����̂��낤���B
�@���T���I����āA��X���Ԃɏ�荞�ނƂ��A���傤�ǐ���������𐬂��ċA���Ă����Ƃ���ł������B���R�ɂ��A���x���g��������ƁA������������U���Ă��ꂽ�B���͂Ƃ����Ɂu�P�p�{�p!�i���Ⴀ�I�j�v�ƍ������B���V�A����w�юn�߂Ĉȗ��A�e�����ʂ�̌��t������قǂɂ����R�Ɍ�����o���̂͏��߂Ă̂��Ƃł������B

���ŏo������N�E�A���x���g�@2004.7.25
�C�l���V���A�ΌÒO�ł̕�Q
�@�ԂŎΌÒO���o��������s�́A��q�̃}�^�R�^���̓���A�F�O���̂قڒ����Ɉʒu���鑐�n�Œ��H���Ƃ����B���������Ă��������������ƈꏏ�ɐH�������̂����A�e�[�u���ɂ̓J�j�A�J�j�A�J�j�B�v�킸�R�ς݂ƂȂ����ԍ�K�j�ƋL�O�B�e�������Ȃ�قǂł������B�����ł̑��̐H����Ɣ�ׂ�ƁA�c�����m�̉�b�͊i�i�ɏ��Ȃ������ƋL�����Ă���B
�@���H��́A�������炳��ɓ쉺���A�F�O����݂̌i���n�E�C�l���V���ɂ�����{�l��n�ɍs�����ƂɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪�ߌ�3���ɏo����������A��s�̎ԗ�̂�����1��̃��S���Ԃ��A�זv�������ɕЗւ��Ƃ��Ă��܂��B�c���̑������u��x�͂��邾�낤�v�Ɨ\�z���Ă����A�N�V�f���g�ł��������A10�l������ŎԂ������Ă��r�N�Ƃ����Ȃ��B���ǁA�u�l�R�o�X�v�Ō������ĕ����A���������B
�@�C�l���V���ɓ�������ƁA��������ɁA�X�Βn�ɂ�����{�l��n2��ɕ�Q�B��O�͕���������݂��Ă������A�\�A�R�N�U��A���V�A�l���Z���邽�߂̑b�ɂ��Ă��܂����炵���B��������́A�u���R�ی��v�ƂȂ��Ă���C�l���V���̊C�܂ŕ����čs���A�C�݂��U���B�C���͂�ő����Ƌu�Ɩ������Ȃ����̏ꏊ�ɁA�ߋ��ɓ��{�l���Z��ł����ƕ����āA�����������B�������V�тȂǂɋ�������A�ΌÒO���֖߂����B
�@�ߌ�4�����ɑ��ɒ����ƁA���x�͖��Ƃ̗���ɐ����E�Ǘ�����Ă���u�ΌÒO��n�v����сu�N�����l��n�v�ɕ�Q�����B�u���R�v�Ƃ܂ł͌����Ȃ����̂́A���Ԃň͂�ꂽ���n�̒��ɓ��{�l�̕�������_�݂��Ă���B�����ɋA�˂����N�����l�i�A�C�k�l�j�U���̕������ꂽ�B���̌�A�[�H��܂ł̎��Ԃ𗘗p���āA�e���A�ΌÒO���E���S���̎U��┃�����������B
�@��ʂ������Ă���ƁA�S���ō��ꂽ�ΐF�̃��j�������g�������B�ׂɂ���蕶�ɂ��A���ꂪ�u�q�C�҃V�p���x���O�̐F�O�����B250���N�v���L�O������̂ł��邱�Ƃ�������[13]�B���V�A�̍q�C�҂ł���V�p���x���O���ŏ��ɐF�O���������A����ă\�A�i���V�A�j�̗̗L�͗h���Ȃ����̂ł���A�Ǝ咣���Ă���̂ł��낤�B�������Ȃ���A�u�N���ŏ��ɔ����������v�Ƃ������Ƃ́A�̗L���咣�̍����Ƃ��ĕs�\���ł���B�W�F�m���@�o�g�̃X�y�C���̍q�C�҃R�����u�X���A�A�����J�嗤���ŏ��Ɂu�����v��������Ƃ����āA�X�y�C�����A�����J�̗L���咣�ł��邾�낤���B���邢�̓R�����u�X�̐��܂������C�^���A���̗L���咣�ł��邾�낤���B����A�C�^���A���咣����̂Ȃ�A�V�p���x���O�̏o�g�n�f���}�[�N���F�O���̗L�ɖ������グ�邱�Ƃ��\�ł��낤�\�\�B��k�͂��ꂭ�炢�ɂ���Ƃ��Ă��A�u�����v�i���B�j�̏��Ԃł����ė̗L�����咣����ɂ͖���������A����͊���I�ȁu�������v���咣���Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł���B���ɏ��Ԃ���Ƃ����Ƃ���ŁA�����������{�ł́A�V�p���x���O���F�O��������1720�N������y���O�A���łɁu���ی䍑�G�}(���傤�ق������ɂ���)�v�i1644�N�j[14]�̒��œ����̑��݂��m�F����Ă���B
�@���̃��j�������g�̑O�ŁA���N�̃��V�A�l������l�Əo������B�b���ƁA��l�̓n�o���t�X�N�B����̏o�҂��J���҂ŁA�V�N�܂ŃM�h���X�g���C�Ђ̐��Y�H�ꂪ���邱�̓��ɑ؍݂���Ƃ����B�܂��A�ߑO���ɑ��̋���Ő�����Ă����͔̂ޏ������ł������B�ꏏ�ɋL�O�B�e������A�u�ʐ^�𑗂邩��v�ƏZ�������������B�����x�����̐N�Ƃ��������������A�F�O���K�⒆�A�u�r�U�Ȃ��𗬁v�Ƃ��ė\�߃Z�b�g���ꂽ�o��ȊO�ɁA�����������R�̏o����������̂̓��b�L�[�������Ǝv���B
���V�A�l�Z���Ƃ̕ʂ�
�@���āA�ߌ�6���O�Ɏn�܂����u�[�H�𗬉�v�́A2���Ԃ̖K���ʂ��čŌ�̌����s���ƂȂ����B����Ɠ����ΌÒO���̃����g�����ɂāA�`���Ɍ������̃Z�f�B�t�����ƌ�p�ҖK��c�̊ۓc�c���̈��A����������A�e�ǁA�z�X�g�t�@�~���[�ƂƂ��Ƀe�[�u�����͂�Łu�Ō�̔ӎ`�v���y���B�����Ŏv�������ʁu�\�����v���҂��Ă����B�O���̗[�H��Ńg�����y�b�g�𐁂������ƁA��i���I��������c��w�̑�炳��ɁA�F�O�����́u�r�U�Ȃ��𗬁v�S���҂���F�O���̃|�X�g�J�[�h�E�Z�b�g���v���[���g���ꂽ�̂ł���B
�@�܂��A�[�H��ł́A�z�X�g�t�@�~���[�̃Z���Q�C�A�I���K�E�|�^�y���R�v�Ȃ���F�X�Șb�����Ƃ��ł����B�Z���Q�C���E���W�I�X�g�N�ŌR���ɏA���Ă������A�����H�Ȋw���ł������I���K����Əo��������ƁB������13�N�O�A�I���K����̕�𗊂��āA�F�O���ɓ�l�ł���Ă������ƁA�ȂǁB�܂��Z���Q�C���E�N���C�i�o�g�ƕ����āA���̓��̏Z�����u�������v�ō\������Ă��邱�Ƃ����߂Ď��������B����ڂƂ������ƂŁA�����ǂ̊w�����A���V�A���b����E�b���Ȃ��Ɋւ�炸�A�ϋɓI�Ƀ|�^�y���R�v�Ȃɘb�������Ă����̂���ۂɎc���Ă���B
�@�ߌ�V���A�[�H��I���ƁA�ΌÒO�̊C�̓I�����W�F�ɐ��܂�������B2���Ԃ̖K��̎v���o�����݂��߂Ȃ���A�������̎V���֖߂�B�V���߂��̊ݕǂɂ́A���łɑ����ȉ��A�u�r�U�Ȃ��𗬁v�S���҂�z�X�g�t�@�~���[�ق��A�F�O���Z����������ɂ���ė��Ă����B������ƒk�b���A�I���K����̕�e����̓`���R���[�g�̂��y�Y�Ղ����B�K��c�����Q�����ԉōŌ�̌𗬂̋@�������A��l���q�����A���V�A�l�����{�l���A�[�Ă��̒��ʼnԉɋ����Ȃ���ʂ��ɂ��B
�@�ߌ�8���i���{���ԁ��ߌ�6���j�A�u�R�[�����z���C�g�v���̃^���b�v�����A�b����g�����o���B�V���̏�Ŏ��U��Ȃ���A�ނ�͌��X�Ɂu�܂����Ă��������v�ƌ����Ă����B���͈ȑO�A�Z����w���C�ő؍݂������X�N������A������ۂɂ́u��x�Ɨ��邩�v�Ǝv�������̂����A�F�O���ɂ͖{�S����u�܂��������v�Ǝv�����B�o�`�̏����������ƁA�D�͏������V���𗣂�ē����o���B�o���Ƃ����U�葱���A�ނ�̎p�A�������̊ݕǂ��ǂ�ǂ����Ȃ��Ă������B�����ĐF�O���Z���́A�����Č֒��ł͂Ȃ��A�D����ނ�̎p�������Ȃ��Ȃ�܂ł����Ǝ��U���Ă��ꂽ�̂ł���B�K��c�ꓯ�́A�Ō�ɍb����F�O���������đ傫�Ȑ��ŋ��B�D�� ���r�y�t�p�~�y��!�i�܂�����܂ŁI�j
�A��̑D�̒���
�@�F�O���̓��e�������Ȃ��Ȃ������A�܂����邩�����C��͔����ɂɕ�܂ꂽ�B�D��ł͋�����߂��ʂ܂܂ɁA�c�����m�ō���̖K��̐������j���A���݂����z���q�������B��Ԋ������Ă����̂́u�M���j�v�A��B��̉����搶�ł������B���ɂƂ��Ă͏��߂Ă̎Q���ł͂��������A�k�������ǂ̕�����ȑO�̘b���đz������ɁA���̖K��́u100�_�ȏ�v�̓_����t��������̂ł������Ǝv���B
�@���V�A���ԂŌߑO0������������A�^���Èł̒��A�D�͍��㓇�̌Ê��z�p�ɓ����E�┑�����B�����ɂ͖k�C�����i�ψ���̍��㓇�K��c�ƍ�������B
�@�������o�`���Ďl���ڂ�7��26�����A�ߑO7���i���{���ԁ��ߑO5���j�N���͕ς��Ȃ��B���H���ς܂�����A�k�C���g����荞��ł���O�ɁA�F�O���K��c�݂̂ʼn�c�����s�����B30���ȏ�̒c�������ꂼ��A2���Ԃ̖K��̊��z���q�ׂĂ������B
�@���s�����������j�搶�́A�����u�w�����x�Ɓw���x�����߂Ėk���̓y�Ԋ҉^���̃L�[���[�h�ɂȂ����v�Ƃ������Ƃ�]�����Ă����B�K��c���̊ۓc������́A�o���O���̌��c���ł̌��ӕ\����U��Ԃ�A�u�i�l���𗬂ł́j�w�����A�s�����A�����A�A�����x�����łȂ��A���͂̐l�X�ɍ���̌o�����w�`����x�A�����ĖK��c���ōĂсw�W���x���Ƃ��d�v�v�Ƃ̎w�E���������B���̑��A��p�ҖK��c������́A�u�L�Ӌ`�������v�u�M�d�Ȍo�������L�ł����v�u�D�̏�ŁA�ꐶ�̗F�B���ł����C������v�Ȃǂ̊��z��A�u���̌�������āA�������̕K�v����������v�u����̖K��̓S�[���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�i�������ւ́j�X�^�[�g�ł���v�u�l���̏Z���Ɛڂ���̂͂��ꂪ�Ō�Ȃ̂ł͂Ȃ��B���ꂩ����ނ�Ƃ͉��x�ł����͂��A���̂��߂ɉ����ł��邩���l�������v�Ƃ������ӌ��������ꂽ�B
�@�ߑO10���߂��A���㓇�����x�D�������B���㓇���ǂ̎��������D�ɏ�荞�݁A�����ł����킹���s��ꂽ�B���炭���āu�o��葱���v���n�܂�A�k�C�����i�ψ���̖K��c�������X�Ɓu�R�[�����z���C�g�v���ɏ�D���Ă����B30��������ƁA���₩�ɂȂ����q�D�͍��������ďo�������B
�@���㓇�̖K��c���ɘb���ƁA�ޓ��͓��{�̐l���x���Ō��݂��ꂽ�u���{�l�ƃ��V�A�l�̗F�D�̉Ɓv��2�������Ƃ̂��ƁB���������łȂ��h���{�݂ł����V�A���̐H�����o����邽�߁A�����O���Ă��܂����������B���łɏq�ׂ��ʂ�A�F�O���ɂ͓K���ȏh���{�݂��Ȃ����߁A��X�͋����ȑD�����ƂȂ����̂����A�D���ŏo����钩�H���K�����{�H�ł���A���̖ʂł͋~��ꂽ�̂�������Ȃ��B���V�A���Ԍߌ�2���߂��A���Ȃ킿���{���ԂŐ��߉߂��A�u���ԓ_�v��ʉ߂���i�ȉ��A���{���ԁj�B�܂��Ȃ��D��ł́A�k���Ɩk�C�����i�ψ���ō�����c�����s��ꂽ�B
�@�C��̓V�C�͉��₩�ŁA�b����͌��n������̐��������L�����Ă���B�N���̊������ĊC�ɖڂ��������B�����2�A3���̃C���J���A�D�Ƌ����ł����邩�̂悤�ɁA�����߂����j���ł����ł͂Ȃ����B�܂��A�����ł͎��܁A�N�W�����������ƊC�ʂɎp���ׂĂ���B�z�G�[���E�E�H�b�`���O�́u��m�v�Ƃ����C���[�W���������̂ŁA�k�̊C�ɂ���قNJC�b������̂�ڂ̓�����ɂ��ċ������B
�@�C��ł�������������̂������B���{�ł͖k�m�݂̂ɐ������钿���E�G�g�s���J[15]�ł���B�C�ʂ��H�Ńo�V���o�V���Ƒł����Ȃ�����ł����̂����āA�ŏ��́A�u�y���M�����M��Ă���̂��H�v�Ǝv�����قǂł���B��u�̏o�����ł������̂Ŏʐ^���B�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A���ƂŒ��ׂĂ݂�ƁA����1�H�͊ԈႢ�Ȃ��G�g�s���J�ł������B
�@�ߌ�1�����A�����ɖ������`�B�k���l������̓y�Y���ł��A�A���E��q�ނ͖h�u��̖��Ŏ��R�Ɏ������߂��A���E�^�o�R���������ݗʂ���������Ă��邽�߁A���D�O�ɒʊ֎m����`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���炩���ߋL�����Ă������\�����Ɋ�Â��āA�m�F��Ƃ��s��ꂽ�B���D�����������ƁA3���O�ɏo�`�������Ɠ����A�����̊C��ۈ����O�ݕǂɉ��藧�����B�u�R�[�����z���C�g�v���̑O�ŏW���ʐ^���B������A�o�X�ɏ���č����O�����h�z�e�����ׂ́u�瓇��فv�Ɉړ����A�ߌ�2���߂��ɉ��U�B����Ŗk���l���𗬁E��p�ҁi�F�O���j�K�⎖�Ƃ̑S�v���O�������I�������B�F�O���㗤2���ԁA�D������4���ԁA�����ł̎��O���C���܂߂��5���Ԃ̍s���ł������B
�@�ߌ�3��������̑�\�ҋL�҉���ς�ł���A�z�e���̋q���ł����x�����Ƃ�B�邩��́A��������K��c���̍s���t���ƂȂ����s���̋������u���v�ŁA����̖K�⎖�Ƃ̒��߂�����ƂȂ�u�j�t�v���������B�����l�ł����I

�u�R�[�����z���C�g�v���O�ɂāA�c���ꓯ�@2004.7.26
�k���̓y���ɂ��Ďv������
�@����̌�p�ҖK��ւ̎Q���́A�k���̓y���ɂ��āA���܂łɂȂ��[���l���������邫�������ƂȂ����B�o���O�̎��O�����A�u�Θb�W��v�̃X�s�[�`���e�̍쐬�A�D��ł̖K��c���Ԃ̈ӌ������A�����Ď��ۂ̐F�O���K��\�\�����̑��ł͓����Ȃ��M�d�Ȍo���i���Ȃ킿�u�S���v�Ɓu�ꌩ�v�j��ʂ��āA�����̒��ɖ{���I�Ȗ��ӎ����萶�����悤�ȋC������B
�@���āA�̓y���ɂ��Ă̔F����[�߂Ă������ŁA���{���k���̓y�Ԋҗv���ɂ����Ăǂ̂悤�Ș_�����f���Ă���̂���m�邱�Ƃ��ł������A����������͓����ɁA���{���̕Ԋҗv���̍����̈ꕔ�������ɓm��ŕn�ォ��ڂ̓�����ɂ��錋�ʂɂ��Ȃ����B�\�A���̖��_�����邱�ƂȂ���A���{���̖��_�������яオ���Ă����̂ł���B
�@�̓y���́A�����߂̖��ł�������A���ɂ�����Č��肪�Ȃ���鐭�����ł������肷��B���l���Ԋҗv���^���Ɍg���͎̂��R�ł���B�������A�������A�����ȑԓx�ŋ���ǂ���ɂł���̂͏��i����т���ɏ�����錾�����j�݂̂ł���B�����錾�ɖ��L����Ă���悤�ɁA���̗̓y���́u�@�Ɛ��`�̌����v����b�Ƃ��ĉ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���́u�@�I�ȁv�_���̈��́A����x�ᖡ��������đR��ׂ��ł͂Ȃ����낤���B
�@�ȉ��A�����l������{���̎咣�̖��_���������B�܂��͓��{���{�̖k���̓y�Ԋҗv���̘_�����܂��ɂ����炢���Ă������B
�@1855�N�̓��D�ʍD�������ȍ~�A�k���l���͈�т��ē��{�̗̓y�ł������B
�A�\�A�͓��\�������i1941�N�j��1945�N4���ɔj���������A1946�N4���̎���������҂����Ɂi���ۖ@�Ɉᔽ���āj�Γ����z�����Ă����i�������|�c�_���錾�����Ɂj�B
�B�u�̓y�s�g��̌����v��搂����吼�m���́i1941�N�j����сu�J�C���錾�v�i1943�N�j�Ƀ\�A���Q�����Ă���B�܂��A�J�C���錾�ŘA�����ɂ����{���쒀����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����u�\�͂�����×~�ɂ����{�������悵���n��v�ɂ́A���{�ŗL�̗̓y�ł���k���l���͊܂܂�Ȃ��B
�C�k���l���̓T���E�t�����V�X�R���a���i1951�N�j�œ��{�����������瓇�ɂ͊܂܂�Ȃ��B
�@�����̎咣�͂����Ƃ��Ȃ��̂ł���B�������A����͍������͂����肵�Ă��āA�������肪�Ȃ��Ƃ����O������������Ă̂��̂��B���́A�����g�͇B�ƇC�̘_���ɂ��ċ^�O������Ă���B
�@��ɁA�C�́u�k���l���̓T���E�t�����V�X�R���a���œ��{�����������瓇�Ɋ܂܂�Ȃ��v�Ƃ������Ƃɂ��āB���m�̒ʂ�A���{���{�͐瓇�i�N���������j�͈̔͂��A�J���`���g�J�����̓�̃V�����V��������E���b�v���܂ł�18���ƒ�`���Ă���B�u������k���l���͕������Ă��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��낤���A���̒�`�̍����ɏd��ȁu���ׁv�����邱�Ƃ��A��r����w�҂̑��R���Y�͂��̘_�l�̒��Ŏw�E���Ă���[16]�B
�@���{���{�������ŋ���ǂ���ɂ��Ă���̂́A���D�ʍD���i1855�N�j�����Ɗ����瓇�������i1875�N�j��ł���i�ȉ��A�����M�Ғ��j�B
�E�u���g���v�v�S���͓��{�ɑ����u�E���b�v�v�S���v���k�̕��u�N�����v�����͘D�����ɑ����i���D�ʍD�������j
�E�u�N�����v�Q�����`���u�V�����V���v���q�c�c�r��\���u�E���b�v�v�����v�\�����m�����y�r�N��j���X����m����������{�鍑�É��j�������������u�N�����v�S���n���{�鍑�j���V�q�c�c�r�i�����瓇��������j
�@���{�����������ł́A��L�̓�̏Ɉ�ؖ��͂Ȃ��悤�Ɏv����B�������A���R�ɂ��A���D�ʍD���́u�����v�̓I�����_��A�����瓇�������̐����̓t�����X��ŏ�����Ă���A��������|�ē��{�����쐬����ɂ������āu���v�������Ă���̂��Ƃ����B
�@���D�ʍD���̓��{���́A�������̂悤�Ɂu�w�E���b�v�x�S���v���k�̕��w�N�����x�����v�i�E���b�v�S��������Ȗk���N���������j�ƂȂ��Ă���B�������A���{���쐬�̂��߃I�����_�ꂩ��ŏ��ɖꂽ�Ƃ��ɂ́A�����ɊT�˒����Ɂu�E���[�v�S���y�����̖k�ɍ݂�N���������v�i�E���b�v�S����������̑��̖k���ɂ����N���������j�ƂȂ��Ă����B���ꂪ�]�ʂ����ہA�u�����̖k�ɍ݂�v���u���n�̖k�ɍ݂�v�ƌ�L����Ă��܂��A���̂܂ܓ��{�����������Ă��܂����̂ł���B
�@�܂��A�����瓇�������̓��{���ł́A�V�����V��������E���b�v���܂ł�18�����u�w�N�����x�Q���v����сu�w�N�����x�S���v�ƌĂ�Ă��邪�A����ɊY�����錾�t���t�����X��́u�����v����u�N�����Q���̃O���[�v�v�ɂȂ�Ƃ����B���Ȃ킿�A�E���b�v���Ȗk��18���́A�N���������̒��́u��O���[�v�v�ɉ߂��Ȃ��̂ł���B
�@�ȏ���A�瓇�i�N���������j�̓E���b�v���Ȗk��18���Ɍ��肳�꓾�Ȃ��A�Ƃ���̂����R�̌��_�ł���B�Ȃ��A���V�A���́A��̏��Ƃ��A�T�ˁu�����v�i�I�����_���A�t�����X���j�ɉ��������e�ɂȂ��Ă���Ƃ����B���͊w�p�I�Ȍ��n���瑺�R�̘_�l���x�����Ă���B
�@�u�ǂ����Ă����R�_���ɔ[���ł��Ȃ��v�Ƃ������̂��߂ɁA�O�̂��ߕ⑫�������Ă��������B�����u�k���l���͐瓇�Ɋ܂܂��v�ƍl���������̍����́A�ӊO�ɂ��A���{�����u�𑨓��܂ł͓��{�ŗL�̗̓y�v�Ǝ咣����ۂɂ悭���������ɏo���u�j�R���C�ꐢ�̃v�`���[�`������P�߁v�i1853�N�j[17]�̕��ʂ̒��ɂ���B�Y�����镔���̃��V�A�ꌴ���Ƃ��̘a����A�ȉ��A���p���Ă݂悤�B
�@�c�c �y �r�����q���u ���u�z �����������r �����y���p�u������ �s���p�~�y���u�� �~�p���y��
�r�|�p�t�u�~�y�z �r �K�����y�|�����{�y�� �����������r�p��.[18]�i��ʂɂ��̓��m�E���b�v���\�\�M�Ғ��n�̓N���������ɂ������X�̗̓y�̋��Ƃ݂Ȃ���Ă���q�c�c�r�j[19]
�@���̕����ǂ�����ŁA�u�k���l���͐瓇�Ɋ܂܂�Ȃ��v�Ǝ咣���Ă�����X�Ɏ��₵�����B�E���b�v������V�����V�����܂ł�18����瓇�i�N���������j�Ƃ���̂Ȃ�A�ǂ����ăE���b�v�����u�N���������ɂ������X�́m���V�A�́n�̓y�̋��v�ƂȂ蓾��̂��낤���B�N���������͈̔͂��𑨓��ȓ�A���Ȃ킿�k���l���ɂ܂ŋy��ł��邩�炱���A���V�A���̃E���b�v���i����ѓ��{���̑𑨓��j�́u�N���������ɂ�����v�u�̓y�̋��v�Ƃ݂Ȃ���Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@���荑�̌������́A�����ɂƂ��āu�s���̗ǂ������v���������������ɏo���A�u�s���̈��������v�ɂ͖ڂ��Ԃ�̂Ȃ�A����Ȏp���́u�@�Ɛ��`�v����͒������ƌ��킴��Ȃ��B�u�@�Ɛ��`�̌����v�d���邩�炱���A�u�k���l���͐瓇�Ɋ܂܂��v�̂ł���B���Ɂu���N�����v�i�����Q���A�F�O���j��瓇���珜�O�ł����Ƃ��Ă��A����E�𑨗����͐��^�����̐瓇�̈ꕔ�ł��낤[20]�B
�@���ɁA�B�̎咣�Ƃ��̘_���ɂ��āB���͂��̘_���ɂ͑S���̐�����������ƍl���Ă���̂����A�����A�����Ɂu�_���ɑ��Ă��̎咣�Ƀu��������v�u�_���I�Ɉ�ѐ����Ă��Ȃ��v�Ƃ������Ă���B
�@�T���E�t�����V�X�R���a���œ��{���瓇����ѓ슒������������Ƃ����Ă��A�u�̓y�s�g��̌����v����\�A�i���V�A�j�ɓ��n����L���鐳�����͂Ȃ��B����Đ瓇���슒�����A�����m��́u���Ԃ���v�̏�Ԃɂ���A�Ƃ����̂����{���{�̗���ł���B���{�̒n�}�����J���A���ł���k�T�n�����Ԃ̖k��50�x���A�J���`���g�J��[�ƃV�����V�����̊Ԃɐ��ݓI�ȁu�������v��������Ă���B�܂��A�J�C���錾�ɂ���u�\�͂�����×~�ɂ����{�������悵���n��v���A1914�N�̑�ꎟ���E���J�n�Ȍ�Ɍ��肳��Ă���A�|�[�c�}�X�u�a���i1905�N�j�����ɂ���ē��{���l�������슒���͓��n��ɊY�����Ȃ��B���{���A���R�ɋ쒀����闝�R���Ȃ������̂ł���B
�@�Ƃ��낪�A���{�͓슒���i��T�n�����j�̃��V�A�̗L���u�ǔF�v���Ă��܂����B1997�N�A���{���{�́A�T�n�����B�̏B�s���W�m�T�n�����X�N�ɏ풓�̏o�����݊����������J�݂��錈��������̂ł���B�O���Ȃ́u�]���̗���ɕς��͂Ȃ��v�Ƃ������A���V�A�̎{�����ɂ����钓�݊��������ł��邱�Ƃ͖��炩������[21]�B
�@���{���{�́A�u�\�͂�����×~�ɂ����{�������悵���n��v�ɖk���l���͊Y�����Ȃ��Ǝ咣���Ă���B�����A�Ȃ��k���l�������Ȃ̂��B�u�J�C���錾�v�����������ɏo���̂ł���A�u�S�Ă̐瓇�A���Ȃ킿�J���`���g�J������̃V�����V�����܂ŗ̗L�ł���v�Ǝ咣���Ȃ��ƁA�_���Ɉ�ѐ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B���łɓ��{���{�����݊���������u������T�n�����͂Ƃ������Ƃ��Ă��A�E���b�v���Ȗk��18���́A�����瓇�������ɂ���ĕ��a���ɓ��{�ɕғ����ꂽ���̂ł���A�u�\�͂�����×~�ɂ����{�������悵���n��v�ɓ�����Ȃ��B�Ȃ��u�T���߂Ɂv�A�E���b�v���Ƒ𑨓��̊ԂɎ���u���E���v�������Ă��܂��̂��낤�B�K��c���̊ۓc���ɂ��̂悤�ɐ��������Ƃ���A���́u�E���b�v���̓��{�l�������͋����Q���肵�Ă���̂�������Ȃ��v�ƌ������B�k���̓y�Ԋ҂��������Ă��Ȃ��Ƃ͂����A�l���̌������́u�Ԋҗv���^���v�Ƃ������{�E��������̃o�b�N�A�b�v���Ă���̂ł���B�������E���b�v���̌������������Ɖ��肵�čl���Ă������������\�\�E���b�v���Ƒ𑨓��̋��E���͈�̉��Ȃ̂��H�@�����炭���{�́A�u�k���l���͓��{�ŗL�̗̓y������v�ƌJ��Ԃ�������Ɏ~�܂邾�낤�B
���_����݂��u�瓇���v
�@��q�̂悤�Ȃ��Ƃ���A���͖k���l�������łȂ��A������܂ސ瓇�̋A�������m��A���Ȃ킿�u�v�ɂȂ��Ă���ƍl���Ă���B���łɏq�ׂ��悤�ɁA��T�n�����̃��V�A��L�́u�ÂɁv���I�����{�̔F�߂�Ƃ���ƂȂ����̂ŁA�����Ŗ��ƂȂ�͍̂����������̎����Q������J���`���g�J������[�̃V�����V�����܂ł̈�A�̓��X�i�瓇���N���������j�ł���B�u�v�Ƃ́A�瓇�ɓ��{�̗̗L�������V�A�̗̗L�����y�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B����́A�u���{���̗L���咣�ł��Ȃ����R�v�Ɓu���V�A���̗L���咣�ł��Ȃ����R�v�̗�����������ΐ��������B
�@�܂��A�u���{���̗L���咣�ł��Ȃ����R�v�����Ă݂悤�B�J��Ԃ��ɂȂ邪�A���{��1951�N�̃T���E�t�����V�X�R���a���ŁA�瓇����ѓ슒����������Ă���B�����߂��炵�āA���́u�瓇�v�ɖk���l�����܂܂�Ă��邱�Ƃ͐�ɏq�ׂ��B�u���{���i�瓇�j�̗L���咣�ł��Ȃ����R�v�́A�c�O�Ȃ��炱�ꂾ���ŏ\���ł���[22]�B
�@���ɁA�u���V�A���̗L���咣�ł��Ȃ����R�v�ɂ��āB�V�����V�����ȓ�̐瓇�ւ̃\�A�̌R���N�U�́A�����������ۖ@�ᔽ�i���\��������O�̑Γ��Q��A���������{�̍~����j�ł������B����ɘA�����́u�̓y�s�g��̌����v�ɂ��\�A�̎����̓y�ւ̐瓇�ғ��͖����ł���A�瓇�̓J�C���錾�ɂ���u�\�͂�����×~�ɂ����{�������悵���n��v�ɂ��Y�����Ȃ��B
�@�ȏ���A���V�A�̓V�����V�����ȓ�̗̗L���咣�ł��Ȃ����A���{���܂������Q���Ȗk�̗̗L���咣�ł��Ȃ��B����Đ瓇�́u�n��v�Ȃ̂ł���B
�@�������A�����炱���A���͂����œ��D�ʍD���ɒ��ڂ������B�u���S�ɋA��v�Ƃ����Ӗ��ł́A���D�ʍD���ւ́u�������v�ł���B���ʓI�ɂ͖k���l���܂ł̐��ݓI�匠�̉�v������̂����A�����𑨓��ƃE���b�v���̊Ԃ����E�Ƃ���̂́A�u�k���l���̓T���E�t�����V�X�R���a���œ��{�����������瓇�Ɋ܂܂�Ȃ��v�Ƃ������قɂ��̂ł͂Ȃ��A���D�ʍD���ł́u�ŏ��̍������v�d���邩��ł���B�F�O���ł́u�Θb�W��v�ɂ����āA�����u���I�����̍������������ȏ�Ԃɒu����Ă��錻�݁A���D�ʍD���́A��X���Ăї����Ԃ�ׂ����ƌ�����̂ł͂Ȃ����v�ƃX�s�[�`�������R�͂����ɂ���B
�@����A�u�r�U�Ȃ��𗬁v���ƂɁu�Ԋҗv���^���W�ҁv�̘g�ŎQ�������Ƃ͂����A��l�Ƃ��Ă̎��̌����́A���{���{��W���c�̂̂���Ƃ͕K��������v���Ȃ��Ƃ������Ƃ������ł��f�肵�Ă����B���́A�k���̓y�ԊҎ��̂ɂ͊T�ˎ^���Ȃ̂����A���̕Ԋҗv���̓y��ƂȂ�ׂ��_�����u�ʐ����v�̏�Ԃ̂܂܂ł��邱�Ƃɂ͒f�Ŕ��ł���B�����̍������������Ȏ咣�����Ă��ẮA���܂�ɔ߂������炾�B
�@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�k���̓y���́u�@�Ɛ��`�̌����v����b�Ƃ��ĉ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ��A���I�����́u�@�I�ȁv�_���̈����A�����������~�܂��čĊm�F����K�v������悤�Ɏv���B���ꂪ���łȂ��̂ƂȂ�Ȃ�����A�����đO�i�͖]�߂Ȃ��̂ł���B

���D�ʍD�������̒n�A���c�E���y���@2004.8.25
���D�ʍD���150���N�\�\�ނ��тɂ�����
�@2005�N2��7���A���D�ʍD����������150���N�̐ߖڂ��}����B
�@����ɐ旧��2004�N9��2���A����͊C�ۂ̏������ɏ��A�k���̓y�i���㓇�A�����Q���j�����@�����B�����炭�ƍ����ō��k������������́A�u������b���������Ɉӗ~�������Ă���v�Ƃ��Ċ��}�����̂��낤�B�����A���̈���ŁA���V�A�O���Ȃ́A�u���a�����G�������邾���v�Ƒ�������s�������������B�����ł͒P�Ȃ�u�����I�A�s�[���v�ł͂Ȃ����Ƃ̌������������B�ʂ����āA���̏���̗m�㎋�@�ɁA�Ȗ��ȊO��헪�͂������̂��낤���B
�@�Ƃ�����A2005�N�̃v�[�`���哝�̖K�������āA�������i�߂��Ă���悤�ł���B���A��X�ɂł���̂́A��]��k�̐��ʂɉߓx�Ɋ��҂��邱�ƂȂ��A��Âɔ��f���A���V�A���̔����������Ȃ����Ƃł͂Ȃ����낤���B���̈�N�͓��D�ʍD����łȂ��A�����瓇�������i1875�N�j130���N�A�|�[�c�}�X�u�a���i1905�N�j100���N�A�\�A�Γ��Q��i1945�N�j60���N�Ƃ����ߖڂł�����B���I�W�����߂ĐU��Ԃ�L�v�ȔN�ɂȂ邱�Ɗ��҂��Ă�܂Ȃ��B
�@����̐F�O���K��́A���ɂƂ��āA�k���̓y���ɑ��ď��߂āu�^���ʂ�����������v���������ƂȂ����B���ӎ���������������̖K��c���Ƃ̏o����������B�����̋M�d�Ȍo�������A����������̃��C�t���[�N�Ƃ��ē��I�W�̉ߋ��E���݁E�����𒍎����A���I�����̐���ȊW�Ƃ������̂�͍����Ă��������Ǝv���B
�@�Ō�ɂȂ������A�k���l���𗬁E��p�ҖK��ւ̎Q���ɍۂ��A�ɂ��݂Ȃ����͂⏕���������������e���ʂ̊F�l�ɁA�S��肨���\���グ�����B
�i2004�N10���L�j
��
[1]���t�{�k�����{���E�F�u�T�C�ghttp://www8.cao.go.jp/hoppo/shisaku/shisaku4.html�Q�ƁB
[2]�O��p�j�u���I�E���\�W�̓����v�i���V�A�j������ҁw���I��Z�Z�N�\�\�����V�A�Ƃ̌𗬎j�x�ʗ��ЁA1993�N�A10�\11�Łj�B�A�_���E���N�X�}�����单�������v��A��č����ɗ��q����14�N�O��1778�N�A�C���N�[�c�N�̖є珤�l�h�~�g���[�E�V���o������s�́A���݂ɂď��O�˂̖�l�ƐڐG�����B
[3]�����s�����ɏ��݂���i���������E�F�u�T�C�ghttp://www.marimo.or.jp/~habomai/�j�B
[4]�u�k���l���̂��܁v�k���̓y����A5�ŁB
[5]�u�������̏v�i�w����̖k���̓y�E2003�N�x�Łx�O���ȍ����L��ہA������9�Łj�B���a20�N8��15�����_�ł̐l���B
[6]�u�����ʐM�j���[�X�v�i2004�N9��7���t�j�B�u���������ɖ��Ԃ̉Ɖ��@���R�K��c�����߂Ċm�F�v�u�E��������2�J���ŁA�ؑ��̐l�Ƃƍ�Ə��Ƃ݂��錚���v4���v�u�G�r���̂��߂̏����Ɖ��H��Ə��̉\��������v�ƕ�ꂽ�B
[7]�u�k���l���̂��܁v�k���̓y����A25�ŁB
[8]1999�N3���A�k���̓y���A��茤����ɂ��u�k���l�����A�ɔ��������\�\��Ƃ��ĘI�n�Z���̏����ɂ��āv�Ƃ������|�[�g���쐬����Ă���B���{���{�̊�{���j���A���̃��|�[�g�̓��e�ƊT�ˈ�v���Ă���B�����Ŏ��́u�����v�Ƃ����L�[���[�h��p�����B
[9]�����a�Y�E��ؖ��`�w���E���I�̓y���\�\����̖͍��x��g���X�A2003�N�A40�ŁB
[10]�u�菇�v�m�ɂ��Ă���Ƃ���铯�錾�́u���̖����q�c�c�r�������邱���ɂ�����a���𑁊��ɒ�������悤�����p�����v�Ƃ��������́A���V�A���ł��s�������t���|�w�p���� ���u���u�s���r������ �� ���u�|���� ���{�����u�z���u�s�� �x�p�{�|�����u�~�y�� �}�y���~���s�� �t���s���r�����p �������u�}
���u���u�~�y�� ���{�p�x�p�~�~���s�� �r�����������p�t�i�����M�Ғ��j�ƂȂ��Ă���B�������u�}�i�������������j�Ƃ������t�Łu�������v�͎�����Ă�����̂́A�u�菇�v��O��W�܂ł͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��i�w���I�ԗ̓y���̗��j�Ɋւ��鋤���쐬�����W�E�V�Łx���{���O���ȁE���V�A�A�M�O���ȁA2�ŁB�N���r���u �y�x�t�p�~�y�u
�����r�}�u�����~���z ���q�����~�y�{ �t���{���}�u�~�����r ���� �y���������y�y ���u�����y�������y�p�|���~���s�� ���p�x�}�u�w�u�r�p�~�y�� �}�u�w�t��
�Q�������y�u�z �y �`�����~�y�u�z, �M�I�D �Q�������y�z���{���z �U�u�t�u���p���y�y, �M�I�D �`�����~�y�y, ������.8.�j�B
[11]�������猵���Ɍ����u���̖��v�́A�u�̓y���v�ł͂Ȃ��u���a�����v���w���Ă���B
[12]2000�N12�����{�A�k�C���V�����W�m�T�n�����X�N�x�ǂ����㓇�A�𑨓��̐V���ЂƋ��͂��Ď��{�����Z���A���P�[�g�i�F�O�E����E�𑨎O�����e100���𒊏o�j�ɂ��A�u���\�����錾�Ɋ�Â��F�O�A���������̓��{�ւ̈����n���v�ɂ��āA�F�O���ł�46�����^���A37�������Ɠ����Ă���i������N�w�������a���ւ̓��\�\�s���v��E�T�n�����J����ʂ��āx���[���V�A�E�u�b�N���b�g��48�^���m���X�A2003�N�j�B
[13]�蕶�ɂ́A�s�B �P�@�M�`�S�] 250 �L�E�S�I�` �O�S�K�Q�\�S�I�`
�O�R�S�Q�O�B�@ �Y�I�K�O�S�@�N�@ �^�K�R�P�E�D�I�W�I�E�J �M. �Y�I�P�@�N�A�E�Q�C�@�t�i�G���E�V�p���x���O�T�����ɂ��V�R�^��������250���N���L�O���āj�Ƃ���B
[14]1644�N�A���얋�{�����O�˂����o���ꂽ�̒n�}����ɍ쐬���������n�}�i�w���I�ԗ̓y���̗��j�Ɋւ��鋤���쐬�����W�x���{���O���ȁA���V�A�A�M�O���ȁA1992�N�A1�Łj�B
[15]�u�Ō�̊y���v�i�k�C�������E�F�u�T�C�g�jhttp://www.hbc.jp/archive/paradise/�Q�ƁB
[16]���R���Y�u���I�ʍD���i�ꔪ�܌ܔN�j�Ɗ����瓇�������i�ꔪ���ܔN�j�\�\�N���������i�瓇�j�̉������v�i���V�A�j������ҁw���I��Z�Z�N�\�\�����V�A�Ƃ̌𗬎j�x�ʗ��ЁA1993�N�A37�\52�Łj�B
[17]���D�ʍD�����������Ă̌��ɐ旧���A�S����\�v�`���[�`������ɏo���ꂽ�P�߁B�u�N���������̓��A���V�A�ɑ�����œ�[�̓E���b�v���ł���A���������V�A�̂̓���ɂ�����I�_�Əq�ׂč\��Ȃ��B����ɂ��i�������Ɏ����セ���ł���悤�Ɂj�䂪���͓����̓�[�����{�Ƃ̍����ƂȂ�A���{���͑𑨓��̖k�[�������ƂȂ�v�Ƃ���A�k���l�����u���{�ŗL�̗̓y�v�Ƃ��鍪���̈�ƂȂ��Ă���i�w���I�ԗ̓y���̗��j�Ɋւ��鋤���쐬�����W�x���{���O���ȁE���V�A�A�M�O���ȁA1992�N�A6�Łj�B
[18]�R���r�}�u�����~���z ���q�����~�y�{ �t���{���}�u�~�����r ���� �y���������y�y ���u�����y�������y�p�|���~���s�� ���p�x�}�u�w�u�r�p�~�y��
�}�u�w�t�� �Q�������y�u�z �y �`�����~�y�u�z, �M�I�D �Q�������y�z���{���z �U�u�t�u���p���y�y, �M�I�D �`�����~�y�y, 1992, ������.8.
[19] �w���I�ԗ̓y���̗��j�Ɋւ��鋤���쐬�����W�x���{���O���ȁE���V�A�A�M�O���ȁA1992�N�A6�ŁB
[20]�k�C����搧��̃p���t���b�g�u�k���̓y�K�C�h�v�i�k���̓y����A2004�N�j�ɂ́A�u���̃p���t���b�g�ł͈ȉ��A���㓇�A�𑨓��y�уE���b�v������k�̃p�����V�����A�V�����V�����܂ł̓��X���w�瓇�x�ƌĂт܂��v�Ƃ������L��A�u�q�c�c�r9��5���܂łɐ瓇�̓��X�Ǝ��������A�F�O���͂��ׂă\�A�ɐ苒����܂����v�Ƃ̋L�q������A�u��N�����i���瓇�j�v�Ɓu���N�����v���Âɋ�ʂ��Ă���B
[21]�����a�Y�E��ؖ��`�w���E���I�̓y���\�\����̖͍��x��g���X�A2003�N�A62�\63�ŁB
[22]�u�\�A�̓T���E�t�����V�X�R���a���ɏ������Ă��Ȃ�����A���{�̐瓇�E�슒�������́i�\�A�ɑ��Ắj�����v�ƌ�����������邪�A���Ȃ��Ƃ��A����ȊO�̓������ɑ��ē��{�����n��̕�����錾���Ă��邱�Ƃ͊m���ł���B
�^�K�R�P�O-2005:
�Q�O�R�R�I�J�R�K�O�E �B�I�D�E�N�I�E �M�T�D�Q�O�R�S�I �P�Q�I�Q�O�D�\
�M�y���p�z�|���r�p �R�r�u���|�p�~�p
�@
45% - �}�y�����r���� �x�p���p�����r �����y�����t�~���s�� �s�p�x�p�@13% - �~�u�����y
23% - ���s�|�� 14% - �����p�~�p
�O�����q�u�~�~�������� �����y�����t�~��-���u���������~���s�� �������u�~���y�p�|�p �Q�������y�y
– �u�s�� �{�������~���}�p�������p�q�~�������� �y �{���}���|�u�{���~��������.
�@�@�M�u�w�t���~�p�����t�~���u �B�������p�r�{�y �~�p�x���r�p���� �O�|�y�}���y�p�t�p�}�y �������s���r�|�y.
�N�p�����������p�� �B�������p�r�{�p 2005 �s. ���r�|���u������ �r �`�����~�y�y ���u���r�u�������z ���� �����u����. �B�� �r���u��
�����u�t���t�����y�� �r�������p�r�{�p�� �r���u�s�t�p �����y�~�y�}�p�| �����p�����y�u �R���r�u�����{�y�z �R�����x, �~�� ���u���u���� �����u�t�y
120 �������p�~, �����q�u�������y������ �����t �������~���{�y�z �x���~���y�{, �q���t�u��
�����u�t�����p�r�|�u�~�p �~�u �����|���{�� �Q�������y��, �~�� �y �t�����s�y�u ���������{�����x�����~���u �������p�~��: �T�{���p�y�~�p,
�C�����x�y��, �@���}�u�~�y��. �@�x�u���q�p�z�t�w�p�~, �L�y���r�p. �S�p�t�w�y�{�y�����p�~, �T�x�q�u�{�y�����p�~, �K�p�x�p�������p�~,
�K�y���s�y�x�y��. �S�p�{�y�} ���q���p�x���} �~�p ���u���r���z �}�u�w�t���~�p�����t�~���z �B�������p�r�{�u �V�VI �r. �q���t�u�� �����u�t�����p�r�|�u�~��
�~���r���u �}�u�w�t���~�p�����t�~���u �������q���u�����r�� �y �u�s�� �r�x�s�|���t �~�p �����~�y�}�p�~�y�u ���p�x�r�y���y�� ���|�p�~�u����.
�Q�������{�y�z �P�p�r�y�|�����~ �~�p �}�u�w�t���~�p�����t�~���z
�B�������p�r�{�u �^�K�R�P�O-2005 ���p�������|���w�u�~ �����y�}�u���~�� �r 15 �}�y�~�����p�� �����t���q�� ���� �H�p���p�t�~���s�� �r�����t�p,
�~�p ���{���p�y�~�u. �K�p�{ �y �{�p�w�t�p�� �t�����s�p�� �������p�~�p �����p�����~�y���p �Q�������y�� �r���t�r�y�~���|�p ���r���u �r�y�t�u�~�y�u
���q���u�z ���u�}�� - «�M���t���������� �P���y�����t��» �x�p���r�y�r �u�s�� �{�p�{ – �C�p���}���~�y�� �N���������u����.
�R���u�t�y �������u�t�u�|�u�~�y�z «�~���������u����» �u������
�y ���p�{���u �{�p�{ «�N���������u���p – �~���r�p�� �y�~�������}�p���y���~�~��-���~�u���s�u���y���u���{�p�� ���q���|�����{�p �H�u�}�|�y». �N���������u���p ("�~������"
- ����-�s���u���u���{�y ���x�~�p���p�u�� ���p�x���}, �t����.) - �~���r���u ���}�����y���~�p�|���~���u �������������~�y�u �q�y�������u����,
�����y �{�����������} ���p�x���}�~�p�� �t�u�����u�|���~�������� ���u�|���r�u�{�p �����p�~���r�y������ ���u���p�����y�} ���p�{���������} �u�u
���p�x�r�y���y��. �D�|�� �~���������u���� ���p���p�{���u���~�� �r�x�p�y�}���t�u�z�����r�y�u ���u�|���r�u�{�p �y �����y�����t��: ���r���x��
�x�p�{���~���r �����y�����t�� �� �x�p�{���~�p�}�y �}�����|�u�~�y�� �y �������y�p�|���~��-���{���~���}�y���u���{�y�}�y �x�p�{���~�p�}�y.
�Q�������y�z�{���u �r�y�t�u�~�y�u ���{�����w�p�����u�z �����u�t�� �p�{�{���}���|�y�����u�� �r ���u�q�u
���u���~���{���p���y���u���{�y�z �������� �H�p���p�t�p �y �������u�����r�u�~�~���u �����{�������y�� �r ���q�|�p�����y �t�����p �B���������{�p.
�Q�p�x���p�q�����{�p �������q�|�u�}�� �N���������u���� �����y�~�p�t�|�u�w�y�� ���������{���}�� �����u�~���}�� �B.�I.�B�u���~�p�t���{���}��
(1863- 1945). �B ���r���y�� �|�u�{���y���� �������t�u�~���p�} �R�����q���~�~�� �r
1924-1932 �s�s ���~ �s���r�����y�| �� ���r���x�y �����s�p�~�y�x�}�p ��
���{�����w�p�����u�z �����u�t���z �q�y���s�u�~�~���} �����{���} �p�����}���r �y �� ���r�|�u�~�y�y "�r�����t�~�������y"
�w�y�x�~�y.
�B�u���~�p�t���{�y�z �����t���u���{�y�r�p�|, ������ �N���������u���p
�u������ ���r���u�s�� �����t�p ���r�|�u�~�y�u �s�u���|���s�y���u���{���u, ���p�{ �{�p�{ �~�p�����~�p�� �}�����|�� ���u�|���r�u���u�����r�p
���p�q�����p�u�� �����|���{�� �r �q�y�������u���u �y �r �����t�u ���r���u�s�� ���������r�|�u�~�y�� �r �{���~���u �{���~�����r �����u�r���p���p�u��
�u�u �r �~���������u����, �s�u���|���s�y���u���{�y �����r�p�����r�p�� �u�u ���p�x���}���}.
�S�p�{�y�} ���q���p�x���}, �r �����~�y�}�p�~�y�y �B�u���~�p�t���{���s��,���u�|���r�u�{
�����p�~���r�y������ �{�������~�u�z���u�z �s�u���|���s�y���u���{���z ���y�|���z. �O�~ �}���w�u�� �y �t���|�w�u�~ ���u���u�������p�y�r�p����
���r���y�} �������t���} �y �}�����|���� ���q�|�p������ ���r���u�z �w�y�x�~�y �y �~���������u���p �{�p�{ �������������~�y�u �~�p���y�� �t�~�u�z �u������ �������|�u�t�~�u�u �y�x
�}�~���s�y�� �������������~�y�z ���r���|�����y�y �q�y�������u���� �r �s�u���|���s�y���u���{���z �y���������y�y.
�B ���������{���} ���x���{�u ���|���r�� «�s�p���}���~�y��» ���q�|�p�t�p�u�� �~�p�y�r�������u�z ���u�~�~���������� �y �t�|��
�y�~���������p�~���u�r �t�p�w�u �q���|�����u �y�x�r�u�����~�� �r �������u���p�~�y�y «���������{�p�� �s�p���}���~�y��». �`�����~���{���u
�r�����p�w�u�~�y�u «�q�p���p�~���� �v�{��»
�������� �~�u �r �����|�~���z �����u���u�~�y, �~�� ���}�����| ���u���u�t�p�u��. �R�p�}���} �s�|�p�r�~���} �r ���������y�z���{���z
���{�������x�y���y�y ���r�|���u������ �R���u���p. �B���{�����s �����u���y���u���{���z �����r�u�����~�������y �y�}�u�u������ ���p�y�~�����r�u�~�~���u
�s���|���q���u ���r�u���u�~�y�u, �{�����������u �y �r�����p�w�p�u�� ���u���r���� ���p������ �������s�� �����~�����y�� �~���������u���� – �N�O�O.
�P�u���r���}�y ���|���r�p�}�y ���u�|���r�u�{�p, �����q���r�p�p���u�s�� �r �{�����}�����u, �q���|�y
�� �s���|���q���} ���r�u���u �H�u�}�|�y. �^���� �s���|���q���u ���r�u���u�~�y�u �����������p�|�y���� �r���������x�t�p���� ���������{�y�u
�t�y�x�p�z�~�u���� �y �{�p�w�t���z �����q���r�p�r���y�z �r �P�p�r�y�|�����~�u �Q�������y�y ���}���w�u�� �����y�{�����~���������� �{ ���������u�~�y��
�C�p�s�p���y�~�p, �r���u���r���u ���u���u�t�p�r���u�}�� �|���t���} �r�y�t�u�~�y�u �H�u�}�|�y �y�x �{�����}�����p. �B���������x�t�p�~�y�u �������s��
�s�|���q�p�|���~���s�� ���t�r�y�s�p �r ���u�|���r�u���u���{���} �}�y�������������u�~�y�y �r �r�������p�r�����~���} ���p�r�y�|�����~�u �q���|��
���p�}���z ���|���w�~���z ���p�q�������z. �N�� �q�|�p�s���t�p���� �y�������|���x���r�p�~�y�� �����~���p�z���y�� ���u���~���|���s�y�z �������~���{���z
�~�p���{�y �y ���u���~�y�{�y ���������{�y�} �y �������~���{�y�} ���������y���u�|���} �y �t�y�x�p�z�~�u���p�} �{�p�w�u������ ���t�p�|������
�r�����|�����y���� �r�y�t�u�~�y�u �H�u�}�|�y �y�x �{�����}�����p �r �������z �R���u���u. �@�r������ �������u�{���p �_���y�z �Y�p�|�p�u�r �����{�p �~�u �����y�~�y�}�p�u�� ���p�t�������~���� �����x�t���p�r�|�u�~�y�z �y ���y����
�s���r�����y��: «�P���t���w�t�y���u, �u���u ���p�~��».
«�R���u���p» ���������y �s�������r�p. �E�u �s���|���q���u ���r�u���u�~�y�u �~�p�r���t�y�� �����u���u��. �N�� ���u���u����
�����u�t�������y�� «�x�p���������y����» ������ �����u����, ���� �u������ ���w�y�r�y���� �u�u. �K�p�{ ������ �q���t�u�� ���t�u�|�p�~��? �B
�������} �}���w�~�� �q���t�u�� ���t���������r�u���y��������, �������p�r �r �Q�������{�y�z �P�p�r�y�|�����~ �y ���{���~���r���y���� �r
�x�p�������|�y ���������{���s�� �|�u���p �� �w�������p�~�y�u�} �������u�z�{���r �y �����������y�r���y���� �~�p �}�������{�y�u �s�|���q�y�~��.
�N�p�r�u���~���u �������u ���p�y�~�����r�u�~�~���u �s���|���q���u ���r�u���u�~�y�u �u���u �y�}�u�u��
�y ���}�����| �����s��, �{�p�{ �}�p�|�� �u���u �x�~�p�u�� ���u�|���r�u�{ �� ���r���u�z ���|�p�~�u���u �y �{�p�{ �}�~���s�� �~�u�r�u�t���}���s��
�u���u ���p�y�� �H�u�}�|��. �P�u���u�t �����y�} �~�u���q�������~���} �}�y�����} �������u���y���u�|�y ���������r�����r������ ���r���� �}�p�|��������
�y �r �����w�u �r���u�}�� ������������ ���r���u �x�~�p���u�~�y�u, ���������}�� ������ �{�p�w�t���z �y�� ���p�s �r �������} �}�y���u
���{�p�x���r�p�u�� �r�|�y���~�y�u �~�p ���q������ ���������{��������. �P���������}��-���� �����u���p �y�}�u�u�� �x�~�p���u�~�y�u �N�O�O-�R���u����, ���� �u������ �R���u����, �~�p�����t�����u�z���� �r�� �r�|�p�t�u�~�y�y
���u�|���r�u���u���{���s�� ���p�x���}�p.
EXPO Japan-2005:
���m������w���V�A��u�t�@�~�n�C�����@�X�x�^���[�i

�@���m�����͓��{�ŊJ�Â����S��ڂ̖����ł��B���܂ōs��ꂽ�S�Ă̖����Ƀ\�A�͎Q�����Ă��܂����B�\�A�����āA���߂ă��V�A�Ƃ��ăp�r���I�����o���̂��A����̖����Ȃ̂ł��B���\�A�̍��X���A�܂�E�N���C�i�A���g�A�j�A�A�O���W�A�A�A�����j�A�A�A�[���o�C�W�����A�J�U�t�X�^���A�E�Y�x�L�X�^���A�L���M�X�A�^�W�L�X�^�������ꂼ��o�W���܂��B���킹��120�̍��X����̑傫�ȎP�̉��ɏW�܂�܂��B
21���I�ɂ����鏉�߂Ă̈��m�����̃e�[�}�́u���R�̉b�q�v�Ƃ������Ƃł��B�e���͂��̑傫�ȃe�[�}�ɂ��Ă��ꂼ��̗����Ɨ��O��i���悤�Ƃ��Ă��܂��B
���V�A�́u���R�̉b�q�v�Ƃ�������e�[�}���u�Љ�ƒn���̒��a�v�Ɖ��߂��܂����B�܂�u���R�̉b�q�v�Ƃ����ꍇ�A���̎��R�ɂ͎���̊������łȂ��A�F�����܂܂�Ă��܂��B�b�q�Ƃ͓��]�ł���A�����̐������l����\�͂����łȂ��A�n���̂��Ƃ�F���̂��Ƃ��܂߂čl����\�͂̂��Ƃł��B�n����F���Ȃ��ɁA�l�Ԃ̐������l���邱�Ƃ͂ł��܂���B�l�Ԃ͉F���ƒ��a���Đ����Ă���̂ł��B���ꂪ�A����A���V�A���W�J����ŏd�v�̃e�[�}�ł��B�p�r���I���̐^��������Œn����\����������ɓW������A���̎����������������Ă��܂��B
�����ł́A�V�����T�O�i���V�A��Łg�C�@�Q�M�O�N�I�` �N�O�O�R�U�E�Q�\�h�j���W�J����܂��B20���I�̏��ߍ��A���ڂ��W�߂������w�Ɖ��w�̔��W�ɂ���āu�������v�Ƃ������_���o�ꂵ�A���R�Ȋw�̐��E�ɑ傫�ȉe����^���܂����B�u�m�I�X�t�F���v�Ƃ����l���������̗���̒�����o�Ă��܂��B
�u�m�I�X�t�F���v�Ƃ������t�͓�̌�傩��Ȃ��Ă��܂��B�u�m�I�v�Ƃ̓M���V�A��Œm�b�܂��͐��_�̈Ӗ��ł��B�u�X�t�F���v�͋����������Ӗ��ł��B���V�A�͐l�Ԃ̐��_�Ɖb�q����ъ��Ƃ̃n�[����[���d�����āA���݂Ɩ����ɂ��Ă̍l�����������܂��B����Noosphera�Ƃ����T�O�́A���V�A�̊w�҃��F���i�c�L�[ (V.Vernadskii 1863-1945)��20���I���߂ɓW�J�����N�O�O�R�U�E�Q�@���_����b�ɂ��Ă��܂��B�����č���̖����ł��Љ�Ɗ��̋������������Ƃ��Ă��܂��B���̑傫�ȃe�[�}���ǂ̂悤�ɎЉ�ƒn���̒��a�������Ă����̂��A�ƂĂ������[�����̂ł��B
���̃v���W�F�N�g��S���v�m�̃V�����G�t���́A�v�ߒ��ɂ����đ�ϋ�J������A�����܂łɎ��Ԃ����Ȃ肩�������Ƃ������Ƃł��B���{�ƃ��V�A�̌��z�Ƃ�f�U�C�i�[�����́A���{�̐����ȉȊw�Z�p�̗͂ɂ�肱�̃v���W�F�N�g���������邱�Ƃ��ł��܂����B
���ɂ��̃v���W�F�N�g�̖ڋʂ̂��ƂȂ̂ł����A�p�r���I���̐^�ɂ͔����������Ă��܂��B���̔����̓K�K�[���������߂ĉF���ɗ��������A�u�n���͐������v�ƗL���Ȍ��t���c���܂������A������C���[�W���A�p�r���I���̔����̌����u���[�ŕ\����Ă��܂��B�܂��A�n����F�������ł͂Ȃ��A���V�A�̑�n��L���Ȏ��R���ے��I�ɕ\������Ă��܂��B������u�m�I�X�t�F���v�̊T�O��\�����̂ƂȂ��Ă��܂��B
�ʐ^�P. ���V�A�p�r���I�������̉��u�C�p���}���~�y�� �~���������u�����v�̌���

�ʐ^�Q�D�V�����G�t�v�m

���E�n�����̃p�r���I������
�@���m������w�O����w�������w�ȂR�N�@�˓c����
�@���͌��݁A���E�n�����̒����A�W�A�����قŌ��n�X�^�b�t�̂���`�������Ă��܂��B���͍��Z���̍����爤�E�n�����ɋ���������A���E���̐l�X���W�܂邱�̃C�x���g�Ɋւ���Ă݂����Ǝv���Ă��܂����B�K�����̂����ׂɂ���
�@�J���̂P�O���قǑO�ɁA�p�r���I���ɗl�q�����ɍs�����Ƃ��ɂ́A�ْ��̂ق��H���W�҂��������������̂ł����A�S���p�ꂪ�ʂ��Ȃ����A�܂��Ă⒆��������ɗ����܂���ł����B�K���Ȃ��Ƃɂ��܂��ܖ��É���w�ɗ��w���̃E�Y�x�L�X�^���̒j�������āA�ʖ���ďo�Ă���܂����B���̌��ʁA�������̓W���[�i���X�g�ƊԈႦ���Ă������Ƃ�������܂����B�����ő��Z�Ȋْ��̓W���[�i���X�g�Ɏ��Ԃ������]�T���Ȃ������Ƃ������Ƃł��B���E�̒��ŃC�G�X�E�m�[�Ƃ����ȒP�ȉp�ꂪ�ʂ��Ȃ��Ƃ��낪����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂ł��B���͂��������p��ɂ����M���Ȃ������̂ł����A�܂��������t���ʂ��Ȃ��Ƃ������Ƃɑ傫�ȕs���Ƃ��ǂ������������܂����B����͓����̃A�e���_���g�ɂƂ��Ă������������炵���������͉p��̂ł��錻�n�X�^�b�t������܂ŕs���ȓ��X���������܂����B��x�������V�A��̂ł�����{�l�X�^�b�t�̎����ăq�������O�����邱�Ƃ��ł��܂������A�J���O�̈�T�Ԃ͌��n�X�^�b�t�ƃR�~���j�P�[�V�������قƂ�ǎ��Ȃ���Ԃ������̂ŁA�������͐}���ق�C���^�[�l�b�g�Ŏ������W�߂ă^�W�L�X�^���ɂ��Ēm����[�߂邱�Ƃɂ��܂����B���̍ۂɊ������̂́A�����A�W�A�Ɋւ����ʂނ��̖{���{���ɏ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���s�p�̃p���t���b�g�����̍��X���͔����A���͒����A�W�A�̏�s�����������悤�ȋC�����܂����B���܂�̎����̏��Ȃ��ɍēx�s�������������́A��N����ɏ��n�挤���̍u�`�ł����b�ɂȂ��������搶�̌�������K��܂����B�搶�͂��낵���̃z�[���y�[�W�▯�����z�Ɋւ��鎑���������ɏЉ�Ă��������āA�{���Ɋ��ӂ��Ă��܂��B���͍�N�����搶�̍u�`���Ă������Ƃɂ܂��^���I�Ȃ��̂������܂����B�l�ꔪ�ꂵ�Ȃ���������邤���ɁA�����A�W�A�̗��j�╶�������̍��X�ɂ͂Ȃ������Ɩʔ����������Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B���̍����玄�ɂ͒����A�W�A�̂��Ƃ�����Ĉ��E�n�����ɗV�тɗ������X�ɏЉ�����Ƃ����C���������܂�Ă����悤�ȋC�����܂��B���̒����Ɋւ��Ă����܂ł͊C�݉����̓s�s�ɂ�������������܂���ł������A�ŋ߂ł͓����̏Ȃɂ��Ēm�肽���Ǝv���悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̂悤�ɐV��������ɋ��������Ă����Ƃ�{���ɂ��ꂵ���v���܂��B
�@�Ƃ���ł������Ă��邤���ɓW��������������������A�J���O�̓�����n�܂�܂����B���n�A�e���_���g�͂܂��������Ă��܂���ł������A���̍��ɂ͒����A�W�A�̎��Ԃ̊��o�����{�l�̂���Ƃ͏����Ⴄ�Ƃ������ƂɋC�Â����߁A���������ׂ������Ƃɐ_�o�����茸�炷�̂͗ǂ��Ȃ����Ƃ��ƌ��܂����B�J��̍��ɂ͌��n�A�e���_���g���������A���͊������C�����ň�t�ł����B�ޏ������͓��{�l�Ƃ͈قȂ�͂�����Ƃ����������痧���ŁA�������Ƃ��Ȃ��悤�Ȗ����ߑ��𒅂Ă��܂����B�܂�����������b�����Ƃ��ł��ĂƂĂ������ȕ��X�ł��B�^�W�L�X�^���͖{���̎���炩���E�n�����ɓ����ł���X�^�b�t�̐l�������Ȃ��悤�Ȃ̂ł����A����ł��ޏ������͋��͂��ē����Ă��܂��B���m��ʍ��œ������ƁA�������邱�Ƃ͖{���ɑ�ς��Ǝv���܂��B���͌������a�Ȃ̂ŊO���ŕ����Ă݂悤�Ƃ����l���͂���܂���ł������A�ޏ����������ē��{���o�đ��̍��X�̕����ɐG��Ă݂�̂��ʔ����̂ł͂Ȃ����ƍl������悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̂悤�ȍl������g�ɂ���ꂽ�̂��������v���܂��B
�@�������Ȃ��猻�݂ł����̉p��̕��s������A�R�~���j�P�[�V�����ɂ�����s�����������܂��B�����͉p������܂�����Ȃ��������Ƃ�������Ă��܂��B�������炢�v�������Ȃ��ƌ�w�͕�����C�ɂȂ�Ȃ��̂��ȁH�Ƃ��v���̂ł��ꂩ�班���������Ă��������Ǝv���܂��B
���E�n�����J��������������O�����B���n�X�^�b�t�̃y�[�X��l�������������킩���Ă��ĕ��͂������]�T���o�Ă��܂����B����̓^�W�L�X�^���⒆���A�W�A�̂��Ƃɂ��Ă͏Љ�邱�Ƃ��ł��܂���ł������A����̓p�r���I���̎ʐ^���Y���ĉ����ʔ����G�s�\�[�h�����������Ǝv���܂��B���ꂩ�疜���ɗ���̍ۂɂ̓��V�A�قɑ����Ē����A�W�A�����قɂ��z�����������B�S��肨�҂����Ă��܂��B
G. Kennan�fs visions of �gthe Russian Future�h
and
(Reflections on G. Kennan�fs collection of
papers �gAmerican Diplomacy�h)
Lomaeva Marina
research student of
Aichi Prefectural University
1
Fully aware that it does
not fit the framework of �eacademic writing�f, I cannot but start this short
essay with a �elyrical�f preface. To a Russian girl born in the
pre-Perestroika era, growing through the late 1980s and early 1990s
– the years of sweeping social change and fervent belief in the liberal �ebright
future�f and �edemocratic institutions�f
– graduating from high school in the fateful year of 1998 (when
the Russian government was forced to admit its failure to fulfill its financial
obligations – the so-called �edefault�f catastrophe, which hit every one of us in
the pocket and ruined our hopes of studying abroad at our parents�f expense), getting
higher education in the cynical atmosphere of �evulture capitalism�f,
flagrant social injustice and penetrating corruption (the years of public
disillusionment with the Yeltsin administration and the Russian �ebrand�f of democracy,
the words �ereforms�f and �eliberals�f turning into terms of abuse, and the
powerful class of �eoligarchy�f emerging) – and finally escaping to Japan to
proceed with my studies in a more academic milieu (which was only possible
because is no Iron Curtain any more: no bars to international exchange, and no
limits to brain drain as its negative consequence) – to a Russian girl,
undergoing a painful transition from the adolescent fascination with Western
culture and values and regarding the English language as a path to freedom to a
bitter encounter with geopolitical realities, George Kennan�fs
incisive works were a revelation.
Half a century ago Mr.
X published his much-talked-of article �gThe Sources of Soviet Conduct�h
in �gForeign Affairs�h – a classic
paper that became an important milestone in the postwar
The concept of
containment soon assumed an air of military confrontation, and was repeatedly
invoked for justification of the Korean and Vietnamese War, although Kennan later argued that his original intention was to suggest
the �epolitical containment of a political threat�f and not the active
containment of the
The foregoing papers and
the concerns expressed in them have become the subject of most exhaustive
studies of the Cold War in the last quarter of the 20th century, and
as a result of it, the revisionist line focusing on the failings of the
post-war US foreign policy is firmly established now, so I see no point in
going over that much discussed topic. In this essay I would like to turn to
another incisive paper by Kennan, published in
�gForeign Affairs�h on the heels of �gThe Sources of Soviet Conduct�h, which seems
to have been long overlooked by both the scholars in the author�fs homeland and
their ideological adversaries overseas. �gAmerica and the Russian Future�h,
as its name suggests, offers a futurological sketch of �g
Futurology as a social
science is placed by popular belief somewhere between the more reliable
�estatistics�f (that is, sociological research) and wild guesses of science
fiction writers and soothsayers (ranging from the renowned Nostradamus
to street charlatans). During the Cold War the attention of the public on both
sides of the Iron Curtain was drawn to works examining the potential
consequences of a nuclear conflict with �eprecise�f methods of technological
forecasting and mathematical modeling (e.g. Herman Kahn�fs �gOn Thermonuclear
War�h (1960)). Kennan�fs paper is nothing of the kind –
it does not stir your imagination with apocalyptic visions of the future, being
based on the author�fs diplomatic experience and expertise it offers no magic
formula (mathematical or other) for �eaccurate predictions�f, its tone is rather
cautious than assertive, and it abounds with warnings to US foreign policy
makers, making its approach slightly moralistic, which might seem boring to an
ordinary reader. And yet reading his astute message fifty years later, I find
his insight awesome, the neglect with which his warnings confronted – regrettable,
and the conclusions he arrives at – deserving undivided attention of officials
of the Ministries of Foreign Affairs, in the former rival superpowers as well
as in Eastern European countries undergoing transition in the political,
economic, and social fields.
In contrast to the
Soviet government, depicted by Kennan in his previous
paper as secretive, duplicitous, suspicious on the verge of paranoia, and
basically unfriendly to its �ecapitalist neighbours�f,
a future Russian government would be �gtolerant, communicative and
forthright in its relations with other states and people�h (p. 137), �gthe
Russia of the future�h will �glift forever the Iron Curtain�h, �grecognize certain
limitations to the internal authority of the government�h, �gabandon, as ruinous
and unworthy, the ancient game of imperialist expansion and oppression�h (p.
143). This marvellous change, however, would not take
place unless certain conditions are satisfied on the part of the �eWestern
well-wishers�f, to whom the author addresses a series of warnings, showing deep
concern over �gour (that is, American – L. M.) inveterate tendency to
judge others by the extent to which they contrive to be like ourselves�h
(p.135). The following arguments can be considered today as applicable to most
of the US dealings with Russia as well as other members of the world community:
�gno members of future Russian governments will be aided by doctrinaire and
impatient well-wishers in the West who look to them, just because they are
seeking a decent alternative to what we know today as Bolshevism, to produce in
short order a replica of the Western democratic dream�h (p.135) – the failure to
correspond to this �edream�f is exactly the charge which the successive Russian
governments constantly face, as if there were a �edemocratic yardstick�f that
international observers could apply universally, something like a fixed value
or a limited range of values, the deviation from which could be automatically
qualified as a �etrend toward despotism�f or �egross violation of human rights�f �c
Kennan urges the
American foreign policy makers to recognize that �gour institutions may not have
relevance for people living in other climes and conditions�h and that �gthere can
be social structures and forms of government in no way resembling our own and
yet not deserving of censure�h (p.135) and stresses that �gof one thing we may be
sure: no great and enduring change in the spirit and practice of government
in Russia will ever come about primarily through foreign aspiration or
advice�h (p.151). The last statement might seem as a matter of course,
and yet it was the biggest stumbling block for the post-Soviet
The first liberal
administrations of the early 1990-s, who made a conscious attempt to follow the
advice offered by its Western colleagues but failed to produce an immediate
effect with their reforms, became the hostages of that well-meant advice: they
were severely criticized by their successors for acting as �eyes-men of the
West�f (one of them, the foreign minister Andrei Kozyrev,
was actually nicknamed �eGospodin Da�f – �eMister Yes�f). The same hackneyed Soviet
allegations of �eselling Russia to the West�f and �efifth column�f were brought up,
resulting in the grotesque spy charges brought against Russian scientists and
reporters, e.g. the trials of Pasko and Danilov – perhaps, not the not the first class
journalists and researchers, but there is still no reason to send them to jail!
The young liberal movement was attacked as pro-Western and unpatriotic (a trend
accounting for the popular usage of the words �eliberal�f and �ereforms�f as terms
of abuse), which allowed their political opponents to unleash a strong
nationalistic (that is, anti-Western, and particularly anti-American) wave and
consolidate under the leadership of Putin. President Putin never fails to meet their expectations and
persistently refers to some unspecified �eexternal enemies�f hatching sinister
plots against our country, once – the �ggreat and powerful�h Soviet Union, today
– the weakened new Russia, �gdefenceless on its both
Western and Eastern borders�h (see his Address of September 4, 2004,
following the Beslan tragedy).
And yet it has
apparently taught no lesson to the Western �ewell-wishers�f: they do not realize
that calling on Russia to abide by their instructions in democratizing domestic
institutions (which is often interpreted as attempted interference in the
internal affairs) and correcting its foreign policy line (which is usually
presented by officials as part of �ethe world plot against Russia�f, playing on
the old fears of �ecapitalist encirclement�f) leads only to further undermining
the already weakened position of the liberal minority in Russia, who, whenever
their appeals to the public coincide with those in the foreign editorials, get
labeled as �eWestern sympathizers�f and are never credited with ability to think
or act independently. Here, another Kennan�fs warning
seems to be worth paying heed to:
These Russian liberals (in
the future
The foregoing paragraph
may provide a clue to the latest curious phenomenon in the cultural life of
2
So much for the problems
the new
We are all agreed, for
example, that the Baltic countries should never again be forced against the
innermost feelings of their peoples into any relationship whatsoever with a
Russian state; but they would themselves be foolish to reject close and
cooperative arrangements with a tolerant, nonimperialistic
Russia, which genuinely wished to overcome the unhappy memories of the mast
and to place her relations to the Baltic peoples on a basis of real respect and
disinterestedness (p. 141).
The strained relations
between Russia and the Baltic countries have shown no sign of improvement over
the last decade, and the persistent attempts of local officials to build a
monument to Nazi soldiers or linguistic discrimination of Russian minorities
are only particular instances of the more general problem: the evaluation of
the occupation of the Baltic states by Soviet troops, preceding the outbreak of
the Second World War. Should the present Russian residents of the Baltic republics,
making up a large proportion of the overall population in Estonia and Latvia,
be considered as descendants of the �eSoviet invaders�f and forced to leave or
fully assimilate? Should the leaders of these republics agree to take part in
the celebrations of the 60th anniversary of the Allies�f victory in
the Second World War? Until that crucial question finds a definite answer, the
idea of �gclose and cooperative arrangements�h between
The following paragraph
directly pertains to the hotly disputed Ukranian
issue:
The
The author is very
circumspect in considering the �gthe final status of the Ukraine�h, warning the
reader that the subject of �gthe relationships between the Great-Russian people
and nearby peoples outside the confines of the old Tsarist Empire, as well as
non-Russian national groups that were included within that empire�h is an
extremely delicate one (p.140). Kennan obviously
differentiates between the two types of historical provinces constituting �gthe
old Tsarist Empire�h: the developed entities like Poland or Finland, which to a
certain extent retained their institutional arrangements within the confines of
the empire, and the more amorphous national groups, which were to a large
extent integrated and assimilated into it, �gintimately bound up�h with the Great
Russians by virtue of their close economic ties (p. 141). The
With regard to Eastern
European states, Kennan speaks in a more assertive
tone about the rightfulness of their claims on the independent status, but at
the same time expresses concern over the potential excesses of nationalistic
waves (and the present shows that his concerns were not altogether groundless,
the irrational fear of and resentment against Russia on the part of her Eastern
neighbours having grave political consequences such
as the expansion of the NATO eastwards):
As for satellite states:
they must, and will, recover their full independence; but they will not
assure themselves of a stable and promising future if they make the mistake of
proceeding from feelings of revenge and hatred toward the Russian people who
have shared their tragedy, and if they try to base that future on the exploitation
of the initial difficulties of a well-intentioned Russian regime struggling to
overcome the legacy of Bolshevism (p. 141).
Reiterating the
importance of distinguishing between specific regimes, which can be
short-lived or long-lasting, and a nation as a large body of people
united by common descent, culture or language, and inhabiting a particular
territory, Kennan expresses his admiration for the
Russian people and �gthe struggle of the Russian spirit through the ages�h (p.
146). Calling on American statesmen to show more foresight and deeper
understanding in their foreign policy toward
We will get nowhere with
an attitude of emotional indignation directed toward an entire people. Let us rise
above these easy and childish reactions and consent to view the tragedy of
Bibliography
George Kennan, �gAmerican
Diplomacy�h, expanded edition (The University of Chicago, 1984)
Graham Evans and Jeffrey Newnham,
�gThe Penguin Dictionary of International Relations�h, (Penguin Books, 1998)
���ȉ��̕��͂́A�w���[���V�A�����x��31�i2004�N11���j�Ɂu���O�̓��A�悭������Ƃ炷�v�Ƒ肵�Ă��낵�����Љ�邽�߂Ɍf�ڂ������̂ł��B�|��҂́A�}���[�i�E���}�G���ł��B
�N�u�r�u���~���u ���|�p�}�� ���r�u���y,
�D�����w�p �~�p �r�u������, ���x�p���y��
�O�t�y�~ ���s���|���{
�y�x �B���u�|�u�~�~���z..
�O �{�����w�{�u «�O�������y��»
|
�K�����w���{ «�O�������y��» �q���| �����~���r�p�~ 8 ���u�r���p�|�� 1999 �s���t�p,
�u�}�� �|�y���� �������� �� �����|���r�y�~���z �|�u��. �N�� �{�p�{�y�u �s���|���r���{�����w�y���u�|���~���u ���u���u�}�u�~�� �������y�x�����|�y �r
�}�y���u �x�p ������ �r���u�}��! �N�u ���q�����|�y ���~�y �y �}�y�{�����{�����} ���~�y�r�u�����y���u���p. �N�p���p�|�p���� ���u�������}�p
���y�����u�}�� ���q���p�x���r�p�~�y��, �x�p�������~���r���p�� �u�u ���������y – ���r�����p�� ���r��������! – �t�u�}���~�������y������
���u���y���u�|���~���u �~�p���������|�u�~�y�u �����~�����~���z ���{���~���}�y�{�y �~�p �~�y�r�� ���������r�u���u�~�y��. �D�����s�~���r �����t
�~�p���y���{���} ���u�������}�p���������r, ���t�~�y �x�p �t�����s�y�}�y �y�����u�x�p���� �{�������� �y �{�p���u�t���� ���������{���s��
���x���{�p... �Q�u�������}�p�������� �w�u ���q�����~���r���r�p���� ���u�|�u�������q���p�x�~�������� �����y�� ���p�s���r �~�u���q�����t�y�}����������
���p���y���~�p�|�y�x�p���y�y ���y�����u�}�� ���q���p�x���r�p�~�y�� �~�p �����~���r�u �����~�����~���s�� �����y�~���y���p, �x�p�t�p�r���y����
���u�|���� �����q���p���� ���p�x�q�������p�~�~���� ���� �r���u�z �������p�~�u �y�����|�u�t���r�p���u�|�u�z-�������y�������r �r �����u���y�p�|���~����
�N�I�I �r�����t�u �T�~�y�r�u�����y���u���p �V���{�{�p�z�t��. �N��, ���r�|�u�{���y���� �����������|�{���z �������~���{���r, �}���w�~��
�r�����r�p���� �x�p���t�~�� �y �{�����������~���u ���������{�y �}���s�����y�� �t�u���u�r���u�r; ���p�{ �y �~���~�u���~�y�u ���u�������}�p��������
�}���s���� �r�����|�u���~������ �r�}�u�����u �� �r���t���z ���u�q�u�~�{�p – �r���u�� �y�~���u���u���������y������ ���������{�y�} ���x���{���} �y
�Q�������y�u�z. �O���u�r�y�t�~��, ������ ���p�{�p�� �y�~���u�������u���p���y�� �����~�����~���s�� �����y�~���y���p �����|�~����������
�y�s�~�����y�����u�� ���p�y�~�����r�� �y ���p�{���p�|���~�������� ���x, �{�����������u �}���s����
���r���x���r�p���� �|���t�u�z, ���r�|�������� �r���u�s�� �|�y���� �}���t�u���~�y�x�y�����r�p�~�~���z ���p�x�~���r�y�t�~����������
epoche – «�r���x�t�u���w�p�~�y�� ���� �����w�t�u�~�y��» – �� �{�����������}
�s���r�����y�|�y �u���u �t���u�r�~�u�s���u���u���{�y�u ���y�|����������, �����|�p�s�p��, ������ �����|���{�� �r�u���������~���u �~�p�����t�y������
�r �����u�t�u�|�p�� �t�������y�w�y�}���s��, ���u�} �y ���|�u�t���u�� ���t���r�|�u���r�����y��������. �S�p�{���u �r�~�������u�~�~�u�u
���s���p�~�y���u�~�y�u ���r���q���t�� �����u�t�����p�r�|���u�� �����q���z �t�p�w�u �q���|�������� �����p���~��������, ���u�} �t�p�r�|�u�~�y�u
�y�x�r�~�u. �P���p�r�t�p, �r���u �~�p���y�~�p�|������ �� �t�p�r�|�u�~�y�� �y�x�r�~�u. �O�~�� ���������t�y�|�� �r�~�������u�~�~�u�u
�~�p�������w�u�~�y�u, ���u���u�t�p�r���u�u���� �r���u�} ���q�y���p���u�|���} ���~�y�r�u�����y���u�����{���s�� �}�y�{�����{�����}�p – �y �{�p�w�t���z
�q���| �����r�p���u�~ �q�u�������{���z�����r���}: «�@ �{�p�{�p�� �}�~�u ���s�������r�p�~�p �����p������ �� �q�������q�u �x�p
�������u�����r���r�p�~�y�u? �O�{�p�w������ �|�y �� �����u�t�y �����q�u�t�y���u�|�u�z?» – ������ �r �y�����s�u �����y�r�u�|��
���~�y�r�u�����y���u�� �r �~�u���r�~��-�|�y�������p�t�����~���u �������������~�y�u.
�` �~�p���p�| �����u�����t�p�r�p���� �r �T�~�y�r�u�����y���u���u �����u���u�{�������� �@�y���y�@�r ���{�����q���u 1998. �B �p�����u�|�u �����s�� �s���t�p ���~�y�r�u�����y���u�� ���u���u�u���p�| �y�x �s�������t�p �N�p�s���� �r �����y�s�������t �N�p�s�p�{������,
���p�������|���w�y�r���y���� ���� �������u�t�����r�� ���� �������������y�}�y���� ���p�r�y�|�����~�p�}�y �r�������p�r�{�y «�^�{������-2005 �@�y���y». �H�t�p�~�y�u ���~�y�r�u�����y���u���p – ���p�}���u �����r���u�}�u�~�~���u, �� ���y�����{�y�}�y
�x�p�����u�{�|�u�~�~���}�y ���|�����p�t���}�y, �~��, �~�p�����t������ �r �~�u�}, ���������� �����r�����r���u���� ���u�q�� �{�p�{ �r
�q���|���~�y���u. �R�p�}���} �w�u ���u�����u�x�~���} �~�u�t�������p���{���} ���~�y�r�u�����y���u���p �� �����y���p�� �u�s��
���p�������|���w�u�~�~�������� �r �������t�~���t�����������~���} �}�u�����u, �y�x-�x�p ���u�s�� �������t�u�~���� �r �~�u�} �~�u
�x�p�t�u���w�y�r�p��������. �P�����|�u �����s��, �{�p�{ ���~�y�r�u�����y���u�� ���u���u�u���p�| �r �����y�s�������t, �{���|�y���u�����r��
�y�x�����p�����y�� ���������{�y�z ���x���{ �����{���p���y�|������ �~�p�����|���r�y�~��. �S�p�{, �{���|�y���u�����r�� �������t�u�~�����r
�~�p���p�|���~���s�� �������r�~�� �x�p ������ �s���t ���������p�r�y�|�� 4 ���u�|���r�u�{�p, �������t���|�w�p�����y�� – 3,
�������t�r�y�~�������s�� �������~�� – �r���u�s�� ���t�y�~ ���u�|���r�u�{. �R�y�����p���y�� ��
�x�p�~�����y���}�y ���� ���������{���}�� ���x���{�� �}���w�~�� �q���|�� �����p�r�~�y���� �� �~�u�r�u���~���} ���|�p�}�u�~�u�} ���r�u���y.
�S���u�q���r�p�|�y���� �{���~���u�������p�|���~���u �y�x�}�u�~�u�~�y��. �S�p�{, ���t�~�y�} �y�x �����u�y�}�����u�����r �}�p�|�����y���|�u�~�~�������y
�s�������� ���������{���s�� ���x���{�p – �r���x���r�p�����u�z �x�p�r�y������ �� �����u�����t�p�r�p���u�|�u�z �{�y���p�z���{���s�� ���x���{�p – ��
�����y���p�| �r���x�}���w�~�������� �������p�~���r�|�u�~�y�� �q�|�y�x�{�y��, �t���r�u���y���u�|���~���� �����~�����u�~�y�z ���� �������t�u�~���p�}�y,
�r ���u�x���|�����p���u ���u�s�� �~�p �������{�p�� �����w�t�p�|�p���� �������q�p�� �p���}�������u���p �����q�����~�������y. �P���y�~���r �x�p
�������{�� ���������u���p ���q���p�x���r�p���u�|���~���s�� ���{�����u���y�}�u�~���p �}���}�u�~�� ���{���~���p�~�y�� �����u�~�~�u�s�� ���u�}�u�������p,
�� �����y�s�|�p���y�| �������t�u�~�����r �{ ���u�q�u �t���}���z, �s�t�u �}�� ���p�������|���w�y�|�y���� �{�����w�{���} �x�p �w�p�����r�~�u�z �y
�����p�|�y �s�������r�y���� �q�|���t�� «���{�y���{�y» (�{���������{�y �}�����p,
�����t�w�p���y�r�p�u�}���u �� ���r�����p�}�y �y �����y�����p�r�p�}�y). �R���u�t�y �������s�� �r�u���u�|���� �y �|�u�s�{���s�� ���������~�u�~�y��
�����t�y�|������ ����, ������ �����|�����y�|�� �~�p�x�r�p�~�y�u «�{�����w���{ �O�������y��».
�D�p�|�u�u �}�~�u �������u�|������ �q�� ���p�����{�p�x�p���� ���q �����~���r�~���� �x�p�t�p���p��, �{�����������u �����p�r�y�|�y���� �����y �u�s��
�����s�p�~�y�x�p���y�y.
�X���� ���p�{���u �{�����w���{ «�O�������y��»?
�K�p�{ �� ���w�u �s���r�����y�|, �{�����w���{ «�O�������y��»
�q���| �����x�t�p�~ 8 ���u�r���p�|�� 1999 �s���t�p �������t�u�~���p�}�y-���~�����x�y�p�����p�}�y �T�~�y�r�u�����y���u���p �����u���u�{�������� �@�y���y. �N�p�x�r�p�~�y�u «�O�������y��» �����y�x�r�p�~��
�������p�x�y���� �~�u�������u�t�u�|�u�~�~�������� �y ���p�����y���~�������� ���q���p�x���r�p�~�y��, �~�p�x���r�p�u�}���s�� �Q�������y�u�z. �^����
�~�p�x�r�p�~�y�u �����������u�q�|���|�y �~�p���y �����u�t�{�y, �r���u���r���u �������p�~�p�r�|�y�r�p�� �{���~���p�{���� �� �������z �������p�~���z.
�S�p�{ �������|�����p�|������ �y�} ���|���r�� «�Q�������y��». �B�������|�u�t�����r�y�y �~�p�x�r�p�~�y�u �������z �������p�~�� �����u���u�����u�|��
�~�u���{���|���{�� �y�x�}�u�~�u�~�y�z �{�p�{ �r �~�p���y���p�~�y�y, ���p�{ �y �r �����~�u���y�{�u. �N�p �x�p�{���u���|�u�~�~���u �r
�~�p�����������u�u �r���u�}�� �~�����}�p���y�r�~���u �������y�x�~�����u�~�y�u �������s�� ���|���r�p – «�Q�����y��»
– ���u���p�����u�u �r�|�y���~�y�u ���{�p�x�p�| �p�~�s�|�y�z���{�y�z ���������~�y�} «Russia»,
������ �q���|�� �������p�w�u�~�� �r �t�y���u�{���y�r�u �}�y�~�y�����u�������r�p �y�~���������p�~�~���� �t�u�|. �B �y���������y�y �����~�����u�~�y�z �~�p���y�� �������p�~ �������������~�~��
���y�s�����y�������� �������p�~��-���������u�t�~�y�{�y – �C���|�|�p�~�t�y��, �@�~�s�|�y��, �@�}�u���y�{�p... �B���u ������ �r���u�}��
�Q�������y�� �y �`�����~�y��, �~�u �r�������u���p������ �|�y�����} �{ �|�y����, �����y�t�u���w�y�r�p�|�y���� �r�~�u���~�u�����|�y���y���u���{���s�� �{�������p,
���p�x�r�y�r�p�r���u�s������ ���� ���y�~�������y�t�u – �}�u�w�t�� �����r�����r�p�}�y �������p���p �y �����u�x���u�~�y��. �P�����|�u
�O�{�����q�������{���z ���u�r���|�����y�y �y ���q���p�x���r�p�~�y�� �R�R�R�Q �}�p�����~�y�{ �{�p���~���|���� �r �����������~�� �������p���p –
�����p�t�y���y���~�~���u «�O�������y��» �����p�|�� �������� �|�y �~�u «�O�����������y��» (���� �������~���{���s�� �����y�|�p�s�p���u�|���~���s�� «�������������y�z» – «���w�p���~���z, �������p���~���z»). �B �~�p�����������u�u �r���u�}�� ��������
���|���s �r�����p�| – �������p�� �y�����u�x, �p �}�p�����~�y�{ �����{�|���~�y�|���� �r �����������~�� �����u�x���u�~�y��. �Q�������y��
�����p�|�p �r���������y�~�y�}�p�������� �{�p�{ �q�u�x�y�~�y���y�p���y�r�~�p��, �q�u�x�|�y�{�p��
�������p�~�p.
�B���q���p�r
�r �{�p���u�����r�u �~�p�x�r�p�~�y�� �{�����w�{�p ������ �~�u�����y�����x�p���u�|���~���u �~�p�x�r�p�~�y�u, �t�p�~�~���u �~�p���y�}�y
�����u�t�{�p�}�y, �}��, �r �����|�~���z �}�u���u �������x�~�p�r�p�� ���|���w�~�������� �y ���������y�r�����u���y�r�������� �����~�����u�~�y�z
�}�u�w�t�� �~�p���y�}�y �������p�~�p�}�y, �����p�r�y�} ���r���u�z ���u�|���� �r�������u���y�������� �~�p�{���~�u�� �� �Q�������y�u�z �|�y�����} �{
�|�y����, ���x�~�p���� �� �~�u�z �����q���|�����u, �������t�r�y�s�p������ ���p�}�������������u�|���~��. �I���������y�� ���q�����|�p�r�|�y�r�p�u��
�~�p�����������u�u, �~�� �~�u �x�p�t�p�u�� ���t�~���x�~�p���~�� �q���t�����u�u. �E���|�y �����~�y�}�p���� ���p���� �{�p�{ �x�p�����w�t�u�~�y�u
�~���r���s��, ���� �����t�|�y�~�~�p�� �r�������u���p �� �Q�������y�u�z, �{���������p�� ���� �����p�r�~�u�~�y�� �� �`�����~�y�u�z �r���u �u���u
�����u�q���r�p�u�� �r ���p�����y���~���} �������������~�y�y, �y�}�u�u�� �r�p�w�~���u �x�~�p���u�~�y�u.
�P���y�~�y�}�p��
�{�p�{ �t�p�~�~�������� ����, ������ �r �`�����~�y�y �t�� ���y�� ������ �}�p�|�� �x�~�p���� �� �Q�������y�y �y �}�p�|�� �u�z
�y�~���u���u������������ (������ �q���|�� ���x�r�����u�~�� �����y �����x�t�p�~�y�y «�O�������y��»),
�}�� �r�y�t�y�} �~�p�����p�r�|�u�~�y�u �t�u�����u�|���~�������y �~�p���u�s�� �{�����w�{�p �r �������}�y�����r�p�~�y�y �~�u�����u�t�r�x�������s��,
�����q�����r�u�~�~���s�� �r�x�s�|���t�p �~�p �Q�������y��. �M���u �����{���|�u�~�y�u �}�~���s�� ���p�x�}�����|���|�� �� �Q�������y�y �y
�R���r�u�����{���} �R�����x�u. �N�� �~�p���y �����u�t�����p�r�|�u�~�y�� – �r�� �}�~���s���} ���������y���~���u – ���p���������p�|�y���� �r
�����p�� �r�}�u�����u �� ���p�����p�t���} �R���r�u�����{���s�� �R�����x�p. �I�x�r�|�u�{�p���� �������{�y �y�x �y���������y�y �~�u ���x�~�p���p�u��
�q������ ���r���x�p�~�~���}�y �y�}�y ���� �����{�p�} �y �~���s�p�}. �O�����u�t�u�|���� �~�p�����������u�u, �y���������y�� �~�u
�������u�t�u�|���u�� �q���t�����u�s��. �O�t�~�p�{�� �����y���u�|�� �������u������ ���������p����, �~�p�����p�r�|������, �r�����������p���� �r
�����|�y ���������r�u���y���u�|��. �I �t�p�w�u �s���r������ �� �����}, ������ �������t�u�~���� �t���|�w�~�� �~�p ���r���u�} ���������u
�����|�����y���� �����u�t�����p�r�|�u�~�y�u �� �Q�������y�y, ���p�}�������������u�|���~�� �r�����p�q�����p���� �y�~���u���u�� �{ �~�u�z,
�������t�u�|�p�r ���u�����u�x�~���� �r�~�������u�~�~���� ���p�q������, �~�p �t�u�|�u �~�u������������ �����u���t���|�u���� �t�y�t�p�{���y���u���{����
�������~�������� �����u�����t�p�r�p���u�|�� �y �}���|���p �����u�t�������p�r�y���� �y�~�y���y�p���y�r�� �����u�~�y�{��. �N�p�����y�}�u��,
���p�����{�p�x���r�p�� �� �{�y�~�u�}�p�����s���p���u – �����r�u�����{���} �~�p���|�u�t�y�y ���� �r���u�}�u�~ �^�z�x�u�~�����u�z�~�p –
�������u������ ���s�|���q�y�������� �r �y���������y�� �y
�����p�t�y���y�y �����r�u�����{���s�� �{�y�~��. �O�t�~�p�{�� �~���~�u���~�y�} �������t�u�~���p�} �y���������y�x�} ���w�u �~�p�q�y�|
�����{���}�y�~��. �O�����x�~�p�r ������, �����y�����t�y������ �x�p���p�����y���� ���u�����u�~�y�u�} �y �����u�t�������p�r�y���� �y�}
�r���x�}���w�~�������� ���p�}�������������u�|���~�� �����{�������� �t�|�� ���u�q�� «�O�������y��».
�I �����s�t�p �������t�u�~���� ���p�~�����u �����u�����t�p�r�p���u�|�� �����r�u�����p���� �����{�������y�� �r �}�y���u �����r���u�}�u�~�~���s��
���������y�z���{���s�� �{�y�~�u�}�p�����s���p���p – ���������p�r�y�r���y���� �r �N�p�s���z���{����
���y�|���}�����u�{��, �x�~�p�{���}�������� �� �~���r�u�z���y�}�y �u�s�� �r�u���~�y���}�y: ���r�����u�~�y���}�y �R���{�������r�p, �A�p���p�q�p�~���r�p, �C�u���}�p�~�p. �P�������} �����y�����t���� �y ���p�}�y ���������r�u���p����
�����u�����t�p�r�p���u�|��, �����r�u������ �u�}��, �~�p�����y�}�u��, �������}�������u���� ���y�|���} «�V���������p�|�u�r, �}�p���y�~��!».
�S�p�{�y�} ���q���p�x���}, �~�p�} �������p�u������ �����|���{�� �~�p�q�|���t�p���� �y ���u�����u�|�y�r�� �w�t�p���� �����s�� �}���}�u�~���p,
�{���s�t�p �������t�u�~���� – �{�p�w�t���z ���� �����t�u�|���~�������y �y �{�p�w�t���z ���r���y�} �������q���} �������u�} –
�����x�~�p�{���}�������� �� �Q�������y�u�z. �R �t�����s���z �����������~��, �������p�������� �r���w�p���� �y�~���u���u�� �{ �Q�����y�y, �~�p�����y�}�u��, �y�x �y�~���u���u���p �{ ���u���}�u�~�r���{����
– �����p�t�u�t�����{�u �r���u�� ���|�u�{�������~�~���� �}���x���{�p�|���~���� �y�~���������}�u�~�����r – �}�~�u �{�p�w�u������ ���u�}-����
�~�u�q�|�p�s���r�y�t�~���} �y �~�u�������p�r�u�t�|�y�r���}, �������{���|���{�� �x�~�p�{���}�����r�� �� �~�y�} ���r�|���u������ �����u�w�t�u
�r���u�s�� �x�~�p�{���}�����r���} �� ���|�u�{�������~�~���}�y �y�~���������}�u�~���p�}�y �{�p�{ ���p�{���r���}�y �y �y�}�u�u�� �}�p�|��
�����~�����u�~�y�� �{ �Q�������y�y. �B�������u���p �� ���u�}-���� �~���r���} �r�p�w�~�p ���p�}�p ���� ���u�q�u, �y �� �����y���p��, ������ �~�u �������y��
�������p�������� ���{�|�p�t���r�p���� �u�u �r �y���������y���u���{���u �������{�����������r�� �|���w�u ���u�s�� �q�� ���� �~�y �q���|�� –
�~�p�����y�}�u��, �Q�������y�y.
�P�����{���|���{��
�~�p�� �{�����w���{ �����p�r�y�� ���r���u�z ���u�|���� �y�x�����u�~�y�u �Q�������y�y �� «���y�������z �t�����{�y», �r �~�u�s�� �}���w�~��
�|�u�s�{�� �r���������y���� �y �r���z���y. �B �{�p�q�y�~�u���u, �����u�t�������p�r�|�u�~�~���} ���~�y�r�u�����y���u�����} �t�|��
�t�u�����u�|���~�������y «�O�������y��», �u������ ���q���y���~�p�� �{���|�|�u�{���y�� �{�~�y�s
�~�p ���������{���} ���x���{�u, �����t�p���u�~�~�p�� �{�����w�{�� �}�u���u�~�p�����} �K�p���� �R�������}��, �����x�t�p�~�� �����|���r�y�� �t�|��
���p�}�������������u�|���~���� �x�p�~�����y�z. �R�����t�u�~���� �}���s���� ���q���p�������� �� �����u�����t�p�r�p���u�|�u�} �y�x �Q�������y�y,
���������y�z���{�y�}�y �����p�w�u���p�}�y. �N�� �����y �������} �{�����w���{ �~�u �����p�r�y�� �~�u�����u�}�u�~�~���z ���u�|���� ���p�x�r�y���y�u
���������y�z���{��-�������~���{���z �t�����w�q��, �����������}�� �r �~�u�s�� �}���s���� �r���������y���� �y ���u, �{���� �~�u ���y���p�u��
���u���|���� �����r�����r �{ �Q�������y�y. �O���~���r�~���� ���p������ �{�����w�{�p ���������p�r�|������ �������t�u�~����, �y�x�����p�����y�u
���������{�y�z ���x���{, �~�� �~�u�}�p�|�� �y ���u��, �{���� ���������r�����r���r�p�| �y�~���u���u�� �{ �Q�������y�y �y �x�p�~���|����
���������{�y�} ���x���{���} �������|�u �r���������|�u�~�y�� �r �{�����w���{. �K�����p���y, �r �������} �s���t�� �{���|�y���u�����r��
�y�x�����p�����y�� ���������{�y�z ���x���{ ���������p�r�y�|�� 23 ���u�|���r�u�{�p �r �s���������u �~�p���p�|���~�����s��
�������r�~��, �������t���|�w�p�����y�� – 9, �������t�r�y�~�������s�� �������r�~�� – 4 ���u�|���r�u�{�p. �H�p ���u������ �|�u�� ���y���|��
�������t�u�~�����r �x�~�p���y���u�|���~�� �r���x�������|��, �~�� �����u�����t�p�r�p���u�|�y ���������{���s�� ���x���{�p ����-�����u�w�~�u�}��
�t���|�w�~�� �����t�t�u���w�y�r�p���� ������ �~�u�r�u���~���u ���|�p�}�� ���r�u���y.
�D�u�����u�|���~�������� �~�p���u�s�� �{�����w�{�p �r�{�|�����p�u�� �r ���u�q�� ���{���{�������y�y ���� �I�������y�����{��, �I�t�x�������t�p-�}�����p �y ���������y�}
�}�u�����p�}, �y�}�u�����y�} ���r���x�� �� �Q�������y�u�z; �����s�p�~�y�x�p���y�� �����{���������� �|�u�{���y�z, �����y���u�} �r �{�p���u�����r�u
�|�u�{���������r �r�����������p���� �{�p�{ �����u�����t�p�r�p���u�|�y ���~�y�r�u�����y���u���p, ���p�{ �y �����y�s�|�p���u�~�~���u
�t���{�|�p�t���y�{�y; �����r�}�u�����~���z ���������}������ ���������y�z���{�y�� ���y�|���}���r. �B�� �r���u�}�� ���~�y�r�u�����y���u�����{���s��
���u�����y�r�p�|�� �������t�u�~���� �����u�t�|�p�s�p���� �r �����}�p�������~���� ���p�|�p���{�p�� �q�|�y�~��, ���y�����w�{�y, �q������. �D�r�p
���p�x�p �r �s���t �r���������{�p�u������ �r�u�����~�y�{ «�O�������y��», �r���u �r���������{�y
�{�����������s�� ���p�x�}�u���p�������� �~�p �t���}�p���~�u�z �������p�~�y���{�u. �B ���u�|���} �t�u�����u�|���~�������� �~�p���u�s�� �{�����w�{�p
�~�u �����|�y���p�u������ ���� �}�u���������y�����y�z �t�����s�y�� ���~�y�r�u�����y���u�����{�y�� �{�����w�{���r. �N�� �y�~���s�t�p ���|�u�~�� «�O�������y��» «�r�������t���� �r ���r�u��», �����u�t�����y�~�y�}�p�� ���p�}�������������u�|���~���u
���p�s�y. �N�p�����y�}�u��, �t���{�|�p�t ���q «�O�������y��» �������x�r�����p�| �~�p
�O���{���������z �{���~���u���u�~���y�y, �����������t�y�r���u�z �r �S���{�y�z���{���} ���~�y�r�u�����y���u���u �y�~���������p�~�~���� ���x���{���r
23-24 �y���~�� 2001 �s���t�p. �V�y���p�y�r�p �S�p�{�p���y�{��,
�{�����������z �����s�t�p �r���x�s�|�p�r�|���| �{�����w���{ (���u�z���p�� ���~ �p�����y���p�~�� �K�y�������{���s��
���~�y�r�u�����y���u���p), �r ���r���u�} �r�����������|�u�~�y�y �����t���u���{�y�r�p�|, ������ �~�y �{���|���������~���z ���q�}�u�~ �y�|�y
���p�x�r�y���y�u �t�����w�u���{�y�� �����~�����u�~�y�z �}�u�w�t�� �Q�������y�u�z �y �`�����~�y�u�z, �~�y �����t�t�u���w�p�~�y�u
�������u�����r���r�p�~�y�� �{�����w�{�p, �u�s�� ���p�x�r�y���y�u ���p�}�y ���� ���u�q�u �~�u ���r�|���������� ���u�|���� �t�u�����u�|���~�������y
«�O�������y��».
�H�p���r�|�u�~�y��
�� �����}, ������ «�}�� �~�u �����p�r�y�} ���u�|���� ���r���u�z �t�u�����u�|���~�������y ���p�x�r�y���y�u ���������y�z���{��-�������~���{���z
�t�����w�q��», �y�|�y �� �����}, ������ «�����t�t�u���w�p�~�y�u �������u�����r���r�p�~�y�� �{�����w�{�p, �u�s�� ���p�x�r�y���y�u ���p�}�y ����
���u�q�u �~�u ���r�|���������� �~�p���u�z �x�p�t�p���u�z», �}���s���� �x�r�����p���� �~�u���{���|���{�� �����u���u�~���y���x�~��. �N�� ���q�u
�~�p���y �������p�~�� �~�p �����������w�u�~�y�y ���r���u�z �y���������y�y �������������~�~�� �����y�~�����y�|�y �y�~�t�y�r�y�t�p �r �w�u�����r��
�����s�p�~�y�x�p���y�y, ���u���y���t�y���u���{�y �r�������t�� �y�x-�����t �{���~�������|�� �����y�� �y�~�t�y�r�y�t���r-�s���p�w�t�p�~. �S��
�����r�����r�� �~�u���r�u���u�~�~�������y, ���u �~�u�s�p���y�r�~���u ���}�����y�y, �{�����������u �q���|�y �����y�r�~�u���u�~�� �r
���~�y�r�u�����y���u�� �~���~�u���~�y�}�y ���u�������}�p�}�y �r�������u�s�� ���q���p�x���r�p�~�y�� (�� �s���r�����y�| �� �~�y�� �r ���p�}���}
�~�p���p�|�u), �}���s���� �~�u���w�y�t�p�~�~�� ���u���u���p�����p���� �r �����r�����r�� �����u�r���������t�����r�p, �{�p�{, �~�p�����y�}�u��, �r
���|�����p�u �� COE (Center of Excellence) – ���p�{ �~�p�x���r�p�������� �{�������~�u�z���y�u �N�I�I, �s�t�u, �{�p�{ �����y���p�u������,
���������u�t���������u�~�� �|�������y�u ���}�� – �r�u�t�� �~�u ���������u���~���|�y���� �����s�p�~�y�x�p�������� �~�p�x���r�p���� �y��
«�W�u�~�����p�}�y �����u�r���������t�����r�p»! �@ �}��, �w�y�r�� �r ���p�{���� ����������, �������y�} ����-�����u�w�~�u�}��
�������p�r�p�������� �{�����w�{���} «�O�������y��», �� �{�����������} �}���w�~�� ���{�p�x�p����
�r �����u�� ���������{�p��:
�N�u�r�u���~���u ���|�p�}�� ���r�u���y,
�D�����w�p �~�p �r�u������, ���x�p���y��
�O�t�y�~ ���s���|���{ �y�x �B���u�|�u�~�~���z...
�K�p����
�R�y���� (�T�~�y�r�u�����y���u�� �����u���u�{�������� �@�y���y, �����u���y�p�|���~��������:
�y���������y�� �Q�������y�y)
���Ƃ��܂����I
���m������w�����w�ȑ��@���}����}
�{���A�������Ƃ��܂����B�T�N�قǑO�A���邱�Ƃ����|���ŁA�Ƃ̋߂��̒�����̉�b�����ɒʂ��Ă��܂����B�����u�t���Ȃ����Ă�����A�o�g�̎Ⴂ�����l���w�����b�������Ƃ����ł��Y��邱�Ƃ��o���܂���B�ޏ������{�ɗ��w����Ƃ������Ƃ����c�ꂪ�{���������ł��B�u�ǂ����ċS�̂悤�ȓ��{�l�̂Ƃ���֗��w�Ȃ���̂��v�ƁB�ޏ��́A�s���ȋC�����̂܂܂œ��{�ɗ����ƌ����܂��B�Ƃ��낪�������Ă݂�ƁA��ۂ͋t�ł����B���ɖ��������A�ړI�n�ɒ����܂ŐS�z���đ����Ă��ꂽ�肷��e�Ȑl�X�ɏo��A�u���{�l�͌����ċS�ł͂Ȃ��v�Ǝv���������ł��B����ŁA���͈��m������w�ɓ����ē��{�ꋳ�t��ڎw�����Ƃɂ��܂����B�����A�����ɍs���āu�S�̂悤�ȓ��{�l�v�Ƃ����C���[�W�������ł��y���ł���d���Ɋւ�ꂽ��Ǝv�����̂ł��B�������A���������T���܂����B���{�ꋳ�t��ڎw���̂ɕK�{�́u���ꌤ������v�́A��u��]�҂��������āA���I�ɂ͂���Ă��܂��܂����B�����ł�ނ��u������������v��I�����܂����B�����ŏo������̂��u���낵���v�̉����搶�ł����B�u�`�ł̓z�b�u�X�Ƃ����b�N�Ƃ��A����������_�ɓ���Y�܂��ꂽ�̂ł����A�t�@�V�Y���̐������_�̍u�`�����Ƃ���ϏՌ����܂����B���܂Ŗ����`�Ƃ������̂ɉ��̋^������������Ƃ�����܂���ł������A�搶�́u�����`�������炵���ߌ��v�Ƃ��ăt�@�V�Y���̘b�����Ȃ���������ł��B�����Ă���f��̈��ʂ������Ă��������܂����B���C�U�E�~�l���剉�́u�L���o���[�v�Ƃ����f��ł����A��l���̃A�����J�l���h�C�c�̃u���W���A���\����F�l�Ƃ��郊�]�[�g�n�̃e���X�ł��낢�ł���ƁA�q�g���[�E���[�Q���g�̔����N���˔@�u�����͉��̂��́v�Ƃ����i�`�X�̉̂𗧂��オ���ĉ̂��n�߂܂��B����ƁA����������Ɏ����ʼn̂��A�̗̂ւ�����L����A�₪�ĂقƂ�ǑS���̑升���ƂȂ�܂��B�u���W���A�̃h�C�c�l�́u���Y�}�ɑR���鐨�͂Ƃ��Ĕނ�͗��p�ł���v�ƂԂ₢�Ă��܂����B�������A���ʂ͒m���Ă̒ʂ�ł��B���͂��̃V�[�������ă]�b�Ƃ��܂����B�����č��܂ŋ^��������Ȃ��������Ƃ��u�₢�����v���Ƃ����̖{���Ȃ̂��Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B�Q�N���ɍ������`�搶�́u���ۖ@�v���Ƃ�܂����B�X�E�P�P�������N������A�����搶�͂��̂܂܍s���A���A�ł̋c�_�@���ɂ�����炸�A�A�����J�́A�����̎葱����i�߁A���N�̂R������ɂ͐푈���n�߂�\���������Ƃ������Ⴂ�܂����B���ʂ͐搶�̂�����������ʂ�ł����B���A�́A�푈�̗}�~�͂ƂȂ�܂���ł����B���A�����Łu�悵�v�Ƃ��Ă��������̍l������������������܂���ł����B�����ŁA�����w�Ȃɑ����Ȃ���A�����搶�̂��w���̉��Ŋw�����ʗ��C�w���ƂȂ�܂����B���_�̃e�[�}�́u�J�������Ɛ����I�R���f�B�V���i���e�B�v�ł��B�u�����I�R���f�B�V���i���e�B�v�Ƃ́A�����`�Ƃ��l���Ƃ����ՓI�ȉ��l�Ǝv������̂����ɂ��āu�J�������v���s�����Ƃ�����̂ł��B�����������l�ς͖{���ɕ��ՓI�ł���Ɖʂ����Č�����ł��傤���B��������`�Ƃ����ϓ_���猾���A���l�̉������Ƃ������ʂ�����Ǝv���̂ł��B���E�̓���������ƃO���[�o���[�[�V�����̖��̉��ɁA���ēI�ȉ��l�ς̈ꌳ�I�x�z���i�s���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���_����������A�����I�Ȗ��̔w��ɑ傫���o�ϓI�Ȗ�肪��������Ă���ƍl����悤�ɂȂ�܂����B���͎��̊w�т̃X�e�b�v�Ƃ��Čo�ϊw�̕����l���n�߂܂����B���͑��ƌ�A������w�̑�w�@�Ŗx�搶�ɂ��č��یo�ς̕����u�����̂ł����A�c�O�Ȃ���@�̓����Ɏ��s���܂����B�ꎞ�͊w�Ԃ��Ƃ�f�O���悤�ƍl���܂������A�x�搶�́A�u�X���[���C�t�Ƃ����ϓ_���獡��肽�����Ƃ�������x�l�����炢�����ł����v�Ƌ��Ă��������܂����B���߂́u�X���[���C�t�v�Ƃ������t��������āA�I�X���K�̎�̐��E�Ő�����Ƃ������Ƃ��Ǝv���Ă��܂������A�x�搶�͎R�o��ɂ��Ƃ��A�w��̓��̑��l���������Ă��������܂����B�Ò��͍��̌��ʂ��ǂ�����̂��A�c����w�̒ʐM����ł��B
���U��Ԃ��Ă݂�ƁA������w�͂Q�V�N�Ԃ�̊w�Z�ł����B�����Ƃ����Ԃɉ߂������̂S�N�Ԃ́A�{���ɖ��̂悤�ł����B�ɓ삩��Q���Ԃ������Ė����A���̃L�����p�X�ɒʂ��܂����B�u��ςł����ˁv�Ƃ悭�����܂����A��ɂɎv�������Ƃ͑S������܂���B�ʐM����ƂȂ�Ɓu�u�`�v�͔N��x�̃X�N�[�����O�ł����̌��ł��܂���B���������A�搶��F�B�Ɗw��ɂ��Č�荇�������̂S�N�Ԃ��{���ɓ���L�����Ԃł������Ɗ����Ă��܂��B�Ⴂ�w�������́A������O�Ǝv���Ă��邩������܂��A���m������w�Ƃ������Ƌ�Ԃ́A�Ȃ��Ȃ��o����Ƃ̏o���Ȃ����̂ł������Ǝv���܂��B
�ӎӁI�@�i2005�N�R��20���j

�������ɂāi�����̃P�C�^�C�ŎB�e�j
������킽���͍K����҂��Ă��܂���
���m������w�X�y�C���w�ȁ@�^�[�j�A�E�g�[���X�E�o�X�P�X
������킽���͍K����҂��Ă��܂����B�Ƃ��ǂ��K��������K��܂����B�ł�����́A�ꎞ�̊Ԃł����B�����Ɏ₵���ƈꏏ�ɋ���A�A�]�A�{�肪����߂炦�܂����B
�ꎞ�̍K����s�K���̊ԂŐS���h��Ă��鎞�ɁA�搶�����̎��������܂����B��͂Ȃ����V�A��������̂��A������͂ǂ����Ă������������ɂ��Ă���̂��Ƃ������̂ł����B���V�A��́A���L�V�R�ł������Ă����̂ł����A�����Ⴂ�����烍�V�A���w�ɊS���������̂ŁA��������ɊS�������Ă����Ǝ����Ŏv������ł��܂����B�������A���ۂɃ��V�A�������Ă���ƁA�������V�A�ɊS�������Ă������ǂ����Ƃ͊W�Ȃ��A�����g�����ł���̂�m��܂����B�ł����̊�т͑��̊Ԃ̂��̂ł����B���V�A�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̑��̕��́A�K�������K�����L���邱�Ƃɂ͂Ȃ���܂���B���{�ɗ��ĕ����Ă��Ă��A��т�������ƂƂƂ��ɁA�₵������������X�����������̂ł��B�ł������Ȃ��j�R�j�R���Ă���ꂽ�̂��낤���B
�l�����̂́A�K����҂��Ă��邾���ł͂��߂��Ƃ������Ƃł��B�K���́A���́A���̐S�̒��ɂ��łɑ��݂��Ă����̂ł��B���̍K�����S�̒��ɕ����߂��A���������̂�҂��Ă��邾���ł͂��߂������̂ł��B�S�̒��ɑ��݂���K�����̂��A�����F�l��搶��Ƒ��ȂǑ��҂�A��������芪�����R�ȂNJO�̐��E����̓��������ɉ����āA���҂�O�ɂȂ����Ă����Ƃ��A�K���͍L����A���i�̊�тɂȂ����Ă����܂��B���R�ɔ��݂��킫�܂��B�����������ɍl����悤�ɂȂ��Ă���́A�₵���͂��܂莄��K��܂���B�K���͑҂��Ă��邾���ł͂Ȃ��A����������K����T���A�O�֏o���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�`��̉ԉΑ��Ŋ؍��̗F�l��
�����̏�Ƃ́H�H�H
���������i���m������w�p�Ċw�ȑ��E��؍q��X�`�����[�f�X�j
�����m�̂悤�ɁA���{�����@�ɂ͌l�̐l���d���邱�Ƃ���߂��Ă���B�������A����ɂ́A�u�����̕����ɔ����Ȃ�����v�Ƃ����A�����������Ă���B���@��12���A13���A�����āA22���ɂ܂ł��u�����̕����v�Ƃ������t���p�����Ă��邱�Ƃ�����A���{�l�ɂ͂ƂĂ��d�v�Ȍ��t���Ƃ������Ƃ��f����B
�@���{�ɋ���ƁA�����Ɍ����̕���������Ă��邩�Ƃ������ƂɈӎ��������B�Ȃ��Ȃ�A�����̐l�����̏�ł̓x���z�����̗��o������Ă��邩��ł���B���͎d�����C�O�ɑ؍݂��邱�Ƃ������A���̍ۂ͕K���z�e���ɔ��܂�B�z�e���ɂ͑�́A�u���E���W�v�ƌĂ������̏ꂪ����B�����ł́A�F�e���r��������A�p�\�R����������A�ȒP�ȗ�����������A�A�C�������|������A�������������A�{��ǂ�E�E�E�ƍD���Ȃ��Ƃ����ėǂ��B�����郊�r���O���[���̂悤�ȑ��݂��B����A�����p�\�R�������Ă����Ƃ��A��l�̃C���h�l�V�A�l�����̂��������ʂʼn��y���n�߂��B�ނɂƂ��Ă͂��C�ɓ���̋Ȃł��A���̐l�ɂƂ��Ă������Ƃ͌���Ȃ��B������A���͂��肢�������B�u�����͌����̏�ł��B�����̒��ɂ��鑼�̃����o�[�ɕ��S�̊|����Ȃ��悤�s�����Ă��炦�Ȃ��ł��傤���B�v�ƁB���̒��́u�����̕����v�Ƃ́A�u���l�ɖ��f���|���Ȃ��v���Ƃ��O��ł���B�����ƕ�������Ă��炦�邾�낤�Ǝv���Ă����B�����A�ނ̒��̂���͈�����B�u���E���W���F�̏ꏊ�ł���Ȃ�A�N�ɂ��̕����Ńp�\�R�������錠��������悤�ɁA���ɂ�������x�̉��ʂʼn��y������������B�v�Ƃ����̂��B
�@���{�l�̏ꍇ�A�l�ɖ��f���|���Ȃ����Ƃ��O��ŁA�����̎��R�d����̂����A�C�O�ɍs�����̏펯���ʂ��邱�Ƃ���ł͂Ȃ��B���肢�����ɂ�������炸�A�ނ͍Ō�܂ŁA�ނ̔[���̂����{�����[���ʼn��y���������̂�����B�O���l�̗F�l�̑����́A�u���{�l�͂ƂĂ���V���������A�}�i�[���Ȃ��Ă���v�Ɨ_�߂�B�唼�̓��{�l���������}�i�[��g�ɕt���Ă���̂́A��͂�u�����̕����v�d���Ă��邩�炾�Ǝv����B����Ȓ��ŁA�u���̏ꂾ����A�e�X�������̍D���Ȃ��Ƃ����ėǂ��̂��B�v�Ƃ����C���h�l�V�A�l�̑O��ɂ́A�Ռ������B����́A�u���R�v�ɑ��鑨�����̍��قł���B
�@�����Ⴆ�Ό��@���Ⴂ�A���炪�Ⴄ�B����ȈႢ�͍��܂ł��m��Ȃ�������ł͂Ȃ��B�������A����͐g�������Ă�����������u�Ԃł������B�����́A��������������̑̌����A���ł͐V�����o�����o�����Ƃ����C���ł���B�������A�O�����Ȏp���ŊO���l�Ƃ̈Ⴂ�𑨂��邱�Ƃ́A���ɂƂ��āA�ƂĂ���Ȃ��Ƃ��ƔF�����Ă���B
��������̕ւ�
������������́A��؍q��̃X�`�����[�f�X���Ƃ߂Ȃ��爤�m������w�ɒʂ������A���̏t�A�����ɊO����w���p�Ċw�Ȃ𑲋Ƃ��܂����B���E�̊e�n����ޏ��������Ă����ւ���ȉ��Ɍf�ڂ��܂��B��y�̊F����ɂ��Гǂ�ł������������Ǝv���A�u���낵���v�z�[���y�[�W�ւ̌��J���������Ă��������܂����B
�Q�O�O�T�N�V���Q�P��
�����搶�A
�����́B�����������Ă���܂��B�����́A�����h������A���ĎQ��܂����B
�����h���Ƃ����ƁA7��7���ɋN�����e���̋L�����V�����Ǝv���܂��B���{�Ŏ��[�̂��j�����Ȃ���Ă������ɁA�ߌ����N�������Ǝv���ƁA�ƂĂ���肫��Ȃ��C�����ł��B
���́A�e������10���ȏ�o���Ă��烍���h���֍s�����킯�ł����A���݂̃����h���̓e���ȑO�Ƃ͕ς�����C�����܂����B���{�̔}�̂ŁA�u�C�M���X�͕����Ȃ������v�A�u���������v�Ƃ����L���i�j���[�Y�E�B�[�N���{�Łj��ǂ݂܂������A�l�X���ƂĂ����Ӑ[���Ȃ��Ă��邱�ƂɋC�t���܂����B�������R���w�Z�֗�����������A���傤�ǏI�Ǝ��Ԃł������A�قڑS���̗��e���q��������}���ɗ��Ă��܂����B�w�Z��������Ƃ������Ƃ́A�ܘ_�����ŁA�����e���d��������͂��Ȃ̂ɁA���ꂾ����R�̕������q������}���ɗ��Ă���Ƃ��������ƁA�F���Ƃ��Ă����Ӑ[���Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�����Ɏ����ŃV���b�N�����q������̐S�̏���������Ƃ���Ă���C�����܂����B���������A�Ƒ����T�ɂ��Ă������邱�Ƃ��A�����Ǝq������ɂ͈�Ԃ̎��ÂȂ̂��Ǝv���܂����B
�u�e���������܂��N���邩������Ȃ��v�A�Ƃ����b�肪���X���܂����A�q���̐S�ɏ��̂��������N���Ȃ���ƐɊ肤����ł��B
����ł́A�܂����ւ肵�܂��B���� ����
�Q�O�O�T�N�V���Q�R��
�����搶�A
����́A�؍��l�Ƃ̊ւ��ɂ��ď��������Ǝv���܂��B���݁A�u�ؗ��u�[���v�ƌ�����قǁA�؍��ւ̔o�D��h���}�A�f�悪�b��ɂȂ�A�ȑO���؍��ւ̗��s�҂��ƂĂ������A�����ɓn���đ؍݂���l���������Ȃ�܂����B�ł����A���̔��ʂŒ|�����A�ߋ��̗��j�F���̈Ⴂ�A�����_�Ђ̎Q�q���ɂ��ċc�_����邱�Ƃ����X����܂��B�����O�܂ŁA���{�̃e���r�A�V���ł́A�u�؍��Ŕ����f�����������B�v�u���{�̍������R�₳�ꂽ�B�v�u�����l�|���錾�t���f����ꂽ�B�v�ƁA�A���̂悤�ɕ���Ă��܂����B�����āA�G������́A�u���j�F���̈Ⴂ����A�؍��l�Ɠ��{�l�̃J�b�v��������Ⴄ�悤�ɂȂ��Ă��܂����iAERA���)�B�v�Ƃ����L�����ǂ݂܂����B
�����������L����ǂޓx�A���͉��x���������Ȃ��ł͂����܂���B�Ȃ��Ȃ�A���͏�Ɋ؍��l�Ɉ͂܂�Đ������Ă��钆�ŁA�L���œǂނ悤�ȍs�ׂ������Ƃ���x����������ł��B�{���ɖ����̂ł��B���{�l������Ƃ����č��ʂ����ꂽ���ƁA�ߋ��̗��j�ɂ��Đ�������ƌ���ꂽ���ƁA�ߋ��Ɋւ��ĕ��������ꂽ��A�������ꂽ���ƁA�ȂǂȂLj����܂���B����́A�������łȂ��A�ꏏ�ɓ����Ă��鑼�̓��{�l�ɑ��Ă����l�ł��B
���߂Ă������؍��l�̕��X�ɂ́A�������{�l���ƕ�����ƁA�u���{�l�Ȃ́H�v�Ɛ����|���A�m���Ă��錾�t���g���āA�킴�킴���{��ʼn�b�����Ă����l����R���܂��B
���́A�؍����j�����قւ������^��ł݂܂������A�ߏ�ȕ\�����������Ƃ͎v���܂���ł����B�i�����A���̗��j�����ق��ǂ��Ȃ��Ă���̂����m���߂�ׂ����Ǝv���܂��̂ŁA���̋@��ɍs���Č��悤�Ǝv���܂��B�j
���ꂩ��A�C�t�������Ƃł����A���͊؍��l�̓�������A�u���{�l�͊؍��l�������Ȃ�ł���H�v�Ɖ��x�������ꂽ���Ƃ�����܂��B
���{�l���A���f�B�A��ʂ��A�؍��ł̔����f��������ƁA�u�؍��l�͓��{�l�������Ă��Ȃ��̂��v�A�u�����Ă���̂��v�Ǝv����������܂���B����͂����A�����Ō������v���̋t�ŁA�o�����Ƃł������܂��傤���B����ȏ�Ԃ��Ǝv���܂��B�ł����A�����Ă����ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ăق����Ǝv���܂��B�ǂ�Ȃɍ��ƍ����A�ᔻ�������Ă��Ă��A����œ����Ă��鎄�����̒��ɍ��ʂ͂Ȃ��Ƃ������ƁB���ƍ��̑㖼���́u�����Ɛ����v�ł����āA�u�l�Ɛl�v�ł͂Ȃ��Ƃ������ƁB�l�͍�����̂��Ƃ������Ƃ��A�����Ȃ����Ɋ����܂��B
���������鎞�A�F�ዾ���|���Ȃ��ŁA�����̖ڂŌ��邱�Ƃ��n�߂����A����ɑ���s�M���́A���͎����̐S������ł���Ƃ������ƂɋC���t���邩���m��܂���B
����ł́A�C�t�������Ƃ�����܂�����A�܂����ւ�v���܂��ˁB�A���������������܂����A�ǂ������������������B���� ����
���Ƃ���
�@�V�C���N�ɂ��č��͖��J�B�ׂ̖������́A�\�z�O�ɐÂ��ł��B�����܌�墂��̂́A���j���̉w����ߕӂŃX�^�b�t��{�����e�B�A���o���A�u�Ǘ��̐��v�B�܂��Ƃɂ������܂����B�F�l�̌��q�p�́A�����f���ɏZ�݁A���C���J�ȗ��A���ӋK���������������u�h�Е������v����̉������u�����v�Ƃ��đi�������i��R�s�i�j�A�����炭����Ɠ���̌܌�墂�����Ȃ����낤���B�����ƁA���Ղ葛��������悢�̂ɂˁB���̂Ƃ���A�����́A����l�̎d��C���F���g�̈���o�Ă��Ȃ��悤�ł��B
�@��N���A������w�ɗ��w���Ă���}���[�i�E���}�G������́A���̂S�������w�@���m�ے��ɓ��w�����B���̎ʐ^�́A�S���T���A���w������̃X�i�b�v�ł��B

������@�}���[�i�E���}�G������A�����Z������A�[�c����q����
�i�NjL�j��L�̑�w�@���O�l�́A�V���X���i�y�j�E�P�O���i���j�ɍs��ꂽ������w��Â̍��ۊw���V���|�W�E���ő劈�����B��������́A���x�w�������C�^���A�ق̃A�e���_���g���Ƃ߂Ă��邪�A���債���_���u�Q�P���I��n��킽�������̉ۑ�v���ŗD�G�_���ɑI��A���_��p�l���[�Ƃ��Ēd��ɏオ�����B�}���[�i�́A����ڂ̃V���|�W�E���ŗ��w����\�p�l���X�g�Ƃ��Ĕ��������B�܂Ƃ߂̔����Łu�ٕ����Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����������ŋc�_���Ă��Ă���̏�̐����ł��B�ˊO�ɏo�āA���낢��Ǝ��ۂɃR�~���j�P�[�V���������܂��傤�v�Əq�ׂ��B�[�c����́A�{�����e�B�A�w���Ƃ��ďI�n�فX�Ɠ����Ă��ꂽ�B�X������͏��w�Z�ŋ�����K���ƌ����B
�V�w�����n�܂����Ǝv����������ċx�݂��B���͎������Ԓ��ł���B���V�A����Ƃ̓o�^�҂́A�������N�A������20�`25���A������10���]�A�㋉�i���p�j��5���O��ł���B���e�I�ɂ͑��ς�炸�v���ɔC���Ȃ��B�w���͂̌��E�������A���낢��ƕs�{�ӂȂ��Ƃ������B�������A���A���V�A��̏㋉�i���p�j�N���X�ɂ́A�ʔ����w���������Q�����Ă���B���낵������Ƃ��Ă��łɉ��N�����߂����Ă��镝���q����A�ɓ����q����̑��ɁA���L�V�R�̃��X�E�A�����J�X��w���痈�Ă���^�[�j�A�E�g�[���X�ƃh�C�c�̃P������w����̗��w���_�j�G���E�z�C�q���A�̓�l�ł���B�^�[�j�A�͂��������V�A���w�̈��D�҂ŁA���Ɂw�I�l�[�M���x�̃q���C���̖��O��t�����B��N�����V�A��̎��ƂɎQ���B���A���[���[�E���g�}���́u�v�[�V�L���_�v���ꏏ�ɓǂ�ł��邪�A�c�O�Ȃ���X���Ƀ��L�V�R�ɋA��B�_�j�G���́A����ׂ���w�̒B�l���B�S���ɏ������������ɂ́A���łɐ��m�ɓ��{���ǂ݁A�b�����Ƃ��o�����B�}���[�i�̏ꍇ�������ł��������A�O���ɂ�������{�ꋳ��̃��x���Ɋ��Q������Ȃ��B�����ׂ����͓��{��ȊO�ɑ�������C�����Ă��邱�Ƃł���B�t�����X��A�X�y�C����A����Ƀ��V�A��ł���B�ނ̃��V�A��̘N�Ǘ͂�lj�͕͂��͂���Ă��āA�V�����[�}����z��������B���̎ʐ^�́A�V��14���A�O���Ō�̃��V�A�ꉞ�p�̎��ƕ��i�ł���B���i�͈�ʂ̋����ł����Ȃ��̂����A�^�[�j�A�̑��ʉ�����˂āA�������ł��������݂Ȃ���̎��ƂƂȂ����B�i�����j�N�j

�E����^�[�j�A����A�ɓ����q����A�_�j�G������A�����q����A����
�@
�@�@
�u���낵�� ��v��� ��12��
�i2005�N�V��29�����s�j
���s
��480-1198
�w�����D-202�i��\�E�����ʔ��j
http://www.tosp.co.jp/i.asp?i=orosiya
���s�ӔC��
�����j�N�i
��480-1198