おろしゃ会会報第8号その2
拿捕、仲裁、オットセイ保護条約
(愛知県立大学外国語学部・共通)
19世紀後半、オットセイの毛皮は高値で売れ、その猟場であるベーリング海を中心に、北大西洋では英米露がきそって猟をおこなった。猟法は、陸上では撲殺、海上では銃殺、であった。生息数はみるみる減っていき、19世紀半ばに百万をもって数えたのが、20世紀初頭には一ケタすくなくなっていた。
オットセイのように、ひろく北太平洋を回遊する動物については、ある一地点でその捕獲を制限したとしても、別の季節、別の地点で捕獲ができるなら、制限は無意味となる。つまり、北太平洋全体で猟を制限しなければ実効はあがらない。そのうえ、公海上にはどの国も排他的管轄権がないから、責任があいまいになる。こうして、「共有地の悲劇」とよばれる問題が発生した。
もう商売にならないほど数が減った1911年、オットセイ保護条約がようやく、日、露、英、米でむすばれた。きわめて初期の多国間環境条約である。
日本にとって、この条約は何であったのか? 環境保護の誇るべき記録なのか? また、日露友好のしるしでもあるのか? 『大日本外交文書』をもとに、その経緯をおってみよう(もとにしたのは、第35巻、第41巻第1冊、第42巻第1冊、第2冊、第43巻第1冊、第44巻第1冊)。
生息数を増やすには、全関係国を拘束する合意がのぞましい。しかし、国家間の合意は口でいうほど容易でない。当時、国際法上、領海は海岸から3海里、というのが定説であったが、横行するカナダの猟船を取り締まるため、米国は3海里の外であっても拿捕する挙にうってでた。
カナダの宗主国であったイギリスは当然、これには不服であるから、フランス人がキャスティングポートをもつパリ仲裁に、英米は問題を付託した(1892年)。仲裁裁判所は公海の範囲について米国の説をしりぞけたものの、オットセイ猟の規則を作成し、英米ともそれを承認した。
しかし、英米の動きに恐怖をいだいた国があった。自国の島々に多数のオットセイが生息するロシアである。締めだされたカナダ船が周辺海域におしよせるのではないか、と危惧された。今度は、ロシアがカナダ船を拿捕することになった。あらたな紛争を予防するため、猟を制限する英露協定(1893年)がむすばれた。
同様の協定は米露間でもむすばれた(1894年)。実はこの数年前、米国船もロシア官憲は拿捕しており、その紛争は1900年にオランダの国際法学者T・M・C・アッセルの仲裁に付託されている。
しかし、オットセイの数は減りつづけた。あらたな枠組みがもとめられていた。米国の提案により、1897年には日露米で国際会議がひらかれた。決議ができたものの、イギリスの不加入で発効しなかった。このころまで、日本は参加に乗り気であった。
ところが20世紀にはいると、日本はいつのまにか海獣保護の「抵抗勢力」になっていた。はじめ猟にもっとも執着していたのはカナダであったが、1897年に遠洋漁業奨励法を制定した日本は、オットセイ猟をも国益伸張の対象としていた。国際的な流行に一足おくれて参加するというのは、捕鯨の場合と似ていないか。
そうした日本の態度に変更を迫ったのが、三重丸事件(1908年)であった。ロシアは英米との協定で露領コマンドルスキー諸島から30海里以内の猟を禁止し、拿捕の権利をあたえられていた。本来なら、無協定の日本船に両協定は適用できない。ところが、三重丸を領海3海里のそとであったにかかわらず、拿捕してしまった。同船は猟の現場をおさえられたわけでもなかった。さらに不幸なことに、連行するロシア兵に船員が抵抗したことから、6名が軍事法廷で死刑の判決を受けた。
結局、ロシアが拿捕について非をみとめ、また死刑判決を受けた者も特赦により釈放された。しかし、あらゆる機会に海外進出をはかろうとしていた日本は、冷や水を浴びせられた格好となった。三重丸も奨励金を給付されていたが、オットセイ猟への奨励金はこの直後、廃止された。その後は、米国が相次いで日本船を拿捕するようになった。
三重丸事件の翌年、かねてパリ仲裁等の規制に、実効的でない、と不満であった米国が、ふたたび国際会議をよびかけた。日英露の賛同を受け、1911年5月11日、ワシントンでオットセイ保護会議が開幕した。
米国ペースの交渉は、開会前に必至となった。実は英米間では、この年の2月に二国間条約が署名されており、すでに了解ができていた。国際会議をよびかけておいて、事前工作をすすめているのであるから、自由な討論も何もあったものでない。英米条約は公海での猟を禁止し、ほとんどを海上に依存する日本にとり不利な内容であった。会議前に明かされた米国案でも、海上禁止の原則はかわらなかった。日本委員は当初の訓令を捨て、すこしでも有利な英米条約を基礎とせざるをえなかった。ごねるほど、日本が悪者になる構図であった。
結局、海上での猟を断念する補償を、日本とイギリスがどれだけ米露から供与され、日英でどのようにそれを分配するか、が交渉の争点となった。ゼロ・サム・ゲームは決裂のふちをたどりながらも、7月7日、オットセイ保護条約の署名にこぎつけた。絶滅を瀬戸際で救った同条約は、改定を経て1980年代、失効することになる。
はじめの問いにもどろう。この条約は環境保護精神と日露友好の証といってよいのであろうか?
自国の国益を普遍的な理想として主張し、国際レジーム(体制)へと格上げするさまは、いかにも米国らしい。
隣国に甘い言葉はいっさいかけず、他国船を容赦なく拿捕するリアリズムは、いかにもロシアらしい。
強国の提案に抗しきれず、あきらかにしぶしぶと多国間条約に加入するというのは、いかにも日本らしい。
外交文化とは、かくも不変なものなのか? あるいは、海洋資源と領域紛争と軍事バランスを主要な争点とする北太平洋の地政学が、それを必然たらしめているのか? 悲観的な答えをだすまえに、もうすこし勉強しておきたい。
(後期のレポートみたいになってしまいました。これくらい書けていれば、Aあげます。)
「北方領土問題解決に向けて」
日本とロシアの間には北方領土問題が存在する。日本の北海道より北の島々とロシア東岸、カムチャッカ半島から南の諸島の間で、古くから国境線をどこに定めるかという交渉が行われた。この領土問題は、二国間の数々の戦争を含む歴史の痕跡であり、簡単に解決する問題ではない。だからこそ両国民はこの問題の歴史を知り、今後の解決に向けて相互理解を深めていく必要がある。以下に、領土の帰属を規定していた条約の流れを見て、北方領土問題がどうして起こったかを振り返る。そして最後にロシア大使館参事官の講演を元に、今後の解決の道を考える。
日本は、1951年のサンフランシスコ平和条約において、千島列島、樺太の一部及びそれに近接する諸島に対する権利を放棄している。問題の北方領土は千島列島に含まれていたのだろうか。1855年の日露通好条約を見てみると、日本とロシアの国境線は択捉島とウルップ島の間にあると定めている。つまり、現在の北方四島は日本に属していた。この時、樺太は両国人の雑居の地となっていた。1875年の条約では、日本は千島列島全島を領有し、ロシアは樺太を領有した。その後1905年のポーツマス講和条約で、日本は南樺太を譲与されている。過去において、北方四島の択捉島、国後島、色丹島、歯舞諸島がロシアの領有にあったことはなかった。
それでは北方領土問題はどうして起こったのだろうか。1941年、日本はアメリカやイギリスなどを中心とする連合国と戦争を開始した。同年、日本はソ連と日ソ中立条約を結び、両国は互いに領土の保全及び不可侵を尊重していた。しかし1945年2月の米英ソによるヤルタ協定において、南樺太の返還、千島列島の引き渡しを条件に、ソ連が対日参戦することを協定した。ソ連は日ソ中立条約を一方的に破り、同年8月18日にクリル諸島北端の占守島に上陸した。その後ソ連軍は千島列島を南下しウルップ島まで来たが、択捉島には上陸せず、一旦北に引き返した。ソ連がすぐに択捉島等に上陸して来なかったのは、北方四島が日本の領土であるとの認識があったからであろう。しかしアメリカ軍が北方四島に進駐していないことを知ったソ連軍は、再び南下し四島を占領した。このように、日本の領土である北方四島は日本が無条件降伏した三日後から、ソ連軍によって不法占拠されたままになっている。
このように見ると、明らかにソ連軍の横暴のように感じられる。しかし北方領土問題がこれだけ解決に時間のかかる難しい問題であるとすると、単にソ連側が悪いというだけでは済まない。領土を確定する時は条約などを通して法的に行う。過去の条約において、あいまいで不確かな規定があるのだろう。
吉田嗣延氏は著書『北方領土』において、ソ連軍の北方四島への上陸は「敵対行為の中止、交戦の停止と武装解除を主眼とするものであり、占領することが目的でなかったと解さねばならぬ。また、このような軍事占領が、そのままただちに領土権の変更をともなうような性格をもたないことはいうまでもない。」と述べている。1946年1月には「若干の外廓地域を政治上、行政上日本から分離することに関する覚書」が出て、千島列島、歯舞諸島、色丹島が日本から分離した。吉田氏はこれに関して、「これをもって領土権の転移をともなう領土の確定をみることはできない。」と書いている。つまり、これらの地域の法的地位は、連合国占領下の日本政府の行政の及ぶ範囲から除かれたことを示すにとどまる。ソ連軍は、吉田氏の言うように交戦停止と武装解除を目的としていたのかもしれないが、何故停戦協定後もずっとそれらの島にとどまったのだろうか。北方四島の所属が宙に浮いた状態で、ソ連軍も戦後の処理をうやむやにしてしまい、現在に至っているのではないか。また「千島列島、歯舞諸島、色丹島」と覚書にはあるが、択捉島と国後島は千島列島に含まれるのか。択捉、国後島は千島列島に含まれないはずであるのに、記述があいまいになっている。これらの不正確な記述がその後の日ソの交渉をややこしくしているのだろう。
吉田氏は、千島列島及び南樺太等の北方領土の法的地位を基本的に定めるものが、サンフランシスコ平和条約であると述べている。この平和条約にソ連は調印していない。もちろん放棄された地域を引き継ぐのはソ連ではない。平和条約は帰属先を指定していない為、連合国はそれらの地域の最終的帰属を決めるべきであるが、何の処置も行われていない。吉田氏は著書『北方領土』の中で、北方領土の法的地位について、過去の関連する条約、協定などと照らし合わせ、くわしく検証している。今まであいまいだった北方領土問題に対する概念が鮮明になり、日本の北方領土への権利主張が正当なものであることがよくわかった。
ソ連はヤルタ協定をよりどころにして、北方領土を領有し、一方的にそれらの地域をハバロフスク地方に編入している。国際法上、いかなる国も第三国の領域をその国の同意なしに処分することはできない。日ソ中立条約を一方的に破棄した上、密かに第三国の領土を動かそうとしていた協定など当然受け入れ難い。第一、なぜ色丹島、歯舞諸島まで占領されているのか。平和条約締結の五年後、アメリカ政府は対日覚書で次のように述べている。「エトロフ、クナシリ両島は、北海道の一部たる歯舞諸島および色丹島とともに、つねに固有の日本領土の一部をなしてきたものであり、かつ正当に日本国の主権下にあるものとして認めなければならないものであるとの結論に到達した。」1951年の平和条約の当事国であるアメリカが、こう述べているのだからソ連の行動は明らかに不当だと思うが、ソ連は決して譲らなかった。アメリカ等も極東の領土問題はあまり介入する程の事でもないと考えたのであろう。下手にどちらかの味方をして第三国が介入すると事態がより悪くなっていたかもしれない。しかし、アメリカ等戦勝国側も千島列島や北方四島の帰属をあいまいな形で処理せずに、最後まで責任を持つべきだと思う。
今まで見てきたように北方領土問題はデリケートで根の深い問題である。しかし一歩ずつではあるが、解決への道を歩んでいる。2000年9月のイルクーツク会談では、プーチン大統領が「平和条約の署名を条件に歯舞、色丹島を日本側に引き渡すという日ソ共同宣言の約束は自分にとっても義務だ」と語っている。ロシア大使館参事官のシェフチューク氏が述べていたように、領土問題を一気に解決するのは無理である。この問題はどちらが勝った、負けたを議論する為にあるのではなく、両国のより良い関係を築いていく為にある。それには両国民の支持が必要である。また、領土問題は日本とロシアが解決すべきであるが、両国は互いに世界にとって大きな影響力を持つ国であることを忘れずに広い視野で問題をとらえなければいけない。シェフチューク氏によると、現在両国間の経済関係は悪い状況にあり、日本でのロシア語、ロシア文学、経済に対する関心が薄くなっているそうだ。彼は、相手を知る為にも領土問題を解決する為にも、相手国の言葉を知らなくてはいけないと語っていた。確かに通訳を通さずに、直接交渉ができたら、より理解し合えるのではないだろうか。互いの国の言葉を進んで勉強しようとする人を増やす為にも、サハリン沖天然ガス・パイプラインの開発など両国の経済発展協力は欠かせないであろう。
【参考文献】
吉田嗣延、『北方領土』 時事通信社 1978年
和田春樹、『北方領土問題』 朝日新聞社 1999年
袴田茂樹、『沈みゆく大国---ロシアと日本の世紀末から---』
新潮社 1996年
ツルゲーネフ『ムムー』と現代ロシア文化の困難
昨秋、久しぶりで加藤史朗先生にお会いした。法政大学でひらかれた、JASSEES全国大会でのお話を拝聴しに伺ったのである。ロシア語教育の現状を述べられた先生の口ぶりは、きわめて厳しいものであった。
講演のあいまの会話で、イワン・ツルゲーネフの短編『ムムー』の話が出た。一昨年、私はこの作家について拙い修士論文を書いたのであった。『ムムー』を先生は授業で講読されたそうで、最近日本で公開された同名の映画化作品も話題に上った。
先生のご講演と『ムムー』をめぐり、あとから考えることがあった。ここに整理したい。
*
『ムムー』はツルゲーネフの初期を代表する短編で、1852年執筆、発表は54年である。当時、彼は『猟人日記』で文名を確立するとともに、所領に蟄居を命じられた身であったが、『ムムー』は『猟人日記』の諸作と同様、農奴の悲惨な境遇を描いていた。恋をした洗濯女とも、可愛がった子犬のムムーとも、女地主の気まぐれで引き裂かれてしまう聾唖のゲラシムは、苦汁をなめる農奴の象徴と捉えられてきた。
『ムムー』はソ連時代にも映画化されているが、上述の映画はユーリー・グルィモフ監督による1998年のもので、日本でも2000年に公開された。新版『ムムー』は原作に大胆な読みなおしを施し、ゲラシムと並置して、「悪役」の女地主に光を当てている。彼女の孤独と行き場のない欲望を前景化した解釈は、農奴の苦しみを訴えるツルゲーネフの小説の裏面で、独り身の老女を侮蔑的に描くというべつの差別がしばしば行われていたことを、正当に指摘している(『猟人日記』にも同形の短編がある)。
とはいえ、女地主がとりたてて同情的に描かれるわけではない。新版が示した解釈の重点は他にある。彼女にかぎらず、映画は全編にわたって、ゲラシムや洗濯女たちの欲望――性欲をスクリーン中にみなぎらせた。大きな胡瓜のピクルスに、女たちが男根よろしくかぶりつく場面などはあざといほどだ。映画は原作を、絡みあう欲望の物語として再提示したと言える。
『ムムー』を欲望が行きかう小説と読む試みには、実は近年に先行者がいる。哲学者のセルゲイ・ジモーヴェツは、1996年に『ゲラシムの沈黙』の表題で論文集を上梓した(『現代思想』1997年4月号に部分訳)。その第1章、彼は『ムムー』でゲラシムの欲望が変形を遂げる軌跡を、精神分析学を適用して読みこんでいる。簡単に紹介しよう。
彼によると、モスクワの地主屋敷へ来る以前、農村にいたころのゲラシムは「動物」的な状態にあり(『ムムー』の出だしでゲラシムは何度も動物に喩えられる)、その欲望は野性かつ自足的なものであった。聾唖はその象徴だ。だが、モスクワに来て、女地主の秩序に組みこまれた結果、彼の欲望も「人間」的なものに転じる。ゲラシムは他者――洗濯女のタチヤーナ――に欲望を覚えてそれを表現しようとし、恋が阻まれると、代わってムムーが彼の欲望とその表現を請け負った。しかしそれも女主人のため破局し、結末、ゲラシムは故郷に戻りふたたび動物として生きることになる。
グルィモフの映画とちがい、ジモーヴェツはゲラシムひとりの欲望に注目し、むしろ女地主は抽象化している。彼の眼目は、ゲラシムの欲望が課せられる変形を、ロシアで権力が作用する伝統的な構造と主張したことだ。すなわち、動物的な自然と人間的な秩序を接続し、前者を後者に変換、また後者を前者に還元しようとする作用に、ロシア文化の特徴があるという。それに即して『ゲラシムの沈黙』第1章では、他にミハイル・ブルガーコフの『犬の心臓』やパヴロフの実験が論じられた。
このように、『ムムー』をロシア文化がもつ欲望の構造全体のなかで捉えると、この作品自体、動物的に沈黙した民衆を、人間的な文学言語に接続しようという、ロシア作家の欲望の典型に思われる。『ムムー』では、ゲラシムの内面が直接に描かれることはほとんどない。タチヤーナやムムーへの彼の愛情は外側から読みとられるだけで、ゲラシムは作家が解釈し表現すべき対象である。
小説冒頭、ゲラシムはまず、見られる対象として読者のまえに現れる。「彼の手にかかると仕事はすいすい運び、彼が耕作し、大きな手のひらを鋤に押しつけて、どうやらひとりで馬の助けも借りず、大地のしなやかな胸を切りひらくところなどを見るのは楽しかった」。グルィモフの映画もこの場面から始まる。その際、農作業するゲラシムを映していたカメラが女地主に移ることで、ゲラシムを見ていたまなざしは女地主の主観ショットとして処理される。原作では語り手ないし読者のものであった視線を、欲望に満ちた女地主のものに転じるこの読みかえは、前者に潜む欲望を鋭敏に捉えていると言えよう。実際、『ムムー』原作では視線が欲望の媒体になっており、タチヤーナがゲラシムを恐れて「目を半ば閉じさえした」一方、ゲラシムは「彼女に見とれだし、とうとうまったく視線を外さなかった」。ムムーを川に沈め、彼の欲望が終わりを告げる瞬間、ゲラシムは目を閉じることで聴覚とともに視覚を遮断し、外界から完全に切断される。
*
こうした古典再解釈の作業には、ふたつの方向からの批判が予想される。
ひとつは読みこみの過剰さに対するもので、原典を歪めロシア文学の伝統を蹂躪することへの反発である。コマーシャル・フィルム界のスターというグルィモフの映像が、しばしば化粧品やハーゲンダッツ・アイスクリームのCMを彷彿させて上滑りぎみであることや、フランス哲学の術語をふんだんに駆使するジモーヴェツのスタイルが、この反発を加熱するだろう。
もうひとつは逆に、彼らのそうした欧米的スタイル(イメージにとどまる曖昧な「欧米」だが)が未熟だという意見である。たしかにグルィモフの映画は、古典の読みかえとしての面白さを除けば高い質をもつとは思われないし、動物(沈黙)と人間(言語)という二項対立を前提し、前者は後者に先立つ起源だと書くジモーヴェツの思考も問題含みである。映画に関しては、日本の配給会社が用意した公開時のビラにも、この作品への微妙な評価が表れている。ビラは子犬の写真を大きく載せていたが、実際には映画が半ば経過して以降、控えめに登場するにすぎない。しばらくまえにヒットしたロシア映画『こねこ』が配給会社の念頭にあったのかもしれないが、ゲラシムと女地主をめぐる主筋より、愛玩動物の可愛らしさが売りこみのポイントに選ばれたわけだ。
第一の批判に対しては、加藤先生がご講演で指摘されたことが思い出される。最近の学生がロシア文化に抱く興味は、電子楽器テルミン(ミュージシャンのコーネリアスが使用して話題になり、昨年には発明者のロシア人をめぐる映画も公開された)であったり、『チェブラーシカ』や『不思議惑星キン・ザ・ザ』といった映画であったりと多様だ。それらの学生たちは、19世紀リアリズム文学に代表される、従来のロシア文化とは無縁である。少なくとも、ロシア文化の受容が古典文学に中心化されていた時代は終わりつつあり、むしろその状況を積極的に活かすことに今後の可能性があるだろう。
伝統的なロシア文化自体にもそれは言える。研究者にとって、原典の厳密な読みが第一の課題となることはむろん変わりないが、それらがもつ意味を更新しアクチュアリティを発掘するためには、従来の文脈を離れた解釈は有効たりうる(好き勝手に解釈してよいということではない)。その結果、ある作家なり作品に照明が当てられ日本でおおいに読まれるが、それがロシアのものとは意識されない、といった状況があってもよいだろう。
とはいえ、現状はそう簡単ではない。新たに人気を呼ぶロシア文化にしても、それはロシアのものとして、あるいはロシアのものだから耳目を集めている場合が多い。たとえば『キン・ザ・ザ』はSFの優れたパロディーだが、配給会社が喧伝したほどのカルト映画ではなく、むしろハリウッド映画になじんだ観客にも、パロディーという枠内で受けいれやすいと思われる。にもかかわらず、『キン・ザ・ザ』がカルト映画として話題になったのは、それがソ連でつくられたという出自と抜きがたい関係があろう。他にも近年、ヴィターリー・カネフスキーやアレクサンドル・ソクーロフといった監督が日本で評価されたのは、欧米の映画文法では測れぬ特異性という、ロシア映画への期待と不可分である。ロシア文化はいまだ、ロシアという国へのエキゾチックな想像力に頼って流布する場合が多い。その想像力の根深さは、ロシア側の全面的協力のもと、赤の広場で初の大規模ロケを敢行したというハリウッド映画『セイント』にも表れていた。ロシアは陰謀と頑迷な民衆が蠢く未知の国として、明らかに見下して描かれる。
これは第二の批判にも関わる。ジモーヴェツをはじめ、90年代ロシアの言論界では欧米の思想をとりいれる動きが活発化し、文学を含んで「ポストモダン」が流行した(98年に私が留学したときは、毎月のようにフランスの哲学書の翻訳が出ていた)。また映画でも、ニキータ・ミハルコフの作品などは一種の「ハリウッド化」を見せている。ソ連色を払拭し、欧米的スタイルを身につけようという流れが、文学・映画・哲学といったハイ・カルチャーをも席巻したと言える。しかし、それが真に欧米にひらかれた試みで、実際欧米で評価されたかというと疑問符をつけざるをえない。いまさらポストモダンもないだろう、と嘲笑する向きもあろう。
だがそれら、欧米的になろうとしている(かに見える)ロシア文化が欧米や日本でかならずしも評価されないのは、単にその試みが未熟で遅れているからだろうか。ポイントはべつにあるように思われる。ロシアでポストモダンが叫ばれたのは、ソ連崩壊という凄まじい出来事と、それにつづく急激な社会変化への反応としてである。そして現実に、人々の暮らしは(特にモスクワで)まったく欧米化(資本主義化)されていったのだが、文学や哲学におけるポストモダンは、欧米化というより、欧米化していく現実の生活と、ソ連時代との整合性をつける試みであったというほうが適切ではないか。欧米の理論を学んだ批評家たちの関心は主にソ連文化に向けられ、ソ連はポストモダンであったといった主張まで生まれた。
そのため彼らの仕事は、欧米産の道具を使いつつも、しばしばロシア内向きのものになった。論述の対象だけの問題ではない。たとえば先述した、自然と言語を二項対立させるジモーヴェツの思考の特徴は、90年代、「文学中心主義」への対抗を標榜した批評家たちに共通していた。身体的な現実と、それを覆いかくす言語・文学といった二項対立がそこでは明瞭である。それは理論的にはともするとナイーヴに映りかねないが、体制を讃える報道や社会主義リアリズム文学の言語が流布する裏で、多くの人々が粛清で命を落とした時代への反省が要請したものだ。
このように最近のロシア文化は、欧米化を深めつつもロシアの歴史との対峙を避けられないでいる。従来のロシアを変形しつつ、ロシアという枠からは離れられないというジレンマがそこにはある。それは一方で、ミハルコフに顕著な、過去のロシアへのノスタルジーという方向にも転じえよう。昨秋日本でひらかれたシンポジウムでも、人気作家ボリス・アクーニンが書く革命前のロシアを舞台にした推理小説が、帝国への郷愁を孕んだものではないかと議論された(『早稲田文学』2002年3月号)。彼の小説の映画化が、ミハルコフとポール・ヴァーホーヴェン(『氷の微笑』で知られるハリウッドの監督)のふたりによりそれぞれ進行中だという話は、内向きと開放に引き裂かれたロシア文化の現状を、一見象徴している。しかし、海外でも上映されるだろうミハルコフの映画がロシア独自の価値を示威し、またヴァーホーヴェンの映画がロシアへのエキゾチシズムを露骨に誇示した結果、両者ともロシアの特殊性というものを前提しそれに依存する点で、図らずも相似た作品になる可能性はおおいにある。
*
いずれにせよ、ロシア文化は「ロシアの」という形容辞を変形しながらもそれに依拠する、という抗争をつづけることになるだろう。ここではごく第三者的に書いたが、それは日本におけるロシア文化の受容・研究やロシア語教育の今後とも関わる。私自身、その当事者としてなにごとかができればよいと思う。
ロシア映画“КИНО”向くままに(1)
カネフスキー監督『動くな、死ね、甦れ!』
(愛知県立大学文学部日本文化学科4年)
このところ数号にわたって、ロシア映画(ソ連時代の映画を含む)の批評を会報に書いてきた。もちろん、自分は偉そうなことが言えるほど多くの映画作品を観てきているわけではないので、あくまで大学でロシアをかじっている一学生からの視点、という前提でそれらを読んでいただければ結構である。今回も映画についてのエッセイに筆をとらせていただこうと思うのだが、毎度のことなので、いっそこの号から連載という形にしたい。タイトルは少々格好をつけて、その名も「ロシア映画“КИНО(気の)”向くままに」!
*
本作品『動くな、死ね、甦れ!』(1989年)は、愛知県立大学サークル「おろしゃ会」のお膝元では一度、昨年2月に名古屋シネマテークで上映されている。ちょうどアレクセイ・ゲルマン監督『フルスタリョフ、車を!』(1998年)の公開と重なっていたのが記憶に新しい。私自身は、ようやく今年1月に入ってから、行きつけのビデオレンタル店に置いてあるのを発見し、これはと思って借りた次第である。監督は53才でようやくこの作品が長編デビュー作となったヴィターリー・カネフスキー。ソ連・レンフィルムの制作となっている。
ソ連・ロシア版『少年時代』
タイトルの「動くな、死ね、甦れ」は、ロシア語で<замри-умри-воскресни>といい、これは彼の国にある「鬼ごっこ」のような子供の遊びの一つだそうである。決して物騒な映画ではないのでご安心いただきたい。そのタイトルが表すように、この物語は小学生が主人公であり、第二次世界大戦後の極東シベリアが舞台となっている。ロシア版『少年時代』とでもいったところか。
ストーリーは極東の貧しい町クーチャンの日常を描き出す。この町の炭鉱には労働地区、いわゆる強制労働収容所がある。主人公の少年ワレルカ(パーヴェル・ナザーロフ)は町に住む小学生、若い母親ニナと二人暮しで、父親はいない。母親はダンスホールで働いてはいるけれども、部屋に恋人の男性を連れ込むこともあって、息子のことはそっちのけ。近所の少女ガーリャだけが彼のことをかまってくれるのだ。イタズラ好きのワレルカは、ガーリャの近くに行っては邪魔ばかりしているが、おてんばの彼女には敵うはずもなく、いつも負けっぱなしである。ワレルカとガーリャはともに、まだ小学生である。初恋などという感情よりも、まずライバル心が先行してしまう。ガーリャに負けじと、ワレルカも彼女の後を追い、労働地区にポットを持ってせっせとお茶売りに行く。
お茶の代金のおつりが足りないときも、母親に大目玉を食らったときも、自分のスケートを盗まれたときも、助けてくれるのはいつもガーリャである。女の子にいじめられ、なおかつ助けられている主人公は、情けないけれども憎めない存在だ。彼はいつものイタズラの延長で、ある大事件を起こしてしまう。当然、純粋な子供心だけに罪悪感はものすごく大きいのだが、このときも彼女が救いの存在となる。
歌という記憶
物語は冒頭、<・・・極東の町クーチャンから来た>という歌詞の俗謡が流れるところから始まる。そして、BGMが皆無に等しい全般を通じて、どこで誰が歌ったのか分からないような民謡、俗謡がスクリーンを横切っていく。不思議なことにその歌の半分ほどは、何と「日本民謡」なのである。時代背景から自ずと理解できることだが、恐らくこれは日本人シベリア抑留者から聞こえてきたメロディーだったのであろう。劇中、主人公が抑留者のもとへ遊びに行く(というより、からかいに行く)シーンが登場する。日本人は兵隊服を着ていて、いつも頭をぺこぺこ下げている。幾分、日本兵を戯画化している面は否定できないが、ロシア人のその時代そこにあった「過去」というものを作品の中によく表しているといえよう。時おり<土佐の/高知の/はりまや橋で・・・よさこい/よさこい>と――と故郷への哀愁に満ちた歌声がスクリーンを横切り、他にも「五木の子守唄」や「炭鉱節」などがモノクロームの映像に挿入される。
『動くな、死ね、甦れ!』という映画は、少年期のワレルカ、その時代を生きた人々の回想録そのものなのだろう。またそれは、約60万人もの多くの日本人が抑留されたシベリアで、日本の民謡を耳にしていたというソ連人のпамять(記憶)なのだろう。この作品は物語の形を借りて、民衆の「記憶」を映し出している。歌は、映像とは異なる側面から作品を脚色し、音楽や台詞の効果を超えて、時代の空気をそのまま映画の中に再現するものだといっても過言ではない。
少女ガーリャはいったい誰?
ガーリャを演じるのはディナーラ・ドルカーロワという少女。そのキャラクターの強さから、スクリーンの中では名脇役というより主役に近い存在なのかもしれない。実は以前、成長後のドルカーロワの姿を別の映画で見たことがある。『ロシアン・ブラザー』で有名なアレクセイ・バラバーノフ監督の『フリークスも人間も』(1998年)で、リーザ役を演じているが彼女なのだ。整った美しい鼻は、幼い頃も今も変わりない。
もっともドルカーロワはデビュー以来、ヴィターリー・カネフスキーの映画で多く演じてきた。『動くな?』の他には、カンヌ国際映画祭「審査委員賞」受賞作品『ひとりで生きる』(1992年)や『僕ら20世紀の子供たち』(1994年)が代表作で、今日彼女はロシアでも有名な若手女優の一人に数えられている。外国映画にも活躍の場を広げる彼女は、現在フランスに在住しているとのことである。
50代の「新人」・カネフスキー
先にも述べたように、この作品は当時53才だったカネフスキーの長編デビューを飾ることになった。カンヌ国際映画祭では有望な新人に贈られる「カメラ・ドール賞」を受賞。「遅れてきた新人」といわざるを得ないのだが、それもそのはず、彼はここ十数年で脚光を浴びるようになったアレクサンドル・ソクーロフやアレクセイ・ゲルマンなどと同じ、言ってみれば「ペレストロイカ組」なのだ。
歴史的な「西欧への窓」・ペテルブルク(旧レニングラード)で培われたレンフィルムの伝統であろうか、そこで撮る監督たちはみな個性派ぞろいであり、カネフスキーもまた例外ではない。シベリアの貧しい炭鉱の町に住む少年の物語、という単純なストーリーなので、監督は一見素直に映画をつくっているようにも受け取れるのだが、必ずしもそうとはいえない面がある。例えば、ピンチから逃れたワレルカとガーリャが息を切らして一緒に大笑いしている場面では、明らかに二人以外に誰もいないにもかかわらず男性の笑い声が録音されているし、またストーリーの最後の展開にいたっては、どう考えても不明瞭な点が残るのである。「観客に媚びて映画を単純化しすぎない」という意味においては、これらの手法は十分評価することができるだろうが、どうもこのあたりの監督のスタンスで鑑賞者の好き嫌いが分かれるような気がする。
最後になったが、カネフスキーの作品中にあるキリスト教(ロシア正教)的な要素について少し触れておきたい。少年ワレルカが町中を歩いていると出くわす、労働地区から追い出された精神破綻者が、彼の顔をじっと見つめる場面がある。10秒以上もの間その男の顔がアップで映し出され、背景にどこからともなく鐘の音が鳴り響いてくる。これについて、ロシア正教で聖人と同一視されることがあった佯狂者<юродивый>に重ね合わせている、と解釈することは可能であろう。もしかすると、悪質なイタズラをする少年の小さな罪悪感を、<юродивый>が見つめていたのかも知れない。
(ひらいわたかひこ/学生会員)
風が吹くまま、気の向くまま、私は「わたし」と旅に出る
2月も終わりに差し掛かった頃、私のところに突然、ある一通の原稿依頼が舞い込んで来た。大親友(心友?)・鈴木夏子さんが所属している「おろしゃ会」の会報に原稿を載せてみない?というもので、最初は、「ロシアとは縁もゆかりもない私、何について書いたらいいの?」と、返事を渋っていたのだが、「ロシアに関係していることじゃなくてもいいから!」と言われ、これも何かの縁かな、と思い、お引き受けすることにした。ただ、いくら「ロシアに限定したテーマじゃなくてもいいから!」というお言葉を頂戴しているとはいえ、「おろしゃ会」の会報に載せようとしている原稿に、ロシアのロの字も出さない訳にはいかないので、まずは「私とロシア」について、少し書いてみることにする。
「私とロシア」。はっきり言って、鈴木夏子さんと知り合うまでは、私のロシアに関する知識は皆無といっても過言ではなかったし、そもそも、ロシアという言葉を耳にしても、「だからどうしたの?」という感じで、それ以上の好奇心を駆り立てられることもなかったように思う。それが、彼女に連れられて「おろしゃ会」の部室や加藤先生の研究室、それに「おろしゃ会」主催のロシア映画上映会に度々顔を出すようになり、彼らの人柄もあったのだろう、「この人たちをここまで魅了するロシアって、どんな国なのかな?」と、少しずつではあるけれど、ロシアについて、私なりにアンテナを張るようになり、今では「何処どこでロシア映画が公開されるよ!」と聞けば、張り切って観に行くようになったし、『チェブラーシカ』に出てくるワニのゲーナのことが大好きで、自身のことも「ミノーシュカ」なんて呼んでいたりする(笑)のだから、人と人が出会うって、本当におもしろいと思うし、せっかくここで、ロシアの深さ、おもしろさの、ほんの氷山の一角を垣間見せてもらったのだから、ここからどんどん掘り下げていって、いつかは「シベリア鉄道に乗って、シベリア大陸横断(途中、キヨスクでチェブラーシカのお人形を購入)」なんてこともやってのけたいなあと、水面下で密かに企んでいる今日この頃である。
さてさて。ちょうどシベリア大陸横断の話が出たところだし、そろそろ本題へと移ることに致しましょう。
加藤先生や「おろしゃ会」のメンバーがロシアをこよなく愛しているように、私にもやはり愛し、大切にしているものがあって、それは映画、サッカー、そして旅。せっかく今回、いろいろな人々の目に私の文章が触れる機会を頂いたのだから、私という人間を形成するうえで多大なる影響を与え、そしてこれからも間違いなく与え続けるであろう「私の旅」について、少し書いてみようと思う。
いつ、そう思うようになったのかは解らないが、おそらく物心ついた時から「旅をした人になりたい」と、漠然と思っていた。「青年は荒野を目指す」という言葉は、いつの時代も私にとって、クラーク博士の「少年よ、大志を抱け」なんて格言よりも余程リアリティがあったし、ある時ふっと現れる、何処から来るとも知れない私の「旅に出たい」願望も、何故ってそれは「青年は荒野を目指す」ものだからよ、と、そう信じて疑わなかった。
私がここで言う「旅」とは、スケジュールでがんじがらめになる、いわゆるツアー旅行ではなく、その昔、沢木耕太郎が乗合いバスでユーラシア大陸を駆け抜けたような、そんな、地球の大きさを自らが踏みしめて歩くことで体感する、けれど何処まで行っても先の見えない「旅」のことだ。これまで何度か旅に出て、数ヶ国を渡り歩いてきたけれど、基本的に私の旅はいつも一人。往復の航空券だけ取ったら、バックパック一つとパスポートを片手に、帰国の日だけはしっかり確認して、あとは大した計画も立てないで、ひょいっと行ってしまう(友達曰く、「風と共に去りぬ」…?)、そんな旅だ。旅に出たら極力、そこにあるものをそのまま見て、そのまま受け止めて、それで自分がどう感じるかを大切にしたいので、現地に着いて、そこの空気を吸い込むまでは、何の予備知識も入れない、何も決めない、考えない。空港のタラップに足を下ろした瞬間から、私の旅は始まるのだ。
私は、旅に関しては(というより、これは人生全般に言えることかもしれないのだが)自分の直感を信じているので、自分が「呼ばれている!」と思ったところ、その時の自分が「行きたい!」と思ったところには、できるだけその時に行くようにしている。そこには、その時の自分にしか感じられないものが必ずや存在するはずで、それはその時に行って、その時の「等身大の自分」が感じなければならない、唯一無二のもの、という気がしてならないからだ。
よく人に、「一人旅なんて、退屈しないの?」と訊かれるが、私にとっての旅とは、「一人になりにいく」ものなので、それは確かに、美しい景色や美味しいお料理を前にして、「一人占めしちゃうのはもったいないから、誰かを連れて来てあげたい」と思うことはあっても、一人で旅を続けること事体には、一抹の寂しさも感じない。何故って、私の旅は「一人になりにいく」ものであると同時に、「誰かに会いに行く」ものでもあるからだ。誰しもが独自の旅のスタイルを持っていて(それはつまり、各自が独自の価値観を持っているってことだろう)、旅をしていて何に重きを置くか、それは個々の自由であると私は思う。ただ、それが私の場合は、そこに暮らす、あるいはそこを傍観者として通過していく、そんな人々との「出会い」なのだ。
「 旅をしていていつも思うのは、その土地の風景を自分のものにするために、そこで誰
かと出会わなければならないことだ。もしそうでなければ、風景は映画のスクリーン
をただ眺めているように、決して自分自身と本当に言葉を交わさない。そして旅をす
ればするほど世界はただ狭くなってくるだろう。けれども誰かと出会い、その人間を
好きになった時、風景は初めて広がりと深さを持ってくる
」(出典先不明)
上に書いたものは、私がとても大切にしている言葉の一つ。旅に出る時はいつも、忘れないように忘れないように、手帳の切れ端に、パスポートナンバーと一緒に書き留めておく。そうして、旅を続けている間、それを片時も離さず、何度も自分に言い聞かせる。
これはもう、声を大にして言ってしまうことなのだが、私は旅に出れば出るほど、自分が持って生まれた「旅運」というものに感謝せずにはいられない。というのも、私はいつも旅先で、それはそれは素敵な人たちと出会えているし、その人たちのことを本当に好きになれたおかげで、そこに吹く風も、私の目を通して見えてくる景色も、アジア独特の喧騒も、全てが愛しく、それこそ、ただ平坦なものとしてではなく、「広がりと深さ」を持って、きちんと自分の中に落とすことができているからだ。私は旅に出る度に、「今目にしているこの風景、彼らの微笑みを、何がなんでも忘れないでおこう」と思うが、それは、とっても真摯で、強くて、祈るような気持ちにも似ていると思う。
私が「旅に出たい」と強く思う時、そこには概ね、ちょっと目を逸らしてしまいたくなるような「過酷な現実」があって、だから時折、旅という、非日常的空間に入り込むことで、そこから逃げるように、「ここではないどこか」を目指す。そこには希望がある(かもしれない)、と信じて。けれど、旅に出る前と出た後で、何か目に見えるほど、人間って変わるものではないと思う。日本に帰ってみたところで、「過酷な現実」が拭い去られている訳でも、残念ながら、ない。それでも私は、旅に出る。そしてこれからも旅に魅せられた一人として、旅を続けていくことだろう。
「旅」は、「そこにいること」以外、自分の名前も、職業も、国籍も、一瞬にして意味を持たなくなってしまう。だから、大好きだ。誰も自分のことを知っている人がいない土地で、別な時間の流れに身を置いて、自分のことを解き放っていると、「ああ、自分はこれからも、どんなことだってできるし、まだまだ何にだってなれるんだなあ」と、いつも思うもの。広いアジアの中にいると、ちっぽけな日本で、ちっぽけな物差しでしか物事を計っていなかった、ちっぽけな自分というものも、少しは見えてくるし。「世界はこんなに狭く(「行こう!」という、その気持ち一つあれば、いつ、何処にでも行けるんだ、ということ)、でも、こんなにも広く、深く、大きいのだから」と、自分に言い聞かせてあげることができたら、きっと私は、(少なくとも見た目には)背筋をしゃんと伸ばして歩いていけるんじゃないかな?と、そんな気にさえさせてくれる。そう、旅って結局は、日常という「終わりのない旅」へと再出発するための、ちょっとした逃避行でしかないのかもしれない。
私は映画とサッカーと旅をこよなく愛しているので、これからもそのように生きていくしかないだろう。だからこそ、「旅馴れた人」になるのではなくて、心を未知のものに向かって開き、見るもの聞くもの感じるもの全てを写す曇りのない鏡を持って、「そこに行ってきた」と、あっさり言えてしまうような、そんな旅をしたいと思う。
おそらくこの会報が出る頃には、私は私のことを待っていてくれる、まだ見ぬ世界、まだ知らぬ人々を、この目で、この耳で、この心で感じるべく、次の旅に出ているはず。その旅のお話はまた、別の機会に…。
最後に一言。加藤先生、そして「おろしゃ会」のみなさん、私を摩訶不思議で、とっても奥の深?いロシアン・ワールドへと誘って下さって、本当にありがとうございます。今年の6月に開催されるサッカーW杯予選「日本対ロシア」、ピロシキでも食べながら、ウォッカ片手に、一緒に観戦しましょうね!
ワニのゲーナとお友達になりたいミノーシュカより、愛を込めて。
Здравствуйте!
Меня зовут Марина Ломаева,
я студентка японо-английского отделения
факультета современных иностранных языков
Красноярского государственного университета.
Сейчас я учусь на четвертом курсе и мечтаю
поскорее закончить университет ? не потому,
что я уже все знаю, а потому, что уже определила
для себя, чем бы мне хотелось заниматься,
а российская система обучения, к сожалению,
не позволяет делать выбор.
Вот именно о выборе мне бы и хотелось
поговорить. Я стала тем, чем являюсь сейчас,
благодаря тем выборам, которые мне пришлось
совершить. Я считаю, что родилась в эпоху,
девизом которой мог бы стать лозунг: 《Делайте
ваш выбор》. 《Ваш》, а не 《правильный》,что
отличает его от решений, предлагавшихся
раньше тоталитарной системой, а теперь
《экспертами》и знаменитостями в рекламных
роликах.
Мои родители-геологи совершили
первый значимый для меня и во многом определивший
мой характер выбор, когда переехали в поселок
Бор Туруханского района, находившийся
в сердце тайги. Если что-то и может вселить
в наши души патриотизм в настоящее время,
то это воспоминания детства. Я не помнила
грязных городских стен, меня не прятали
с детства в бетонную камеру, называемую
городской квартирой. Я помню простор, сосны-великаны,
которые росли у нас во дворе, маленькие
открытия, которые я совершала каждый день,
играя в траве (она росла скудными пучками
на песчаной почве) или на берегу реки. Я
летала с родителями на вертолете, восторженно
глядя на расстилавшийся внизу темно-зеленый
ковер соснового бора, болот, крохотных
озерец. А на выходных или во время родительского
отпуска мы рассекали по Енисею на моторной
лодке, поднимая тучи брызг кристально чистой
воды.
В выборе номер два я уже принимала
символическое участие −мы переехали в
самый северный крупный город Заполярья
− Норильск. Я не могла не замечать ужасной
экологической обстановки в этом городе,
но в памяти осталась и романтика Севера,
пестрые национальные костюмы долган −
племен, издревле живших на этой территории.
В этом городе пронизывающих ветров, городе,
основанном политзаключенными во времена
сталинских репрессий, живут мужественные
люди, ученые, творцы. Я получила там прекрасное
школьное образование и сделала очередной
выбор в пользу чтения и ленинского девиза
《учиться, учиться и учиться》. Там я, по рекомендации
родителей, решила не вступать в ряды пионеров
(сама идея была уже безнадежно развенчана),
большей частью из детского бунтарства
и любопытства. И впоследствии я нередко
выбирала стезю аутсайдера, путь против
течения, потому что иначе невозможен никакой
прогресс. Я не верю в светлое будущее, к
которому можно прийти, построившись стройными
безликими рядами.
Я выбрала изучение иностранных языков
уже здесь, в Красноярске, учась в старших
классах. Я задыхалась в одиночестве, в духовном
вакууме математического класса. Никогда
не забуду атмосферу фальши, попытки навязать
нам определенный образ мышления:
We don’t need …no thoughts control…
Teacher, leave them kids alone!
(Это тоже наследие советской школы −
сейчас многие пытаются
ее идеализировать, и это меня пугает.)
Английский язык стал для меня
дорогой к свободе, дорогой в загадочный
непознанный мир. Но эта дорога в конце концов
привела меня на японское отделение, и я
почувствовала, что уже не хочу идти дальше
в поисках неведомого− пора сделать привал
и начать осваивать этот безбрежный континент.
Я воткнула палку в песок и построила шалаш
на берегу. Моей первой встречей с аборигенами
была волонтерская работа с одногруппником
на Чемпионате мира по лыжному ориентированию,
проводимом в Красноярске. Японская команда
восхищалась нашей дерзостью и мужеством
−мы пытались познакомить их с разными сторонами
жизни нашего города, располагая словарным
запасом в тысячу слов и несколькими грамматическими
конструкциями. Мы же были абсолютно счастливы.
С тех пор я жила от одного чемпионата (вольная
борьба, хоккей, самбо− я никогда и представить
не могла, что меня будет интересовать спорт!)
до другого, от одного приезда делегации
или гастролей японского дирижера до следующего.
Как я уже говорила, я сделала выбор
в пользу изучения иностранных языков потому,
что мне хотелось находиться среди людей,
хотелось заботиться о людях, помогать им,
чувствовать их понимание и симпатию, иногда
переходившую в настоящую привязанность,
дружбу. Единственный момент, когда мне
очень не хотелось, чтобы они видели меня,
это момент расставания ? красные заплаканные
глаза, чувство опустошенности отчаявшегося
Робинзона, провожающего глазами корабль,
исчезающий на горизонте.
И вот недавно я сделала еще один
выбор: я решила, что не
хочу больше чувствовать себя рыбешкой,
выкинутой на раскаленный песок, −я хочу
жить и работать в этой атмосфере уже в качестве
профессионала. Я мечтаю о том, что порочные
мифы и зловещие призраки прошлого, разделяющие
наши народы, исчезнут ? я собираюсь приложить
все усилия к этому. Я знаю, что, делая
свой выбор, должна рассчитывать только
на свои силы и упорство, но бесстрастная,
слепая судьба тоже иногда преподносит
сюрпризы и подарки. Одним из таких подарков
было знакомство с профессором русской
истории Като Сиро, ставшим моим первым−настоящим!
−учителем, моим 《духовным наставником》,
моей путеводной звездой. Я не знаю, как
благодарить небо, за то, что он тоже сделал
выбор поддерживать связь с этой красноярской
студенткой, имя которым легион. Я надеюсь,
что мои пути с ним и с Японией, на чей дикий
и неизведанный берег я когда-то высадилась,
не разойдутся. Я совершаю этот выбор.


2001年8月16日 2001年8月17日 クラスノヤルスク大学にて
こんにちは!
(クラスノヤルスク国立大学現代外国語学部4年)
私はマリーナ・ロマーエワといいます。クラスノヤルスク国立大学現代外国語学部日本語・英語学科の学生です。今は4年生で、早く大学を卒業したいと思っています――それはもうすべてを学んだからではなく、何を勉強したいかがはっきりしていても、残念ながらロシアの教育制度が選択を許容しないからです。
ここでは、その「選択」についてお話できればと思います。私が今の私となったのはかつてせざるを得なかった選択のおかげです。私は「自分の選択をしなさい」ということがモットーとなり得る時代に生まれたのだと思います。「正しい(選択)」ではなく、「自分の(選択)」というのは、かつては全体主義的なシステムが促し、今日においては「専門家」やコマーシャルの有名人が求めているものとは一味違うものです。
私の両親は二人とも地質学者ですが、私にとって重要性をもち、多くにおいて私の性格を規定している一つめの選択をしました。当時、タイガの「心臓部」に位置している、トゥルハンスク地区のボル(松林)・ニュータウンに移り住んだのです。今日において、私たちの心に愛国心を抱かせるものがあるとすれば、それは子供時代の記憶でしょう。私は都市の汚れた壁を憶えておらず、幼い頃から都市住宅という名の「コンクリートの部屋」に閉じ込められたことはありません。私が憶えているのは、広々とした大地、家の庭にそびえていた巨大な松、そして草地(砂質土壌に疎らな束となって生えていました)や川岸で遊びながらの毎日の小さな発見、といったものです。私は両親と一緒にヘリコプターに乗って空を飛び、眼下に広がる針葉樹林、沼地、小さな湖が織りなす深緑のカーペットを有頂天になって眺めました。休日や親の休暇がとれたときには、モーターボートで清冽な水しぶきを上げながら、エニセイ川を駆けぬけました。
二つめの選択に、私は象徴的な意味ではすでに関わっていました。私たち家族が北極圏の大都市・ノリリスクに引っ越したのです。この街の公害のひどさを感じずにはいられませんでしたが、それでも記憶には北方のロマン――この領域に昔から住んでいる種族・ドルガンのまだら模様の民族衣装――が残っています。寒風が身にしみる、スターリン弾圧時代に「政治犯」によって礎がすえられたこの都市は、勇敢な人々、学者、作家の街だと思います。私はそこですばらしい学校教育を受け、読書に励むなど、レーニンのスローガン「学べ、学べ、もっと学べ」にしたがい、ごく普通の日々を過ごしてきました。この街では、両親の勧めもあって、ピオネール(その理念はすでに地に堕ちていました)には入らないことに決めました。とはいえ、実情は子供の反抗心と好奇心からでした。後になってからも私が幾度となくアウトサイダーの道、流れに逆らう道を選んだのは、そうでなければいかなる進展も不可能であったからです。整然とした個性のない隊列によって未来がつくられるとすれば、私は進むべき輝かしい未来というものを信じません。
私が外国語を学ぶことを選択したのは、クラスノヤルスクに引っ越して、高校に入ったときのことです。数学のクラスの孤独さや精神的な真空状態に息苦しくなっていたからです。私たちの思考に決まった型を押しつけてくる欺瞞的な雰囲気は、決して忘れることはないでしょう――思想統制はもういらない。教師よ、子供たちを放っておいて!
(これもまたソヴィエト時代の学校の遺産です。いまでも多くの人が美化しようをしていますが、これには驚かされます。)
私にとって英語は自由への道、謎めいた見知らぬ世界への道となりました。しかし結局のところ、この道が私を日本という分野へ導くこととなり、もう未知の発見にはこれ以上進みたくない、今は立ち止まりこの際限ない大陸を理解しはじめるときである、と感じるようになりました。私は砂地に棒をさし込み、ひとまず岸に掘立小屋を建てたのです。私の最初の「先住民」との出会いは、クラスノヤルスクで行われたクロスカントリー・スキー世界選手権での、ある仲間とのボランティア活動でした。日本選手団は私たちの大胆不敵さに感嘆しました。私たちは一千の語彙といくつかの文法構造を駆使して、彼らに街の生活の多様な側面を知ってもらえるよう試みたのです。これはまったく幸いなことでした。このときから私は、次から次へと、選手権大会(フリースタイル・レスリング、アイスホッケー、サンボなど、自分がスポーツに興味をもつことになるとは思ってもみませんでした)、代表団の来訪、また日本の指揮者の公演での通訳を経験してきました。
すでに述べたように、私は外国語を学ぶという選択をしました。それは人々の中に入って、気を配り、お手伝いをし、彼らへの理解と、ときに本物の愛情である「友情」につながる共感を得たいと思ったからです。人々が私に目を向けてほしくない唯一の瞬間、それは別れ――泣きはらした赤い目、水平線に消えていく船を見送りながら絶望するロビンソン・クルーソーような無力感――のときです。
そして最近、もう一つの選択をしました。私は自分を熱砂に打ち上げられた小魚のように感じるのはうんざりしており、この世界の中でプロフェッショナルとしてやっていくことに決めたのです。国民を分断している、不道徳な神話や過去の亡霊が消えてなくなることを私は望んでおり、そのためにすべての力を捧げることにしました。私が選択をする中で知ったのは、自分の力や根気だけを頼りとするのは当然ですが、ときに思いがけない贈り物をくれる寂静にして不可思議の運命もあるのだ、ということです。そのような贈り物の一つが、ロシア史の教授である加藤史朗先生との出会いでした。私にとって先生は、最初の「本当の」先生であり、「心の教師」であり、導きの星です。また加藤先生が、無数にいる学生の中からこのクラスノヤルスクの女子学生とのつながりを支持するという選択をしてくださったことに対しては、感謝のしようがありません。加藤先生や日本とともに歩んでいく道は、たとえ未開で前人未踏の岸に上陸してしまうものであっても、一本道であり続けることでしょう。私はこの選択をやり遂げるのです。
イルクーツク紀行
(クラスノヤルスク国立大学現代外国語学部)
加藤史朗先生 3月28日(20時)
御無沙汰しております。今頃日本は年度末年度始めで、忙しい頃だ、と思い出しています。
でも、ロシアでは忙しいと言うことはまるっきりありません。自分のためや、仕事のために、仕事をするのではなく、稼いだお金で大型休暇を過ごすために働くのがロシア人です。(最近では、そうでもなくなってきましたが)。
私も、週20時間の授業の他は拘束されません。
3月中ごろ、1週間ほど、クラスノヤルスク大学を留守にして、イルクーツクへいってきました。私の出身地の石川県ロシア協会の依頼で行ってきたのですが、出発前に学部長に「イルクーツクに1週間ほど行ってきます」とひとこと言い、「どうぞ」とひとこと許可をもらい、行ってきました。その間私の授業は休みになりました。
イルクーツク紀行文を書いてみました。もしお時間があったら読んでみて下さい。
イルクーツクまではシベリア鉄道で18時間ほどでいけます。ウラジオストックまで4日間半もかかるのに比べて、あっと言う間の距離です。それで、コンパートメントの寝台車ではなく「大部屋」の寝台車のチケットを買いました。チケットには列車の出発は、モスクワ時間、3月11日20時40分と書いてあり、時間的にもまずまずでした。クラスノヤルスク時間0時40分(モスクワとの時差が、つまり4時間)に間に合うよう駅に行って初めて分かったことですが、それはウズベキスタンの首都タシケントからイルクーツクへ向かう「国際列車」でした。ウズベキスタンは昔はソ連構成15共和国の1つで、ソ連崩壊後も、ロシアとよい関係にありますが、一応、外国です。ロシア人や、ウズベキスタン人はビザ無しで行き来ができます。
タシケントの列車はきれいではないと言うことは知っていました。でも、ここまでとは思いませんでした。列車と言えば交通機関だと思っていましたが、タシケント発の列車は、その常識を覆すものでした。普通は寝台車の寝台は「一人の人」が「寝るため」にあるのですが、この列車は違います。
クラスノヤルスクにその列車が到着したのは夜中でした。中に入ると、1つの寝台に何人もの人が座っていたり、1つの寝台に2人の大人が寝ていたり、ただ、大きな荷物が乗っていたりしました。
確かなことは、寝台の数より乗客の数がはるかに多いということです。私のチケットには、もちろん寝台の番号が書いてありすが、すでに、ウズベク人女性が2人占領していました。3人で寝るということもあり得ます。列車が発車して暫くして、ぽっちゃりしたウズベク人の車掌が来ましたので、「この寝台は、私ので、ほらここにちゃんと番号が書いてあるでしょう、この人たちに退くように言って下さい」と頼みましたが、思っていた通り、そのウズべク人女性は、「私は、タシケント出発からずっとここにいるのよ。」と知らん顔。丸顔ウズベク人の車掌も「チケットはチケット。ここでは別の決まりがあって、すべては車掌が決めるのです。あなたは、こちらの方で寝て下さい」と少し離れた上段の寝台をさしました。そこにはウズベク人のおじさんが熟睡しています。「今この人を起こして退かしますから。」と言われました。その上段でもよかったのですが、でも、私のチケットの番号は下段です。下段ですと寝台の下に、オーバーや自分の荷物を置けますが、上段ですと、置くところもありません。下段の方がずっと便利です。それで、「いいえ、それでは、困ります。」と食い下がりました。「私はわざわざ下段を買ったのです。上段に寝るのは怖いのです。1度落ちたことがありますから」と、実はデタラメを言いました。何でも口実があればいいのです。「落ちるから、私は絶対に上段にはいかないわ。ここが私の場所なんだから、他の人を退かしてちょうだい」と、もう喧嘩腰で言いました。すると驚いたことに、そのウズベク人車掌はあっさりと承知して、私の寝台を占領していた女性を退かしてくれました。
そのせいかどうか、シーツ代として、普通の値段の3倍(200円)も請求されました。ウズベク人乗客は70円くらいでシーツをもらっています。でも、130円で、事がおさまったったとすれば安いものです。丸顔さんも少し儲かったことですし。
その夜、上にも下にも横にもぎっしりと置かれているウズベク人の荷物が落ちてこないかと心配しながら、何とか寝ました。
次の日は、寝台の上にもテーブルにも、市場の売り台のように、いろいろの商品が並びました。駅につくと、大きな鞄を持ったバイヤーが乗り込んできて、それら商品を卸値で買っていきます。停車時間が20分30分の大きな駅ではウズベク人が、プラットホームに自分の商品を並べます。列車の移動中、他の車両からバイヤーが来て、買っていきます。バイヤーが通る度に、私の向いのウズベク女性が「女性用下着はいかが?」「綿の部屋着は、安いよ」「この靴下はいい品質だよ」と声をかけています。なるほど、上段では商売がしにくいです。寝台に並び切らない商品はヒモに吊るしてぶら下げてあります。ウズベクは物価が安いので、それを持てるだけって列車に乗り、4、5日かけてイルクーツクヘ行く途中で売り捌き、そのお金で、イルクーツクでは安いがウズベクでは高いと言う物(例えば、チョコレート、ビスケットと言ってました)を買って、同じ列車で、戻って来るのです。 夏、ウズべックなど中央アジアでは果物や野菜が安いので、それを大量に北国ロシアに運びます。バイヤーではない一般のロシア人でさえ、中央アジアから列車が着く頃(通過する頃)、駅のプラットホームに行って直接、安く買ったりします。
昨夜は、私が「寝台を明け渡せ」だの、「荷物を退かせ」だのと喧嘩腰で話していたウズベク人達でしたが、実はみんな愛想のいい人たちで、目があえばにっこり微笑んでくれます。お互いにはウズベク語で話していますが、わたしとは、ロシア語で話しました。
ウズベキスタンはイスラム教の国ですから、一夫多妻です。妻達は夫の家で一緒に暮らし、2人ほど妻があるのが一般的だそうです。彼女の夫は失業中なので、妻は(一応)一人しかありません。ウズベキスタンでは多くの工場が倒産状態で失業者が多く、この列車のほとんどの乗客のように、個人的な国境貿易(買った=売ったの運び屋)やっているそうです。最近、国境の税関が厳しくなったので、需要は大きいが税率の高い果物などは避けて、衣料品を中心に運んでいるそうです。途中通過するカザフスタンで、安い中国製の衣料品を買い足すのだそうです。失業中の夫がこの「運び屋」をやらないで、女性がやるのは、その方が税関を通りやすいからだそうです。泣いたり、叫んだりすれば、少しぐらいの違反には目をつむってくれるとか。なるほど、車両内のウズベク人は半分以上が女性です。わずかな男性は上段で寝ています。
一人のウズベク人男性が起きてきて、私に、「日本人はぶたを食べるか。」と聞きました。「もちろん食べる。」と答えましたが、すぐ、イスラム教徒の人たちは、ぶたは不浄な動物なので食べないのだと思い出しました。(彼は日本人にぶたを売って、日本の優秀な電気製品を買いたいのだそうです)。「ぶたを食べるウズベク人もいるのよ。私は絶対に食べないけどね」と先ほどの女性が顔をしかめながら言ってました。
知り合いになったのですから、彼等の安い綿製品も少し買いました。せっかくですから、首都タシケントや、古都ブハラ、サマルカンド、コーカンドのこと、征服者チムールのこと、ついでに、ウズベク語も少し教えてもらいました。中央アジアの国々は治安が悪いと報道されていますが、普通の住民にとっては日常生活に特に危険もないようです。まあ、当たり前のことですが。 タシケント発イルクーツク行き列車は、そんなわけで、ロシア人はめったに交通機関として利用しません。時々、やむなく乗り合わせるはめになったロシア人は、あきらめて、小さくなって上段に寝ています。
夕方遅くなってイルクーツクに着いた時、ほとんどのウズベク人は降りようとしませんでした。もうイルクーツクの卸売り市場や工場は閉まっているので、イルクーツク製品を何も買うことなく、この列車で又タシケントに帰るのです。帰りの駅駅で又商売ができます。昨日のぽっちゃりウズベク顔の車掌さんが、「この列車はどうだったかね」と聞くものですから、「おもしろかったわ。さようなら」とちゃんとウズベク語で答えました。
確かに面白かったです。でも、「贅沢な」旅になれた日本人にはすすめられません。車内はとても汚れています。ウズベキスタンの列車にくらべれば、ロシアの列車は豪華ホテル並です。1月のモスクワ旅行の時、シベリア鉄道では、トイレに苦労しました。駅に停車中やその前後2、30分はトイレが使えないよう鍵がかかるのです。でも、タシケント列車は、鍵なんて壊れていて、いつでも使えます。でも、自分が使う時は、、、
イルクーツクには4日半いました。列車代は安かったですが、ホテル代が1泊4000円と高かったので、出張旅費がぎりぎりでした。知り合いに頼んで、ホテル代は少し割り引き料金にしてもらいましたが。
今回の訪問は、日本語の授業をしている大学、学校、友好協会の他、イルクーツク州庁の保健局へも行ってきました。日本ユーラシア協会からの調査依頼の項目に、イルクーツク住民の保健医療環境というのもあったからです。
メールがすごく長くなってしまいました。最後まで読んでいただいてありがとうございました。金倉孝子
(編者注:金倉先生のことは、1996年秋の朝日新聞社会面で大きく取り扱われている。切り抜きをとっておいたが、今、所在不明である。先生はクラスノヤルスク在住の唯一の日本人として、教鞭をとるかたわら、通訳としてもご活躍中である。)
「おろしゃ会」7号の寄稿者に宛てて
加藤様
奥山@高山市図書館です。ギリギリセーフといったところですか。本当は五十棲氏に宛てた部分で触れた大黒屋光太夫か杉野兵曹長について書きたかったのですが、多忙につき7号に寄せられた方々への私信という形を取らせて頂きました。(プライバシー的にマズいと思われる部分はカットして頂いて結構です)
年初めに研究室にお邪魔した時、急逝なさったとおっしゃられていたのが確か左近先生でしたよね。先生にはいろいろお世話になっているにも関わらず期待にそぐえず申し訳ありません。取り急ぎ。以下が原稿です↓
「おろしゃ会」7号の寄稿者に宛てて
年初めに加藤先生の研究室を訪ねる機会がありました。そこで7号の冊子を渡され、初めてじっくりと皆さんの原稿に目を通しました。というわけでできあがったのが今回の投稿です。
早坂氏へ
"研究方法は劇的に進化する"の部分で1970年代初頭の大学図書館に触れられている部分が印象的でした。ラテンアメリカ地域と比べ東欧・ロシア地域はインターネット関係のデータベースも充実しているようですね。先に、ビジネス支援図書館協議会のビジネス支援情報源リストのWeb部門の作成に携わった折、貿易関連のサイトを調査していてそう思いました。ラテンアメリカ地域もJETROアジ研にいつまでもおんぶにだっこではいけないのですが・・・。
故左近氏へ
私の文章をとても楽しみにしていて下さったと伺って本当に残念です。東京外語と言えば私が現役当時第一志望で目指していた大学当時のキャンパスは開学以来の西ヶ原にあり、近くに激安のトンカツ屋(店主は不慮の死を遂げたそうです)があったり、巣鴨のとげぬき地蔵(おばあちゃんの原宿)があったりと面白いところでした。現キャンパスは三多摩の東京スタジアムの方に移ったと聞きます。
ドミィトリエフ氏へ
現在信州松本にお住まいとのこと。文化圏的に非常に近い飛騨高山、北アルプスを隔てたところで住んでいるだけに親しみを感じます。昔、富山(氷見)で水揚げした寒ブリを高山経由で松本まで運んでいたことはご存じでしょうか。野麦峠が女工さんたちがモデルの話『あゝ野麦峠』で有名になるもっと以前のことです。富山・高山間は越中ブリ(米一升の価値)、高山・松本間は飛騨ブリ(米一俵の価値)があるとされていました。昨年研修で訪れた富山県立図書館には環日本海資料を中心に集められている資料のコーナーがありました。イゴリ氏がみえる新潟ラインも強固ですが、富山経由のロシア情報もなかなか捨て難いものがあります。
イゴリ氏へ
その略歴を読んでとても親近感を覚えました。なぜならまず名大の国際開発にいらしたことがあるということ。ここは社会科学系で研究をしていきたいスペイン学科生が進学を希望する場合に、筑波か神戸か名大かと選ぶ選択肢の一つであり、過去沢山のスペイン学科生をはじめとする県大のOB・OGの方々が学ばれています。
次にご専門が移民問題や明治政府の対外政策であるということ。広瀬武夫の研究を通じて明治政府の政策再評価を試み、また著書『北南米への日本人移民の歴史』はスペイン学科でも多数卒論等で取り組んだ知り合いがいて、一度拝見したいなと思った次第です。
五十棲氏へ
私も三重県「津市」出身の26歳です。「中学・高校時代に先生と出会われた」という書き方をみると、加藤先生は北勢のどこか私立にでもみえたのでしょうか。(高校教師から転じて大学教員という例は県大において珍しいことではありませんから)
私は学科は違えど外国語学部出身なので、中等教育課程での外国語選択について地域性を出す、例えば九州では韓国語、富山・新潟北海道あたりではロシア語かなと想像していたのですが、文脈を拝見する限り現実はそう甘くないようですね。
三重県はロシアと縁が深いんですよね実際。F1で有名な鈴鹿サーキットのある鈴鹿の白子出身の大黒屋光太夫に、日露戦争で名を馳せた杉野兵曹長。パルケエスパーニャやバレンシアオレンジを通じたスペインとの繋がりだけじゃないぞ三重はという気がします。
春の反省(&次回予告)
今回、『おろしや会』創立四年目のめでたき春に発行される今号に、誠に勝手ながら自らの言葉を載せることができなくなった鈴木です。昨今の学生によくありがちな、追い詰められ、逃げ場がなくなった結果出した答えがこれです。本当にお恥ずかしい限りです。
そもそも、予定としては、相当長い時間(約二年)をかけ、加藤先生に多大なご迷惑と心配をおかけして完成した問題の卒業論文の総括を載せるつもりでした。卒論の口頭試問で、副査を担当していただいた、英米学科の吉瀬先生に、学問の何たるかをご指導いただき、自分の学問への可能性に胸をわくわくさせてコンピューターの前に座した私だったのです。が、文章を書き進めるにつれ、自分の研究のいたらなさに絶望したのです。このような中途半端な文章のままでこの『おろしや会』会報に載せる訳にはいかない!という一学生のはかないプライドによって、今回の運びとあいなりました。
こうやって時間をかけることで次回益々プレッシャーが大きくなることは目にみえておりますが、それとともに研究に対する高揚感、広がりは、益々大きくなっているのでした。
何やらつらつらと書きましたが、これは要するに言い訳です。書けなかったのです。学生は言い訳する生き物です。しかし、加藤先生のおっしゃるとおり、過去をいつまでも振り返ってばかりではならないのです・・・・・。
今日は春の嵐が吹き荒れていました。桜の花も風にまきあげられて、青く、高い空にすいこまれていきました。その様を見て私は思いました。春は始まりの季節です。そして、変化の時期でもあります。私は頭を切り替え、次号に向かって進むのです。では、次回の予告です。もちろん次回は卒論の総括を掲載したいと願っております。もちろん、他にも計画はありますが、あまり調子のいいことを言うと失敗するので、そこはお楽しみ、ということでご容赦願いたいと思います。
今回、何も載せないのは罪、会員として何でもよいから書けとの命を受け、このような長い言い訳話を書いています。その私の横では平岩君が会報の仕上げを、正面では加藤先生がお仕事をなさっています。こんな状況でこの原稿を書いている訳です。笑えます。あと何度、私はこんな状況に自分を追い詰めるのでしょうか・・・。それでは、またの機会に。次回は果たしてどちらに
転ぶのでしょうか。
追悼 左近 毅 先生
今年1月4日、左近先生の急逝の報に接しました。「えーーー」というほど驚きました。といいますのも、昨年12月15-16日、名城大学で第2回日露戦争研究会を開催しましたときに、左近先生に発表していただいたからです。発表だけではありません。研究会のあと、知多半島の内海温泉での懇親会に行ったのですが、そこでも夜12時過ぎまで、一緒に酒を飲んでいました。しかも、つまみを持ってきてくだるような心配りもされ、さらに、疲れを知らずよくしゃべり、酒量も決して少なくありませんでした。確かに先生は、皮膚がんを患われており、昨年春には大阪市立大学病院に入院されておりました。しかし、入院中も精力的にお仕事をされ、ヴィターリー・グザーノフ著『ロシアのサムライ
: 日露の歴史をあやなすモザイクの世界』左近毅訳(元就出版社, 2001)を、昨年6月には出版されております。また、雑誌『セーヴェル
= Север』 ハルピン・ウラジオストクを語る会の中心的な執筆メンバーであられ、おもしろい論考を多数書かれておりました。一昨年名城大学で講演していただいた際にも、昨年12月の内海温泉でも、わざわざ京都から車でこられています。その先生が、研究会から半月ほど後に亡くなられるなど、私には信じられないのです。
私が左近先生とはじめて会ったのは、1994年にロシア人の友人デー・ベー・パヴロフの著書を成文社から翻訳されたときでした。パヴロフが来日した際に、翻訳の御礼を言いたいというので、会見をセットしたのがはじまりでした。私が4年前に横浜の短大から名城大学に移ると、東京からの帰りだと申され、私の研究室に寄られ、当時私の研究室にあった「川上俊彦文書」(現在は国会図書館憲政資料室に寄贈)に目を通されて行きました。その後も、ロシア語能力が低く翻訳がうまくいかない私の質問に親切に答えてくれました。昨年2月に私が出版した『ロシア共産党文書館日本関連文書目録』(ナウカ、2001年)の索引作成でも、貴重なアドバイスを多数いただいております。日露戦争研究会を設立しようとしたときにも、主要メンバーとして参加することを確約してくれました。まだまだ、いろいろとアドバイスいただきたいことがありましたのに、ショックが隠し切れません。
左近先生の業績は偉大です。数々の翻訳をなされております。その一端を挙げると、次のようになります。
アンリ・アルヴォン著『アナーキズム』左近毅訳(白水社、文庫クセジュ
; 520、1972)
バクーニン [著]『バクーニン著作集』1 ? 6、外川継男,
左近毅編(白水社, 1973)
H.M.ピルーモヴァ著『バクーニン伝』1?2、佐野努訳、左近毅解説
; [1], [2](三一書房, 1973)
トロツキー[著]『われわれの政治的課題 : 戦術上および組織上の諸問題』藤井一行,左近毅訳(大村書店,
1990)
デー・ベー・パヴロフ, エス・アー・ペトロフ著 ; イー・ヴェー・ヂェレヴャンコ史料編纂『日露戦争の秘密
: ロシア側史料で明るみに出た諜報戦の内幕』左近毅訳(成文社, 1994)
ナターリヤ・エム・ピルーモヴァ [著]『クロポトキン伝』左近毅訳(法政大学出版局、叢書・ウニベルシタス
; 457, 1994)
ジョージ・ケナン [著]『シベリアと流刑制度』1、2、左近毅訳(法政大学出版局、叢書・ウニベルシタス
; 519-520, 1996)
ミハイル・バクーニン [著]『国家制度とアナーキー』左近毅訳(白水社,
1999)
以下のように、著作も多彩です。
『解説・総目次・索引』(緑蔭書房、賀川豊彦関係史料双書
; 4 『世界国家』別冊, 1992)
奥村剋三, 左近毅編『ロシア文化と近代日本』(世界思想社,
1998)
Такеши Сакон,Сибирь начала
XIX века глазами
японца ,(1999)
堀江満智著『遥かなる浦潮(ウラジオストック) : 明治・大正時代の日本人居留民の足跡を
追って』左近毅監修・解説(新風書房, 日露交流叢書 ;
1、2002)
偉大なロシア研究者であられた先生がもうこの世におられないことが、どれほどロシア研究にとって大きな痛手であるのか、計り知れません。しかし、悲しんでばかりもいられません。先生の亡き後も、みんなで力を合わせて日露戦争研究会を続けていかなければならないからです。先生が天上から見守ってくれていることを頼りに、日露戦争百周年に向かってがんばっていきたいと考えております。
最後に、あらためて左近毅先生のご逝去に、心から哀悼の意を表したいと思います。
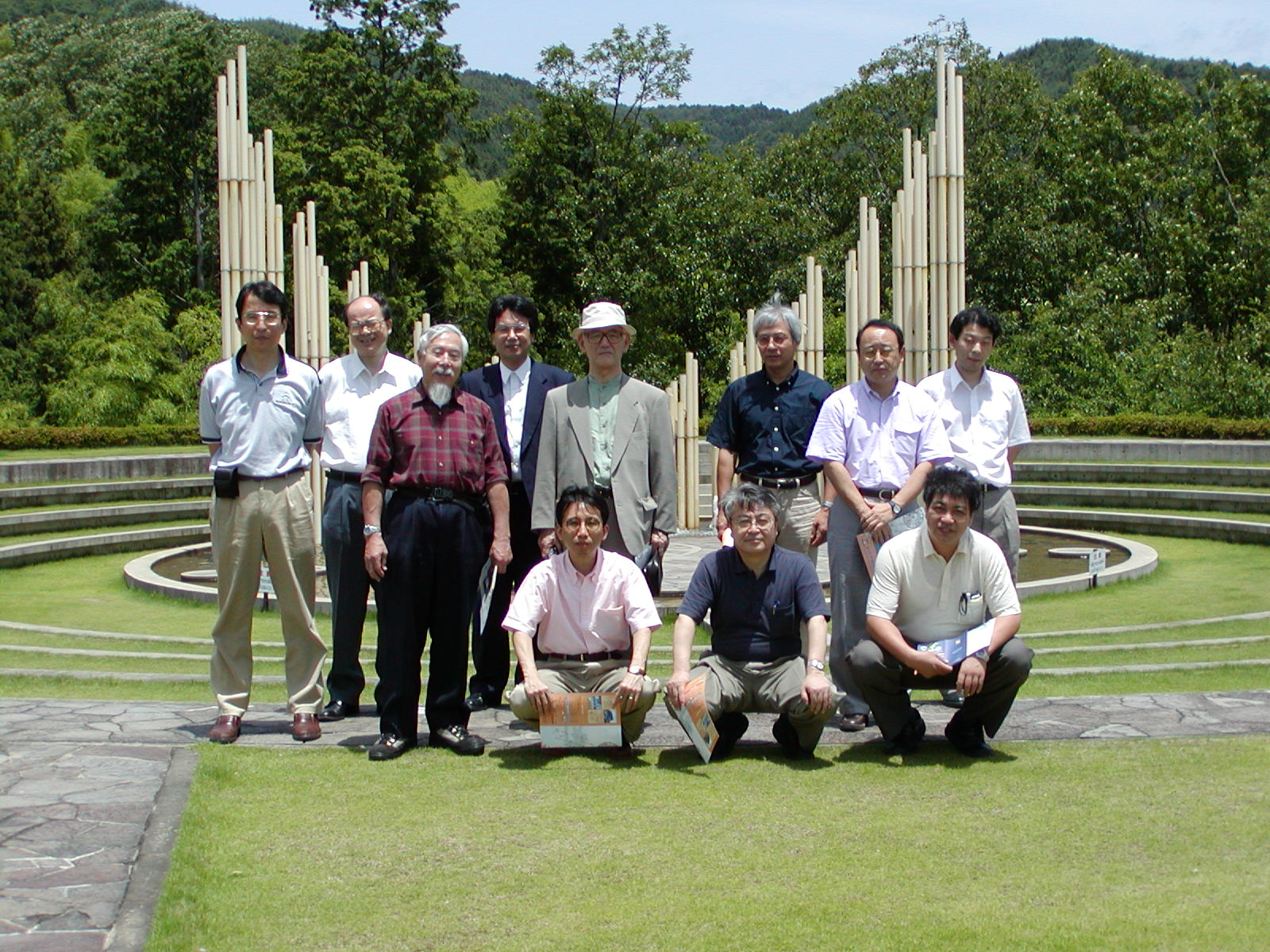
2001年7月 日露戦争研究会発足の合宿で杉原千畝記念平和公園を訪ねる
左から三人目、顎鬚をたくわえておられるのが、故左近先生(加納 格氏写)
おわりに
この第8号も大学の入学式シーズンにあわせ、何とか発行にこぎ着けた。最近の発行は、第4号が2000年4月8日、第5号が12月8日、第6号が2001年4月8日、第7号が10月8日といった具合であり、1年に2回のペースとなっている。
本号にも多方面から貴重な原稿をいただいた。巻頭エッセーの中村喜和先生が講師をされていた前年度のNHKラジオ「ロシア語講座<応用:ロシア民話の世界>」を、編者(平岩)は毎回聴講していたので、先生から寄稿していただいたことは「おろしゃ会」学生一同にとっても、大変光栄なことである。ロシア科学アカデミー研究員で日本滞在中のジェレズニャク女史の論文は、ロシア国内の日本語教育についての重要な資料であり、ロシア語をこれまで学習してきた学生や、これからロシア語を勉強しようと考えている新入生にとって必見である。また、東京大学大学院の乗松氏は「ムムー論」の中で、愛知県立大学・ロシア語上級クラスで「むむ?っ!」と唸りながら読んでいた難解なツルゲーネフの小説を、ロシア文学の現代的解釈というテーマと絡めつつ、明快に解説してくだった。他にも多くの方から素晴らしい論文・エッセーをお寄せいただいたことに、この場を借りて深くお礼申し上げたい。
さて、昨年秋以降のサークルの近況報告をすると、11月2・3・4日に学内で催された「第4回県大祭」におろしゃ会も模擬店を出店、ブリヌィとロシア紅茶を販売した。設立3年目にして初の大学祭参加でもあり、サークルにとって一つの転機であったことは確かである。大変な仕事ではあるが、売り上げによって財政面に余裕ができるので、後輩会員には次回以降も続けてほしい。11月10日には紅葉見物をかねて名古屋・平和公園へエクスクールシヤ(遠足)に出かけ、夕方ロシア料理「ロゴスキー」で懇親会を開いた。この半年間の行事が以上のように少ないのは、各自卒論、英語講読など「勉強」で忙しかったためである。楽しいサークル活動があるに越したことはないが、それが動機づけとなって研究意欲がわいてくるのであれば、結構なことではないか。
5月には私ども愛知県立大学に、おろしゃ会設立して初めてのロシア人留学生・マリーナ・ロマーエワがやってくる。昨年のクラスノヤルスク訪問団の通訳を務めた彼女は、その後代表団の招きで一度来日し、加藤史朗先生のご尽力により特別聴講生というかたちで留学が実現した。日本とロシアの学生がお互いに触発されながら学ぶことで、きっと実り多い3ヶ月となるだろう。
春になり、新しく「おろしゃ会」の門をたたく者もいれば、大学を去っていく卒業生もいる。このサークルでの活動が、学生、研究者、社会人、そして参加したすべての人々にとってかけがえのない一瞬であることを願う。(平岩)