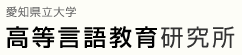2008年度研究活動・報告
第3回 言語教育研究会
以下のように開催されました。
日時:2009年3月6日金曜午後1時から午後5時
会場:外語棟3階会議室E305
研究発表
小柳公代(フランス学科)「嘘を言わないパスカルが用いただましの言説テクニック」
北尾泰幸(愛知大学)「英語分裂文における多重焦点について」
宮浦 国江(英米学科)「認知言語学と英語教育(1) 放射状カテゴリーを中心に」
大森 裕実(英米学科)「国際英語の視点とEFL環境 -Nativelikenessとの相克関係か相即相入関係か-
講演会「ICTを活用した英語教育 ―Nintendo DS と e-Learning 」柏原郁子氏
以下のように開催されました。
「ICTを活用した英語教育 ―Nintendo DS と e-Learning 」
〈講師〉 大阪電気通信大学工学部英語教育研究センター 柏原郁子 准教授
〈日時〉 平成21年1月28日(水)15:00~17:00
〈場所〉 愛知県立大学学術文化交流センター小ホール
〈主催〉 地域連携センター 文理連携研究会、高等言語教育研究所、情報科学共同研究所
〈チラシ〉 ダウンロード pdf
第2回 言語教育研究会
以下のように開催されました。
日時:2008年10月28日火曜 午後1時より午後5時まで(新県大ファンファーレ期 間中)
会場:愛知県立大学 学術文化交流センター2階 小ホール
研究発表
糸魚川美樹「愛知県立大学『医療分野ポルトガル語・スペイン語講座』からみたスペイン語教育」(仮)
堀田英夫「地域コミュニケーション支援のための特定領域スペイン語教育」
森田久司「生成文法の言語モデルの特異性およびその根拠 - 日本語WH疑問文の一考察 -」
劉 乃華「教室における中国語文法教育のプログラム」(通訳 竹越孝)
長沼圭一「英語とフランス語における国籍を表すコピュラ文について」
多言語競演レシテーション大会
2008年11月2日に第1回多言語競演レシテーション大会を開催しました。多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。
会場からの投票で最優秀賞と優秀賞を選んでいただきました。
第1部(学習歴1年目)最優秀賞スペイン語: [スペイン学科1年] Federico García Lorca “Romance sonámbulo” (フェデリコ・ガルシア・ロルカ「夢遊病者のロマンセ」) 優秀賞 中国語: [中国学科1年] 漢詩三首 孟洪然「春暁」、王維「送元二使安西(元二の安西に使するを送る)」、朱熹「偶成」 第2部(学習歴2年目以上)最優秀賞フランス語: [フランス学科] Antoine de Saint-Exupéry “Le Petit Prince II”(星の王子さま II) 優秀賞 英語 [英米学科] A scene from “Dead Poets Society”(『今を生きる』の1シーンより) |
審査委員会により、以下の二つの賞の受賞者が選考されました。
| 学長賞 英語 [英文学科3年] Severn Suzuki “A Plea for our Planet” 外国語学部長賞 ポルトガル語: [英文学科1年] “História da Imigração Japonesa no Brasil”(ブラジルに渡った日本人移民の歴史) |
上記受賞者には、賞状と愛知県立大学後援会からの副賞が授与されました。
展示企画「世界のあいうえお表」
「新県大ファンファーレ」(2008年10月-11月)の期間、世界の「あいうえお表」の展示をしました。古代文字史料館での紹介ページを下に引用します。
| 世界の「あいうえお表」の展示 過日(10月28日から11月5日まで)、愛知県立大学の一階ロビーで各種文字表の展示があった。これは本学の高等言語教育研究所が主催し、古代文字資料館が協力して行われたものである。比較的短い収集の期間であったが、学生や教員の協力のもと、ぞくぞくと(?)、世界各地より絵入の文字表(あいうえお表)が集まった。これは、現地の子供たちが文字を学ぶ際に使うものである。集めてみて、類似した文字表が世界の各地にあることに驚いた。  
集めた文字表を系統ごとにまとめると次のようになる。 |
世界のあいうえお表
お国柄が反映した絵入りの文字表の展示です。タイ文字、ラオ文字(ラオス)、デーバナーガリー文字(インド、ネパールなど)、ハングル、英語アルファベット、平仮名など、楽しい「あいうえお表」があります。 日時: 10月28日(火)~11月5日(水) |
県立大すべて大公開(仮称)参加展示企画
『世界のあいうえお表』へのご協力のお願い
「県立大すべて大公開」参加展示企画として、古代文字資料館の協力を得て、世界の文字教育資料の収集と展示を高等言語教育研究所で構想しました。
幼児や児童の文字教育のために各国で市販されている絵のついている文字表と文字練習帳(できるなら文字の書き順が分かるものがよい)を入手し、文字のしくみや成立史などの研究発表を加え、学内に展示するという企画です。絵入り文字表と文字練習帳の入手につきまして、ご協力賜りたくメールしています。お手元にそのような資料がありましたらお貸しいただきたく、あるいは譲っていただきたくお願いします。また、近く海外に出かけられる先生におかれましては、現地にてそのような文字表の入手を賜りたくお願いいたします。
担当の吉池孝一 高等言語教育研究所運営委員 までご連絡ください。
現在、古代文字資料館に以下の資料がありますが、同じ文字の資料であっても、それぞれに特徴がありますのでダブっても価値あると思われます。時代や作成者が異なれば、違いあることが予測されますので、入手にご協力下さい。
インドのデーバナーガリー文字ヒンデイー語の文字表と練習帳
ラオスのラオ文字ラオ語の文字表と練習帳
タイのタイ文字タイ語の文字表と練習帳
日本の平仮名日本語の文字表と練習帳 イギリスのラテン文字英語の文字表と練習帳
他に、個人のところに
スペインの絵入スペイン語文字(アルファベット)帳
中国の絵入「漢語ピンイン字母」表 があります。
(以下趣意書抜粋)
幼児や児童の文字教育のために各国で市販されている絵のついている文字表を各国から収集し、これをポスターとして展示することによって、愛知県立大学学生、訪れた一般の方、それに高校生に世界の言語と文化の一端を視覚で体感してもらう。同時に本学での多彩な外国語教育の存在をアピールする。
外国語教育・外国語学習において、文字教育や文字を覚えることも大きな位置を占める。幼児や児童が、文字を覚えるのに、絵と結びつけて覚える方法がある。文字が絵から派生したことを考えると、それは一つの有効な手段である。文字とともに掲げられた絵は、その言語が用いられる土地の文化や自然など風物を反映しているものもある。
本学には、英語、ドイツ語、アイスランド語、フランス語、スペイン語、カタロニア語、ポルトガル語、ラテン語、ギリシャ語、ロシア語、中国語、韓国朝鮮語、タイ語、日本語の授業が開講されていて、また、世界各地をフィールドとした研究者がいるので、世界各地の言語の絵がついた文字表を収集することができる状況にある。
本学の古代文字資料館では、古代文字資料の収集と研究の経験があり、その協力を得て、今後、収集した文字表によって、世界各地での文字教育方法について研究する。
幼児や児童の文字教育のために各国で市販されている絵のついている文字表を各国から収集し、これをポスターとして展示する。また、日本ではあまり目にしない文字の場合、その文字の仕組みや成立、その文字を使う言語などの概説をまとめ小冊子にする。
学外に対しては、本学の外国語教育・研究への取り組みを周知することで、学生募集へ効果、地域の理解が期待される。 学内に対しては、学生の世界への関心を高め、勉学の意欲を高めることができる。
第1回 言語教育研究会
以下のように開催されました。
日程:2008年 8月7日木曜 午後2時より午後5時まで
会場:学術文化交流センター2階 小ホール
第1部 研究発表
森田久司「To不定詞と動名詞の使い分け:メガフェプスダから進歩したか?」
宮浦国江「本学英語教育体系化・リソース化・可視化の試み」
堀田英夫「地域コミュニケーション支援のための特定領域スペイン語教育」
第2部 座談会
「愛知県立大学における外国語教育と高等言語教育研究所の役割」